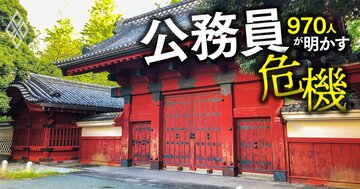上に立つ人は、権力を抑制的に使うべきだ
パワハラを「見て見ぬふり」をさせない体制を構築
私は、長谷川元副大臣の話は承知していないのですが、政治家、特に政務三役(大臣、副大臣、政務官)は、官僚の力をどうやって引き出すかを考える立場です。それなのに、パワハラをやって萎縮させてしまったとしたら、まともな意見や政策が出てくるのか、ということです。
最近は、上に立つ人の心構えというか、コモンセンスがなくなってきた気がします。選挙に出て、人の上に立とうという人間は、抑制的に権力を使わなければいけない。ギンギラギンに権力を行使したのでは、恐ろしがって誰も付いてきません。
――政治家からのハラスメントを防御する側の役所としては、どう対応するべきでしょうか。
ハラスメントを見聞きした上司や部下が、通報するシステムが機能してしかるべきですが、残念ながらそうなっているとはいえないかもしれません。
――見て見ぬふりをされてしまうケースが多いのでは。ダイヤモンド編集部は、ダイヤモンド・オンライン上で、公務員へのアンケートの回答を募集中ですが、これまでに届いている回答を見ると、役所内のハラスメントの通報窓口への信頼性は高くありません。
これは言いづらいんだけど、兵庫県の場合は、元県民局長(故人)からの公益通報を受けた県庁がきちんと対応できなかったといわれている。そうだとすれば、県庁として体制に不備があったといわれても仕方がないと思います。
――その点について第三者委員会の報告書でも違法性を指摘されたのに、齋藤元彦兵庫県知事は責任を取りませんでした。
一般に、御身大切で、自分は巻き込まれなくないと言いだしたら、誰も物を言えなくなります。上に立つ者が「遠慮なく言ってこい」と言うしかない。わが省では、もし(パワハラなどが)起こったら直ちに上に知らせろ、大臣に言えと普段から伝えています。通報や告発をした人を徹底して守ることが大事です。
 むらかみ・せいいちろう/1952年生まれ、東京大学卒業。河本敏夫衆議院議員(元通産相)秘書から86年衆議院初当選(旧愛媛2区)後、13回連続当選。第2次改造・第3次小泉内閣で国務大臣(行政改革・構造改革特区・地域再生担当)・内閣府特命担当大臣(規制改革・産業再生機構担当)。小泉政権では郵政民営化を問う解散に閣議で異論を唱え、安倍政権では安全保障関連法案採決の本会議を欠席、また最近では原発再稼働に反対するなどリベラル保守の立場から時の政権に物申してきた。著書に『自民党ひとり良識派』(講談社現代新書)。村上水軍の末裔。父信二郎氏も衆議院議員だった。2024年10月より現職。 Photo by Y.W.
むらかみ・せいいちろう/1952年生まれ、東京大学卒業。河本敏夫衆議院議員(元通産相)秘書から86年衆議院初当選(旧愛媛2区)後、13回連続当選。第2次改造・第3次小泉内閣で国務大臣(行政改革・構造改革特区・地域再生担当)・内閣府特命担当大臣(規制改革・産業再生機構担当)。小泉政権では郵政民営化を問う解散に閣議で異論を唱え、安倍政権では安全保障関連法案採決の本会議を欠席、また最近では原発再稼働に反対するなどリベラル保守の立場から時の政権に物申してきた。著書に『自民党ひとり良識派』(講談社現代新書)。村上水軍の末裔。父信二郎氏も衆議院議員だった。2024年10月より現職。 Photo by Y.W.
総務省は、職員の働きがい
キャリア形成をサポート
――総務省では最近、職場の活性化のために何を変えましたか。
まず、局長以上に定期的に大臣室に集まってもらい、担当分野に限らず広い視点で、わが国の将来、今後の総務省の在り方について自由に意見を述べてもらっています。また、大臣レクのときなどにも、個別課題の深掘りをするためフリートーキングをするようにしています。このほか、各分野から覇気のある若手を集めて「チーム村上」という勉強会を開き、政策を練っています。大臣に直接、意見が具申でき、自分の提案が官邸の経済財政諮問会議に反映されるチャンスがある。これまで以上に、そういう形で政策立案に参加したり、大臣と対話したりすることを増やしていきたいと思います。
省内では、自分から提案しようという機運が高まっています。私がこういう(ざっくばらんな)性格だからということもありますが(笑)。
――どのように人事の運用を改革していますか。
結構、努力しています。具体的には、次官級幹部自らが所信表明スピーチをして、総務省の意義や、職員に期待することを語っています。
また、各管理職が「働き方マネジメント宣言」をして、組織のミッション、働き方の方針を表明、共有しています。もう一つは、職員自身が自分のキャリアを積極的に考え、成長できるようにしています。例えば、省内の20ぐらいのポストへの人材配置を公募しています。異動を希望する若手職員が手を挙げて、適性を見て登用しています。
また、総務省から企業に転職した人材に、中途採用で戻ってきてもらっています。今後も、多様なキャリアを持つ人材に活躍してもらえるようにしていきます。
――地方自治体も含め、優秀な人材を採用し、辞めないようにするにはどんな工夫が必要でしょうか(地方自治についての詳細は本特集の#5『「県庁も道州制も不要」発言の真意を村上総務相が激白、人口が半減する時代を見据え議論を本格化する』5月17日〈土〉配信予定)。
われわれの世代は、国民からリスペクトされて、天下国家を大所高所から議論できれば、給料が安くても構わない人が少なくありませんでした。
ところが今(公務員は)は、給料、待遇は悪く、リスペクトはされないというイメージで語られる印象です。これでは人材は来ません。だからこそ、皆が自由闊達に政策や哲学を提案できるようにすることが重要です(詳細は本特集の#3『村上総務相が語る、中央省庁の「忖度文化」を改める秘策とは?“国家中枢の危機”は政治が招いた』参照)。
大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、真美子夫人の出産に立ち会うため産休を取ったように、子育てと仕事を両立できるようにすることも欠かせません。男性の育休取得も大事です。多彩な人材が活躍できる環境づくりは、われわれ政治家の責務だと考えています。
Key Visual:SHIKI DESIGN OFFICE, Kanako Onda