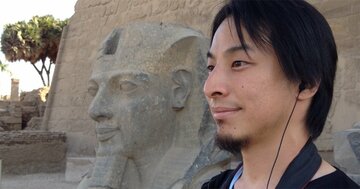プログラミングの思考は
人間関係にも応用できる
ひろゆきによれば、プログラマーにとってコンピューターとは、「宇宙人か謎の生物」のようなものだ。つまりそれは原理的に「私」を理解してくれないし、「私」からも相手を理解できない存在である。しかし、そうしたコンピューターも、こちらが正しく命令すれば、それに応えてくれる。ここにプログラミングの大きな魅力がある。「命令した通りの結果が出る快感」を抱いているという点に、プログラマーの基本的な価値観があると、彼は指摘する。(編集部注/『プログラマーは世界をどう見ているのか』(西村博之・SB新書、2022年)を参照)。
この「快感」は、彼が議論において相手を論破する際、その動機となる支配欲と、ほとんどそのまま重なり合う。つまり彼は、コンピューターに対してソースコードによって命令するように、議論において相手を追い詰めるのである。
彼は、議論におけるやり取りによって自分の仮説を検証し、その仮説が正しければ、相手を論破することに成功する。それは、プログラミングの命令が正しければ、コンピューターが思った通りの挙動を示すのと同じである。
だからこそ、彼は相手から理解されたいとも、相手を理解したいとも思わない。彼にとって議論の相手は、思い通りに動かそうとする存在でしかないのであり、その限りにおいて、コンピューターと何ら変わらない。言い換えるなら、それは「宇宙人か謎の生物」以上のものではないのである(編集部注/『プログラマーは世界をどう見ているのか』(西村博之・SB新書、2022年)を参照)。
実際に、ひろゆきはプログラミングの思考を現実に人間関係にも応用することを推奨している。
(編集部注/『プログラマーは世界をどう見ているのか』(西村博之・SB新書、2022年)。
彼の論破芸は、しばしば詰将棋のようだと言われることがある。しかし、実際には彼がそこで演じているのは、複雑なコミュニケーションによるプログラミングに近いものなのだろう。彼が相手に向けるまなざしは、コンピューターの画面に向けるそれと、本質的に変わらないのである。
プログラマーの倫理に
基づいた議論の言動
プログラミングの思考が議論に応用されるのだとしたら、議論における言動は、通常のそれとは異なる価値観に基づいて展開される。つまりそれは、プログラマーの倫理に基づいたものになる、と考えられる。