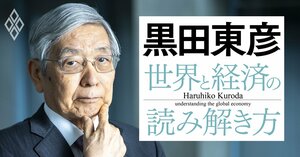いまこそ、ブランドアイコンとしての存在感が活きる
別物だと感じる背景には、あるクルマの存在がある。
今回の展示でも、ID.Buzzの隣に並んだ「Type 2」だ。1950年代から70年代にかけてグローバルで販売されたバンであり「ワーゲンバス」とも呼ばれる。ちなみに、38年にプロトタイプを生産した「ビートル」が同社にとっての初量産車「Type1」ということになる。
生産中止後も、ヘビーユーザーが世界各地におり、近年は車中泊をしながら各地を巡るライフスタイルである「バンライフ」の象徴として根強い人気を維持している。
日本でも、コロナ禍以降でキャンピングカーブームとなったこともあり、Type2に改めて注目が集まり、中古車市場ではレストアした50年落ち車が400万~500万円で取引されている状況だ。
Type2が今でも愛されている理由は、商用と乗用を兼用できる独特の車内空間と、その空間が外からもひと目で分かるエクステリアデザインにある。フロントマスクの表情が愛らしく、かわいらしい。
いまでは、「ミニバン」が日本を中心として人気カテゴリーとして定着しているが、その原点にType2がある。
 「ID.Buzz」オマージュの原点、「Type2」(写真手前) Photo by K.M.
「ID.Buzz」オマージュの原点、「Type2」(写真手前) Photo by K.M.
そんなエポックメーキングをEVでも引き起こそうと、ID.Buzzが企画されたのだ。
ただし、期待は大きかったのだが、量産までかなり時間を要した。
2017年にプロトタイプが登場し、2019年のドイツ・
その中のひとつが、ID.Buzzだ。
筆者は同ショーの現場で実車を見たが、第一印象は「Type2のオマージュとして、わかりやすいブランドアイコン」というものだった。
EVプラットフォームをID.シリーズが共用することが前提であるため、ID.Buzzが量産される可能性が高いとその場で感じた。
それから6年を経て、ID.Buzzが日本で発売されたわけだが、その間に欧米中韓日のメーカーからさまざまなEVが登場し、日本で発売されている。だが、グローバルでは政治主導によるEV普及が頭打ちとなり、「EVは踊り場」といわれる状況にある。
だからこそ、ブランドアイコンとして多くの人から賛同を得やすい、ID.Buzzの存在が目立つように感じる。