株主提案はたとえ否決されても
出すことに意味がある!
繰り返しになるが、日本の会社では株主提案はほとんど可決されない。あるいは、株主総会で株主が質問する際に提案をしても、「動議ですか?議長の立場からは反対です。反対にご賛成の株主様、拍手をお願いします。はい、過半数の承認を得ましたので、株主様の動議は反対となりました」といった感じでいとも簡単に否決される。
しかし株主提案が否決されても、総会で動議が反対されても、それでおしまい何の意味もありませんでした、というわけではない。
会社側は全面的な対立を避けたがる。重要そうな株主提案には事前にコンタクトし、一部の要求を受け入れるなどして株主提案の勢いを削ごうとする。動議も芯を食ったものであれば、必ず対策を練る。
反対と賛成が僅差であればニュースになり、その会社の経営陣は、声を上げない多数の株主が潜在的な不満を抱いていることを思い知る。翌年にもっと悲惨な状況にならないよう株主を納得させるような施策、あるいは経営改善案を積極的に考えるようになる。
また、いくら大企業の取締役であっても、面と向かって大声で罵詈雑言を浴びせられたらキツい。アクティビストに強く言われたから屈した、となれば対外的なイメージは最悪だ。だから、まずは否決するものの、自社で対策を検討するのは当然のことだろう。
もちろん株主にもいろんなタイプがいて、フジの株主総会でも実際、突然に意味不明な質問を叫び始める人もいたし、放送法を理解していない質問も相次いだ。
しかし改めて考えると、大株主の声ですら、否定ありきというのは不思議な話だ。会社側からすると何か違うのかもしれないが、大株主は企業価値と株主利益の最大化という株主からすると至極当然の目的を達成するための提案をしているのだから。
まとめると、株主提案は否決されても反対されても、結局は会社が提案を取り入れて自己改善するプロセスにたどり着く。会社が変わるきっかけはモノ言う株主の声であることを痛感した、2025年の株主総会シーズンであった。
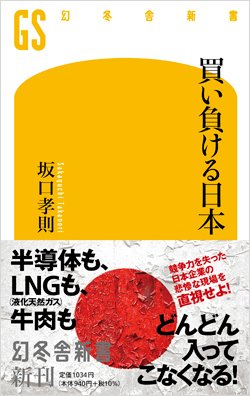 筆者の新刊『買い負ける日本』(幻冬舎)
筆者の新刊『買い負ける日本』(幻冬舎)



