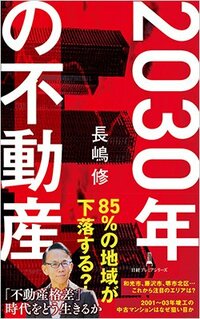大切なのは、焦って結論を出すことではない。5年ごとの計画見直しなどを一つの節目としながら、住民間の意見交換を粘り強く重ねる。そうした地道な合意形成のプロセスこそが、マンションの未来を左右するといっても過言ではないだろう。
加えて、管理会社から提示された見直し案をそのまま受け入れるだけでなく、複数の道筋を示してくれるような外部の専門家へ意見を求めるのも一案だ。
最後に、定まった方針を「形に残す」ことの重要性も付け加えておきたい。総会の議事録や長期修繕計画書にその方向性を明記しておけば、方針の継続性を確かなものになるはずだ。
「終活」を設計できる力が
新たな資産価値になる
繰り返しとなるが、これからのマンション価値は、物理的な頑健さだけでは測れない。資産として機能し、時代の変化に合わせて姿を変える力、すなわち「社会的な寿命」こそが、資産価値を大きく左右する時代に入ったのである。
選択肢が増えたからこそ、将来の方向性を定めず、場当たり的な運営を続けるリスクは格段に高まった。そんな中、最も危険なのは何も決まっていない、という状態にあることだ。
では、どうすればいいのだろうか。その答えは、実は身近なところ、これまで単なる修繕の予定表と見なされていた「長期修繕計画」にある。
管理組合は、5年に一度の見直しが義務付けられている長期修繕計画を、単なる修繕工事の計画としてではなく、マンションの出口戦略まで見据えた「経営戦略計画」として位置づけることが重要になってくる。その場で出口戦略の選択肢をテーブルに載せ、そこから逆算して計画を練り直す。このサイクルを主体的に回し続けることこそ、未来に向けた最大のリスクヘッジであり、新たな資産価値を育む道でもある。未来に向けたその一歩を踏み出す覚悟が、これからの管理組合には不可欠となるだろう。
(株式会社さくら事務所創業者・会長 長嶋 修)
さくら事務所公式サイト
https://www.sakurajimusyo.com/