資産効率向上の努力が
事業報酬が減少させる矛盾
現行制度には他にも問題がある。JR西日本が5月21日に実施した投資家向けのスモールミーティング資料に、会社側の説明として「鉄道事業が中長期的に運賃改定を繰り返すことで安定的なフェーズに入った場合、現行の総括原価方式では、鉄道事業営業利益は800億円程度しか確保できなくなる」との興味深い記述があった。
営業利益が800億円程度で頭打ちになるとはどういうことか。同社に話を聞くと、「現行のレートベース方式には資産効率の概念がなく、資産効率の高い当社はインフレ影響を価格転嫁できていない状況」だという。
レートベース方式が資産額から事業報酬を算定するのは、設備投資に対応する資本コストを確保するためだった。しかし、大規模設備投資が一巡し、むしろ今後は設備のスリム化を進める段階に入った。
JR西日本は、「当社はより少ない資産で効率的に利益を生む企業努力で将来の投資原資を捻出してきたが、現行運賃制度は資産規模に応じて利益額を想定しているため、資産効率を意識し、資産規模を抑えると制度上想定される利益額も小さくなる」と説明する。
つまり現行方式では、資産をスリム化すればするほど事業報酬は減少する。また、この資産縮小は単なる切り捨てではなく今後、深刻化が想定される労働力不足に対応する自動化・機械化を伴う合理化であり、一定規模の投資が必要だが、その確保が十分にできないのである。
同社は「企業努力を上回る水準でインフレが進行すると、これまでの企業努力が消失するまで価格転嫁ができないため、利益が頭打ちないし縮小する」として、「将来の鉄道の持続性に必要な利益を確保するための事業報酬率設定」、「急激な外部環境変化に対応可能な機動的な運賃改定」を国に要望していると述べた。
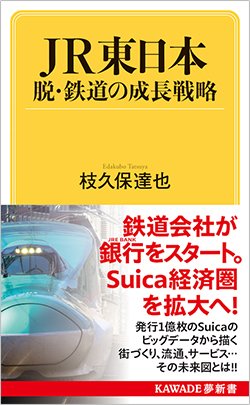 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
国土交通省は2024年4月に「収入原価算定要領」を改定し、設備投資を促進するための減価償却費の算定方法、人件費の算定方法、災害復旧費用の取り扱いなどを改善した。かねて鉄道事業者が要望してきた項目の一部が反映された形だが、JR西日本などの反応を見るにまったく不十分というのが本音のようだ。
国土交通省の「収入原価算定要領の運用改善に関する調査委員会」の資料を見ると、こうした問題意識は国も共有しているようだが、60年にわたって改良を重ねてきた現行の総括原価方式が、人口減少時代に追いつかなくなっているように思える。
日常に根差した鉄道では、先行して運賃自由化が進んだ航空や高速バスのような完全なダイナミックプライシング(変動価格制)の導入は現実的ではないとしても、現行の制度のままでは機能不全に陥るだろう。鉄道利用者は最大のステークホルダーである。鉄道運賃制度というベールに包まれた仕組みに、当事者として関心を持つことから始めねばなるまい。







