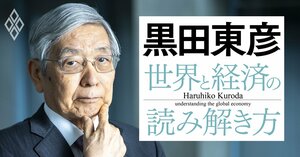小売業に従事する人員数は約1500万人と、米国全体の雇用者数の10%に相当する。小売業で関税コストを全て吸収するには、15%程度の人件費削減が必要になる試算である。雇用悪化は避けられないだろう。
一方で、(3)販売価格を引き上げた場合、販売数が減少する懸念も強い。米国の個人消費は、トランプ関税を見据えた駆け込み消費とその反動減で振幅が大きくなっているが、消費者マインドの悪化により、基調としては明らかに減速している。このうえ、販売価格を引き上げると、深刻な販売減に陥る可能性がある。米国企業としては、トランプ関税の価格転嫁の度合いとタイミングを見定めている状況にあろう。
企業の仕入れコストは大幅に上昇しており、過去の経験則からすると、本格的にインフレ率に影響が及ぶのは夏場と予想される。インフレ率が加速するか、企業が雇用コストを先行して雇用悪化が深刻化するか、FRBとしては頭の痛い状況にある。
トランプ氏の利下げ圧力は
FRBの意思統一の障害
FRBが抱える第三の不確実性は、トランプ氏による政策介入である。トランプ氏は、今年入り後にFRBが金利を据え置くたびに利下げ圧力を繰り返しており、最近は「パウエル議長は(利下げ再開が)遅すぎたことで伝説になる」と述べるなど、パウエルFRB議長に対する個人攻撃を一層強めている。
また、トランプ氏は、来年5月に任期を迎えるパウエル議長の後任を早めに選出する方針を示す。人事面でFRBに揺さぶりをかけ、FRBへの影響力を強める意図があると考えられる。
こうした動きに影響を受けたかのように、FRB内でも利下げに傾く高官の情報発信が目立っている。ボウマン副議長は昨年9月の大幅利下げ決定に対し、ただ一人反対票を投じるなど超タカ派(物価安定のための金融引き締め優先)とみられていたが、足元では利下げに積極的な姿勢を示し、そのスタンスの変化が際立っている。
また、ウォラー理事も7月利下げの可能性を示唆するなど、ハト派(景気下支えのための金融緩和優先)姿勢が目立つ。ウォラー理事は、コロナ禍における高インフレからの脱却において、FRB内で理論的な支柱として重要な役割を果たしてきた。昨年までは、FRB全体の意思決定を代弁するパウエル議長と同様の情報発信が中心であり、中道派とみられてきた。ただ、ウォラー氏の最近の情報発信は、パウエル議長が利下げ時期を明確にしないこととの違いが明確になっている。
ボウマン氏とウォラー氏は、第一期トランプ政権時に、トランプ氏から指名された経緯があることから、トランプ氏の方針に沿った動きをするとの見方がどうしてもくすぶる。二人とも、現在のFRBにおいて重要な位置づけにあり、次期議長の候補としても名前が挙がる人物である。金融政策判断の意思統一が困難となり、情報発信にも混乱が生じている。