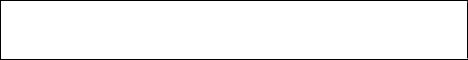板ガラス世界2位の日本板硝子を突然襲った社長交代劇。英国人のスチュアート・チェンバース社長が9月末日に辞任する。就任から1年2ヵ月での退任発表に、株価は8月末日時点で1割近く値を下げたが、今後の経営リスクは、これにとどまらない。
最大の問題は、経営者の人材難。後任に前社長の藤本勝司会長が復帰するが、あくまでも後継者が育つまでのつなぎ。それでも、数年間はとどまると見られている。その間、グローバル経営を推進するトップが不在となる。
日本板硝子は2006年、世界大手の英ピルキントンを買収、「小が大をのんだ」と称された。生産拠点29ヵ国、130ヵ国に展開する企業へと変貌を遂げ、連結売上高の約8割を海外が占める。
そのグローバル化を担っていたのが、ピルキントンを率いていたチェンバース氏。ところが、日本での単身赴任生活が2年間続き、16歳の長男が「見知らぬ他人になる」と懸念、53歳の若さでリタイアを決意した。
「日本の伝統的なサラリーマンは会社を第1に、家庭を第2に置くが、私にはできない」と話す。
ピルキントン買収後の日本板硝子は絶妙の経営体制を築き上げてきた。委員会設置会社に移行し、日本人による監視体制を強化、12人の取締役中、7人を監視役にした。一方で、残り5人の取締役が執行役を兼任、うち外国人が4人に達する。つまり、日本人がにらみをきかせ、外国人が実務を取り仕切る「ハイブリッド型」で支えてきたのだ。チェンバース氏はその要といえた。
同氏の下、買収の後遺症だったネット借入金は約5100億円から目標の約3500億円まで1年前倒しで圧縮。昨秋からの景気後退には、従業員を約6700人削減し、生産能力を2割強落として対応中だ。年間100億円以上のコスト削減で、業績回復の兆しも見えた矢先だけに、先行きの不安感はぬぐえない。
(『週刊ダイヤモンド』編集部 小島健志)