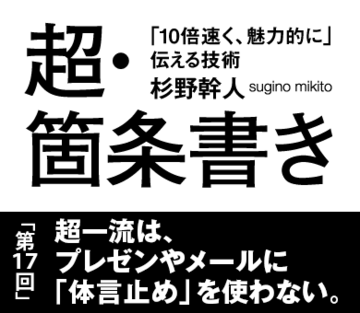戦略コンサル、シリコンバレーの起業家、MBAホルダー、世界のエリートの「新常識」とは?
答えは「Bullet Points(ブレットポイント)」と呼ばれる“箇条書き”によるコミュニケーション。
箇条書きは、英語や会計、そしてロジカルシンキングと同じくらい世界的に求められているスキル。「短く、魅力的に伝える」。それが箇条書きの強みだ。
箇条書きは、メール、プレゼン、企画書・報告書、議事録等、あらゆるビジネスシーンで大活躍する。『超・箇条書き』の著者、杉野氏にそのエッセンスを語ってもらう。(初出:2016年8月5日)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
読み手を混乱させる「8つの言葉」
プレゼンは伝え手主導のメディアで、ペースは伝え手次第だ。「何を話すか」「どう話すか」はもちろん、スライドも普通は一度しか表示されない。
聞き手は、伝え手のペースに合わせて、気を緩めることなく、流れてくる情報を随時、情報処理しなくてはならない。曖昧なところや納得できないところがあっても、聞き手はそこで立ち止まって確認することはできない。もし途中でわからなくなっても、話はどんどん先に進んでしまう。
しかしこれがメールだと、曖昧なところや納得できないところはそこで止まって考えたり、関係ある情報を探したりして理解を深めることができる。ここがプレゼンとメールでは決定的に違う。
そのため、プレゼンでは1つひとつの文のキレが勝負だ。しかし残念なことに、多くのプレゼンでは、読み手の思考停止を誘うような言葉が使われている。さっそく見ていこう。よく見かける使用例もあわせて、紹介する。
(1)「~を改善する」 例:売上を改善する
⇒上手くいっていないのだから、改善するのは当たり前
⇒改善すること自体ではなく、どのようにして改善するのかを相手に伝えないと意味がない
(2)「~を見直す」 例:中期経営計画を見直す
⇒上手くいっていないのだから、見直すのは当たり前
⇒どのようにして見直すのかを相手に伝えないと意味がない
(3)「~を推進する」 例:販売戦略を推進する
⇒やることが決まっているものを推進するのは当たり前
⇒具体的に何をするのかを相手に伝えないと意味がない
(4)「~を最適化する」 例:コスト構造を最適化する
⇒最適化できるならするのは当たり前。最適化したくない人はいない
⇒具体的に何をすると最適化されるのかを相手に伝えないと意味がない