記事検索
「数学」の検索結果:1561-1580/2850件
#10
「高収入」「高ステータス」「安定」のイメージで高い人気と難易度を誇る医学部。その医学部合格者数の上位校には、中高一貫校がずらりと並び、毎年の常連校も多い。医学部に強い学校ランキング、そして常連校で行われている専門講座の気になる中身を大公開する。
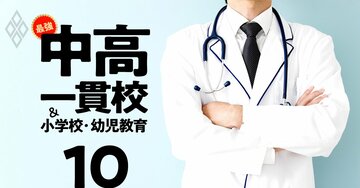
#9
偏差値は低くて入りやすいのに、大学受験に強い、レバレッジの利く中高一貫校はどこか?そんな“掘り出し物”を見つけるべく、独自ランキングを作成した。ここでは、関西など西日本の中学受験者のボリュームゾーンが、進学先の大学として望むことが多い難関私立大学群、関関同立にとりわけ強い中高一貫校のレバレッジ度ランキングを掲載する。

#8
2021年入試で、西の王者、灘中学が受験者数を大きく減らすという珍事があった関西。その中学受験塾関係者の間でささやかれているのが、22年入試への「首都圏の中学受験ブームの関西到来」だ。関西の最新中学受験動向と共に、入学時の偏差値と卒業時の偏差値を基に算出した、入りやすいがその後伸びるレバレッジ度ランキングの【関西版】を掲載する。

#6
偏差値は低くて入りやすいのに、大学受験に強い、レバレッジの利く中高一貫校はどこか?そんな“掘り出し物”を見つけるべく、独自ランキングを作成した。ここでは、東日本の中学受験者のボリュームゾーンが、進学先の大学として望むことの多い難関私立大群、MARCHにとりわけ強い中高一貫校のレバレッジ度ランキングを掲載する。

#5
偏差値は低くて入りやすいのに、大学受験に強い、レバレッジの利く中高一貫校はどこか?そんな“掘り出し物”を見つけるべく、独自ランキングを作成した。ここでは、早慶をはじめとする最難関私立大学にとりわけ強い中高一貫校のレバレッジ度ランキングを掲載する。

#3
偏差値は低くて入りやすいのに、大学受験に強い、レバレッジの利く中高一貫校はどこか?そんな“掘り出し物”を見つけるべく、独自ランキングを作成した。ここでは、東大・京大をはじめとする難関国立大学にとりわけ強い中高一貫校のレバレッジ度ランキングを掲載する。
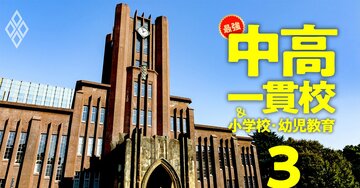
【中学受験への道】第99回
元学長が付属中高校長に!新校長人事で見る首都圏「中高一貫校」の将来
新型コロナの感染再拡大が懸念される中、新年度が始まった。1年前の今頃は各校とも休校期間中の学びの確保に四苦八苦していたが、今では対面授業とのハイブリッド化で学校の特徴が示せるまでに進化を遂げている。年度初めは人事の季節でもある。この新しい時代のかじ取りを託された新校長を順次ご紹介していこう。

#2
偏差値では入りやすいのに、大学受験に強い、レバレッジが利く中高一貫校はどこか?そんな“掘り出し物”を見つけるべく、独自ランキングを作成した。ここでは首都圏175校の総合ランキングを掲載する。

日本の「AI自動翻訳」劇的進化の実態、特許や製薬・金融など専門分野に変革も
国産のAI翻訳が、特許、製薬、金融などの専門分野で、すさまじい進歩を遂げている。なぜ精度が急速に上がったのか。どのような産業でどのように役立てられているのか。国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)フェロー隅田英一郎氏に聞いた。

資格なんて取得しても仕事では大して役立たない。高額な講習や受験料をせしめる資格試験は新手の詐欺商法だ。このようにやり玉に挙げられることも多い中、その男がこれまで取得した資格の数は760以上。まさに“資格依存症”だ。一体何が彼をそこまで駆り立てるのか。

ダイヤモンド・プレミアム(有料会員)ならダイヤモンド社のベストセラーが電子ブックでお読みになれます!月ごとに厳選して提供されるダイヤモンド社の話題の書籍から、ここでは一部を抜粋して無料記事としてお届けします。全体をお読みになりたい方はぜひダイヤモンド・プレミアム(有料会員)にご登録ください!今回は2021年4月提供開始の『この1冊で一気におさらい!小中学校9年分の算数・数学がわかる』。小・中学生から専門学校生、大学生、大人まで、数学と算数の基本をサクッと復習したい人にぴったりの本です。

今回は、51歳・会社員男性Eさんからのご相談です。年収1200万円で住宅ローンの支払いが85歳まである上に、月々の家計が赤字とのこと。月に最低限いくらためれば2人の子どもを大学院まで進学させた上で、老後生活も苦労しないで済むか?というご相談です。

第12回
都立「日比谷高校」はなぜここまで復活できたのか
都立の名門である日比谷高校校長に在任9年。2021年入試でも東京大学合格実績は全国の公立高校トップで、さらに合格者数を積み増した。なぜ躍進を続けているのか。そこには武内彰校長の粘り強い校内マネジメント改革への取り組みがあった。高校の3年間で私立中校一貫校に匹敵する教育力を発揮している理由に、森上展安・森上教育研究所代表が迫る。

第4回
コロナ禍で情報収集がカギに! 2021年度から様変わりした大学入試を国公立別におさらい!
2021年度から大学入試は大きく様変わりした。前回紹介した大学入学共通テストにつづいて、コロナ禍の影響もふまえた、国公立と私立、また総合型選抜と学校推薦型選抜ごとの入試方式の特徴について確認しておこう。

新型コロナウイルスの流行は、これまでの日常を変えた。教育も、新型コロナウイルスの影響を大きく受けたものの一つだ。一度目の緊急事態宣言下においては、学校は休校になり、子どもたちは塾にも通えなくなってしまった。その後も、学校は休校にならなくても、さまざまな制限があることに変わりはない。そんな中、自ら学ぶ「自宅学習」に注目が集まるのは自然なことだろう。

第10回
「トゥキュディデスの罠」
「お金持ちになるにはどうしたらいいのか」という疑問にこの連載ではいろんな角度から答えを示していきます。お金持ちなら誰でも知っている秘密を明かしていきます。その疑問の答えにたどり着くには「お金」「経済」「投資」「複利」、そして「価値」について知っておく必要があります。少し難しい話も出てきますが、今は完全にわからなくても大丈夫です。資本主義の仕組みについても、詳しく解説していきます。なぜなら、資本主義の世界では、資本主義をよく知っている人が勝つに決まっているからです。今後の答えのない時代において、どのように考えながら生きていけばいいのか、ということもお話ししていきたいと思います。さあ、始めましょう!

第48回
行動経済学でみる投資家心理
◎大好評! シリーズ10万部突破!!ふつうの会社員でも10年あれば、気づいたときには1億円!小型株は伸びしろが大きいわりに、目を付けている投資家が少ない。それだけに、株価が何倍にも伸びる可能性をふんだんに秘めている。大学時代に投資を始めた著者は、6~7年後に資産1億円を達成。いまでは1銘柄だけでも億単位のリターンを得ている。10万円から株式投資をスタートしたとしても、収入から生活費を除いた分を追加して投資額を増やしていけば、1年で資産100万~200万円は十分狙える。資産100万円になれば銘柄の選択肢が広がり、資産を急角度で増やせる可能性がアップ。資産1000万円くらいで壁にぶつかりがちだが、この壁を突破すれば10万円を100万円、100万円を1000万円に増やした感覚で“億り人”へ!ベストセラー『10万円から始める! 小型株集中投資で1億円』の刊行から1年。今度は『10万円から始める! 小型株集中投資で1億円 実践バイブル』として、小型株集中投資のテクニックを全公開!

第3回
大学入学共通テスト後の入試とは!? 来年の受験に向けておさらいしておこう
2021年度から大学入試は大きく様変わりした。共通テストやコロナ禍の影響もふまえて、フクザツな入試方式について理解しておこう。
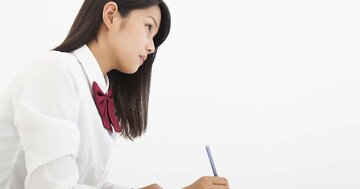
輸出大国・中国は建国から100年を迎えたとき、何を輸出するのでしょうか。それは「形あるもの」というハードではなく、「ノウハウ」というソフトに置き換えられている可能性が高いでしょう。いわば、“中国の成功体験の輸出”です。
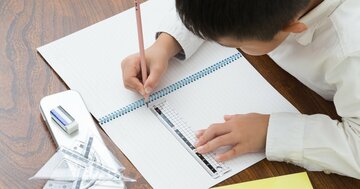
職場や人前で自分をうまく表現することができない。成長したいと強く願いながらも、今ひとつ突き抜けた成果を出せない。そんなモヤモヤを抱えていませんか?その原因はあなたの能力が低いからではなく、自分を表現できていないだけかもしれません。Zアカデミアで次世代リーダーの育成を行い、2021年4月開校の武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の学部長に就任するほか、多くの大手企業やスタートアップ育成プログラムでメンター、アドバイザーを務める伊藤羊一さんも、かつてはそうだったといいます。『ブレイクセルフ 自分を変える思考法』(世界文化社刊)では、伊藤さんが自身の失敗談を交えながら「自分自身を突破=ブレイクセルフ」した方法を説きます。
