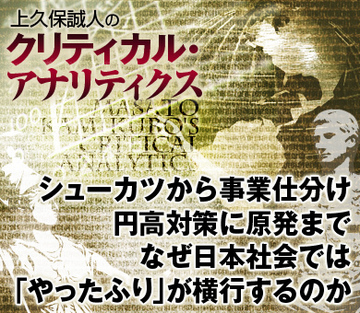上久保誠人
第55回
日米首脳会談で、日本は安倍首相のタフな交渉によって、TPP交渉には「聖域」があるという言質を、バラク・オバマ米大統領から勝ち取った。だが、首相が誇るほど「大きな成果」だったわけではない。元々首脳会談前から、TPPに関して日本は優位な立場にあったからだ。
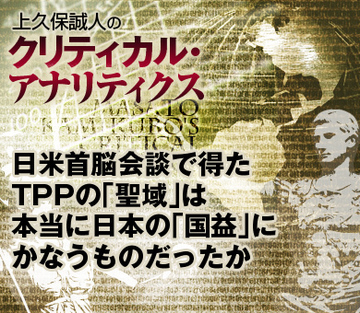
第54回
G20で、日本は「円安誘導」との名指しの批判を回避することができた。事実上、金融緩和の強化は容認されたのである。麻生太郎副総理・財務相は、G20終了後の記者会見で「一番の成果は、通貨戦争とあおられるのを完全に抑えられたことだ」と、安堵の表情を浮かべた。
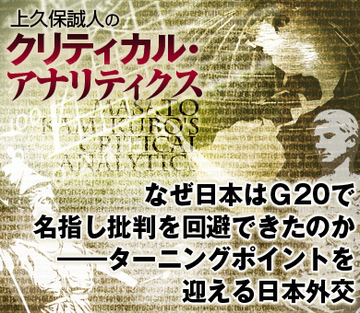
第53回
安倍内閣の支持率が上昇している。世論調査によっては70%を超えるものも出てきたようだ。一方、参院選の惨敗後、民主党はすっかり影が薄くなってしまった。民主党は安倍内閣とどう対峙し、どう行動すべきだろうか。
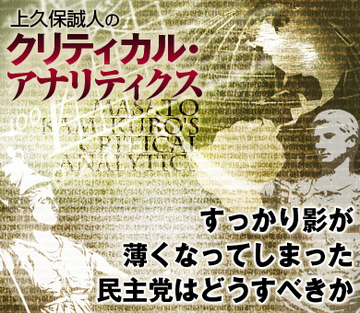
第52回
アベノミクスとは、現在のところ、指導力も政治力も発揮されていない、政策全体へ配慮する知恵もないものだ。安倍首相が、本当に日本経済再生につながる経済政策を実行するなら、それは高度な政治力・交渉力・リーダーシップを発揮し、既得権者の抵抗を乗り越えてこそ実現できるものではないだろうか。
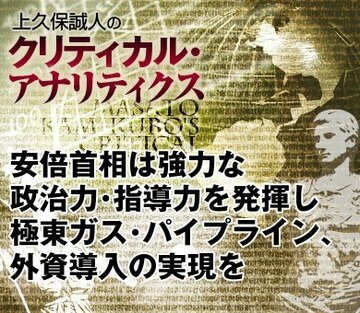
第51回
安倍晋三内閣が「緊急経済対策」を決定し、「3本の矢」で成り立つ「アベノミクス」がいよいよ動き出した。今回は、安倍内閣・党役員人事の分析を通じて、「アベノミクス」による日本経済再生の実現の可能性を論じたい。
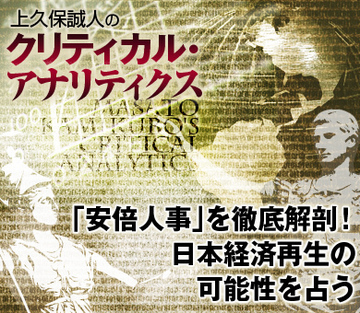
第50回
衆議院総選挙で、自民党と公明党で325議席を獲得した。参院で否決された法案を衆院で再可決できる、3分の2以上の議席数を確保する、圧倒的な大勝利だ。しかし、今回の総選挙は2005年・2009年と異なり、自民党に「風」が吹いたわけではなかった。
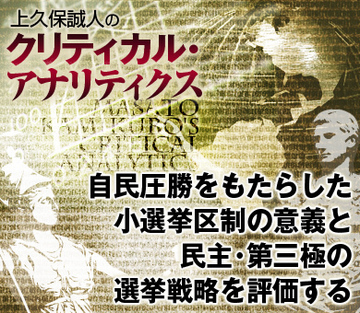
第49回
今、隣国との「領土問題」が重要な政治課題となり、衆院選で「国防軍」「集団的安全保障」など安全保障が争点となっている。そこで、筆者も安全保障問題を取り上げるが、それは軍事力を中心とする「伝統的安全保障」ではなく、「非伝統的安全保障」である。

第48回
野田首相の衆院解散決断については、「政局」の観点からさまざまな議論が展開されている。だが、この連載は「政局論」と一線を画したい。「政局論」では、野田首相が解散に追い込まれたと主張するものが多い。だが「政策」に焦点を当てると、全く別の見方が可能になる。
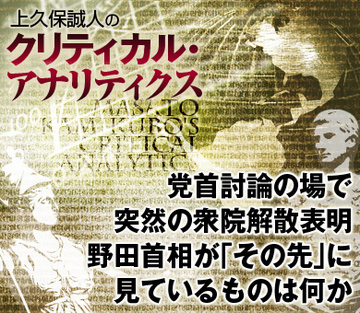
第47回
野田首相は「一票の格差是正」「特例公債法の成立」「社会保障改革国民会議メンバーの人選」の3つの条件を提示し、解散時期の明示を拒否。野党の追求にも動じる様子を見せない。次第に安倍総裁は、世論の批判が自民党に向かうことを恐れ始めた。
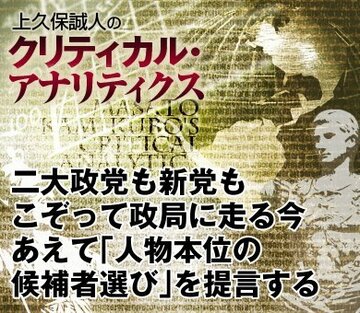
第46回
前・安倍政権の外交を「自由と繁栄の弧」+「戦略的互恵関係」とみれば、それが米国の戦略のベースである「地政学」に基づく包括的な国際戦略であるということがわかる。安倍総裁はこの戦略を再評価すべきだろう。
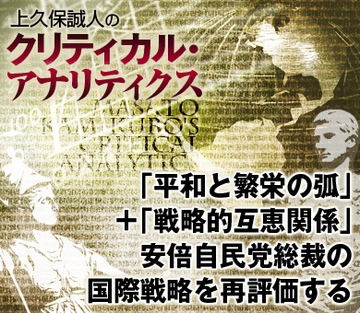
第45回
安倍氏の新総裁就任に際して、1つ気になることがある。それは、安倍氏が5年前の首相辞任について「当時は病気で政権を離れるしかなかったが、2年前に新薬が開発されすっかり良くなりました」と説明していることだ。
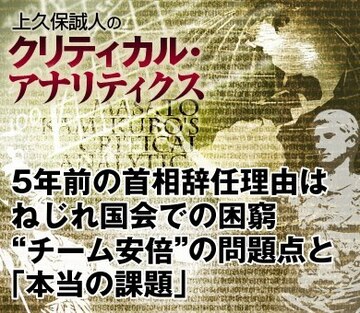
第44回
今日、自民党総裁選が投開票される。谷垣総裁は「過去の人」となってしまったようだ。だが同氏は、政治的な意思決定としては稀有な成功例であり、国際的にも高く評価されている消費増税実現の立役者の1人でもある。「政治家・谷垣禎一」の再評価を試みたい。

第43回
英国といえば、製造業が衰退し、金融・法律、会計、コンサルタントなどの高度サービス中心に移行した国とされる。だが、エコノミスト誌の記事によれば、英国の製造業は拡大しているという。
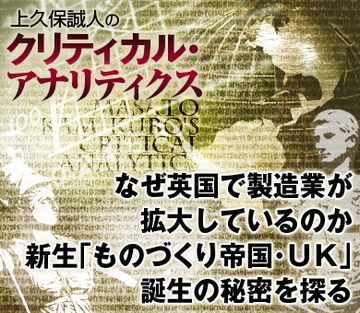
第42回
選挙制度改革は、2009年衆院選における「一票の格差」を最高裁が「違憲状態」と指摘したことでスタートした。だが、新たな区割り案勧告期限が過ぎても、制度改革が進まなかったのは、中小政党が抜本的制度改革を主張して譲らなかったからだ。
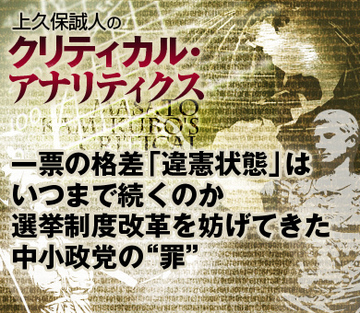
第41回
金曜の夜、「原発再稼働反対デモ」が霞が関一帯を埋めている。これまで市民運動と関わりが薄かった一般国民の反原発運動への参加が増え、市民運動を超えてより広範囲に原発不信が広がり、それが原発推進を「政治的」に困難にしている。

第40回
小沢一郎氏ら49人が新党「国民の生活が第一」を結党した。自民党、公明党は解散総選挙を求めて圧力を強めており、野田佳彦内閣の政権運営は厳しさを増しているようにみえる。だが、野田首相は三党合意で国会での圧倒的な多数派形成に成功しているのだ。
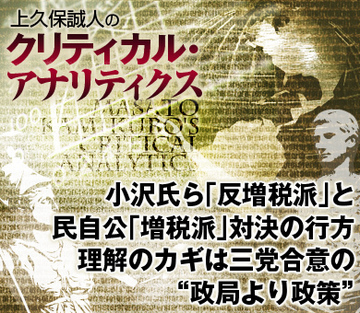
第39回
今回は「政治家・小沢一郎論」を展開する。たとえ、離党劇が小さな話にすぎなくても、「小沢一郎」が、約25年に渡って日本政治の中心であったことは言うまでもない。その功罪は、過小評価すべきではないと考える。
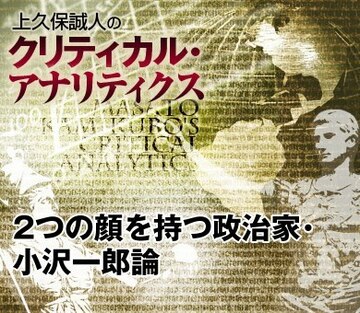
第38回
民自公3党の実務者協議が、政府提出の「消費増税法案」と自民党の「社会保障制度改革基本法案」の修正で合意に達し、消費税率引き上げが決定した。なぜ与野党間で消費増税のコンセンサスを形成することができたのだろうか。
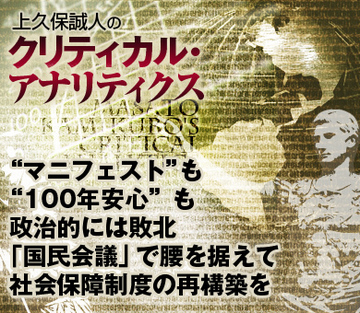
第37回
与野党間で奇妙なまでに消費増税賛成のコンセンサスが出来上がっている状況を、「財務省の陰謀」だとする類の批判が巷に氾濫している。政策通として知られる、みんなの党・江田憲司幹事長氏までもが、著書で「財務省のマインドコントロール」だと論じているのだ。
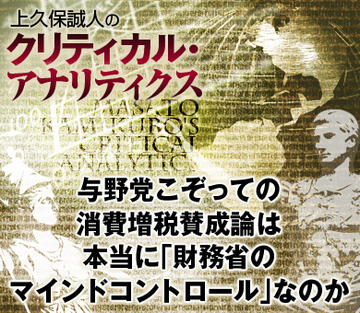
第36回
大学で1~3回生を見ていると不思議でならない。彼らはいずれ直面するシューカツの大変さを知っているはずだ。だが、早めに危機感を持って必死で勉強したり、語学や技術を磨く学生は少ない。大多数は、ほどほどにサークル活動を楽しみ、バイトし、楽勝科目を選んで出席している。