早川幸子
第28回
友人に勧められて、昨年9月に出版された「アンアンのセックスできれいになれた?」(朝日新聞出版)を遅ればせながら読んでみた。「今の若い女の子の考えは、これほどまでに社会に抑圧されているのか」と少々ビックリしてしまった。

第27回
消費税増税法案が注目を集めているが、「社会保障・税の一体改革」では、医療の財源についてもいくつかの見直し案が出されており、中には国民の健康格差を拡大する恐れのあるものも含まれる。そのひとつが70~74歳の前期高齢者の窓口負担の引き上げだ。
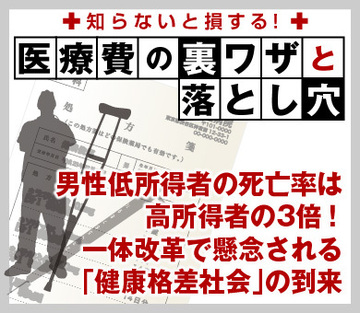
第26回
〈健保組合、保険料率上げ 高齢者医療負担重く〉4月11日、日経の朝刊1面にこんな見出しが飾った。大企業の従業員が加入する健康保険では、高齢者医療への支援金を支払うために健康保険料を引き上げる組合が増えており、その負担によって企業収益や家計が圧迫されるというのが記事の内容だ。
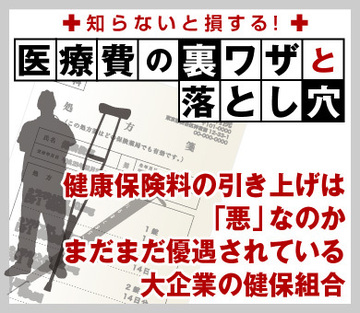
第25回
薬の処方にかかる技術料は、受診した場所により2つの報酬体系がある。ジェネリック医薬品を使って薬代を抑えても、実際の医療費が先発医薬品を使っている人とほとんど差が出ないというケースもあるのだ。詳しく検証してみよう。

第24回
長期療養や大きな病気をして医療費が高額になった場合の窓口負担を抑えられるものがある。それが「限度額適用認定証」だ。2007年4月に導入され入院費に限って適用されてきたが、この4月からは通院治療でも使用が認められることになった。
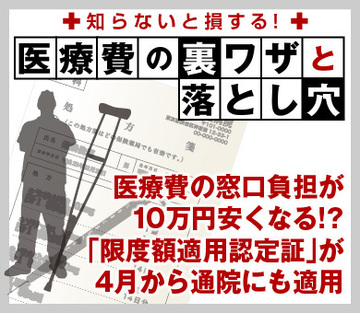
第23回
病気やケガで入院したときに備えて医療保険に入っている人は多い。中でもここ数年「終身型」の医療保険の人気が高い。しかし来年度の医療費の改定内容を見ると、こうした医療保険に入っていても、給付金を受け取る機会はどんどん減っていくのではないかと感じている。
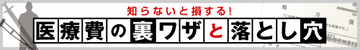
第22回
病気やケガをした原因によっては健康保険が使えないこともある。仕事が原因による病気や通勤途中に負ったケガなどの治療をする場合で、健康保険ではなく労災保険(労働者災害補償制度)から補償を受けることになっている。その申請のポイントを見てみよう。

第21回
健康保険には、病院や診療所で自己負担したお金が一定額を超えると払い戻しを受けられる「高額療養費」があるが、これとは別に医療費がたくさんかかった人には税金面でも優遇がある。それが確定申告の「医療費控除」で、間もなく受け付けが開始される。
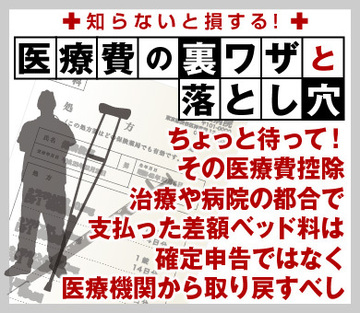
44歳で住宅ローンを組むのと、60歳でキャッシュで購入するのはどっちがトクか?
賃貸の場合、いつまでも家賃を払い続けなければならず、高齢になると更新できないという不安もある。持ち家は家賃の心配はないが災害時のリスクや介護状態になれば住むのが難しくなることもある。損得だけでは計れない老後の住まいを考える。
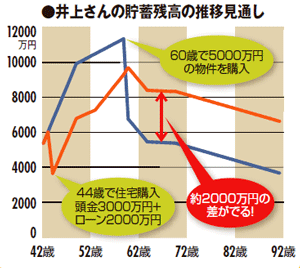
第20回
20XX年4月。進行性の胃がんが見つかったAさんは、治療方針について話す担当医の言葉に愕然とした。「進行しているので、早急に切除したほうがいいでしょう。医学的には抗がん剤による化学治療も勧めたいのですが、健康保険が高価な抗がん剤の使用を認めてくれるかどうか……」
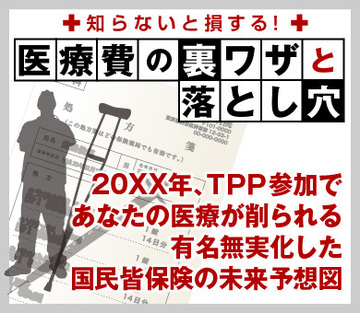
第19回
ある晩、胃痙攣を起こした同僚の2人。Aさんは翌日の午前中にかかりつけクリニックを受診。一方Bさんは我慢して働き、深夜になってから大学病院を受診した。ところが診療内容はなのに、2人の自己負担額はBさんのほうが6690円も高かったのだ。さて、このカラクリとは?
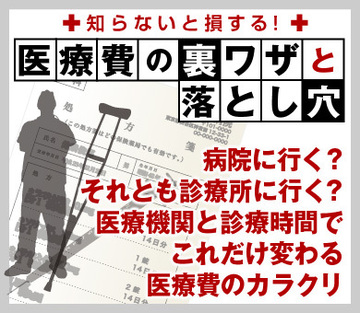
第18回
会社員の健康保険は、保険料の追加負担なしで親を扶養に入れられることを前回の本コラムで紹介したが、親を扶養することで得られるメリットは保険料の節約だけではない。医療費が高額になった場合、「世帯合算」することで負担を軽減できる可能性があるのだ。
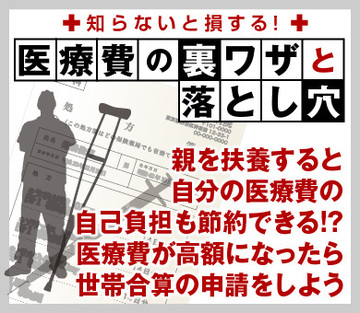
第17回
会社員の健康保険は、扶養家族の人数によって直接的に保険料が変わることはない。扶養家族にできるのは配偶者や子どもだけではなく、一定の要件などを満たせば、離れて暮らす父や母も扶養に入れることができ、結果的に親の保険料の負担を抑えることが可能になる。

第16回
会社員の場合、健康保険料は天引きされ会社がまとめて支払っているので、自分の負担額を知らない人も多いだろう。ましてや、それがどのように決まるのか、他の人と比べて高いのか安いのかといったこともわからないはずだ。そこで、今回は会社員の健康保険料の仕組みを紹介する。

がんの治療を受けている人は全国で152万人と言われている。医療制度改革によって通院での治療も増える中、がん保険の見直しは必要なのだろうか。

第15回
病気やケガをしたときの心配事として、「収入が途絶えてしまうのではないか」という生活費の不安をあげる人が多い。しかし、会社員は健康保険法や労働基準法などさまざまな制度によって、生活が守られていることをご存知だろうか。
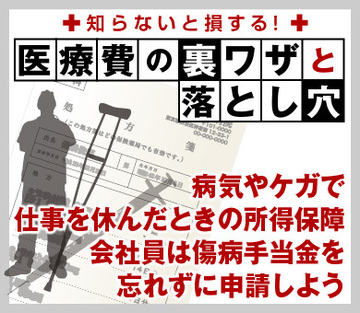
第14回
腰痛、肩こり、手足の関節の痛みなどに悩む人は、年齢を重ねるごとに多くなる。しかし、はり・きゅう、マッサージ、整骨院・接骨院で受ける施術が、すべて健康保険の対象になるわけではない。そこで今回は、こうした施設では、どのようなときに健康保険が使えるのかを見ていきたい。

第13回
病院や調剤薬局に行ったとき、「おくすり手帳を持っていますか?」と聞かれたことはないだろうか。今回の震災ではおくすり手帳を持っていたおかげで、避難所などでもこれまで飲んでいた薬の情報を伝えられた被災者もいて、その存在が改めて見直されている。

第12回
健康保険には、患者が支払う自己負担額に上限を設けて、医療費が高額になっても極端に個人の負担が増えないように配慮した高額療養費という制度がある。今回は高額療養費の裏ワザとして、知っておきたい「世帯合算」について紹介する。

第11回
自転車で転倒し、救急車で大学病院に運ばれたAさん。健康保険証を提出したところ、事務職員にビックリすることを言われた。「交通事故は健康保険が使えませんよ」…。
