新井美江子
#6
半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスが、自動車事業よりも利益率の高い非自動車事業を強化するべく、巨額買収を進めている。「自動車離反」ともささやかれる動きに、ルネサスの自動車事業担当のキーマンはどう答えたのか。自動車メーカー向けのビジネスはどのように収益性を上げていくつもりなのか。自動車メーカーとの関係性や将来戦略についてトコトン本音を語ってもらった。

#4
どの自動車メーカーよりも速くコロナショックから“復活”し、ケイレツのサプライヤーをホッとさせたトヨタ自動車。しかし、足元でトヨタはグループ内再編という大改革を行おうとしているようだ。「何を、どこまでやるのか」。選択と集中を断行しなければ、日本の自動車業界は「内燃機関ガラパゴス」と化してしまいそうな状況にある。

#1
従来、半導体大手のルネサスエレクトロニクスは、トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーの“従順なしもべ”だった。だが、その主従関係に変化の兆しが見え始めている。スマートフォンやデータセンター向けなどの旺盛な半導体需要を背景に、自動車メーカーが半導体の調達に苦しむ“買い負け”が生じているのだ。ちょうど同じタイミングで、ルネサスは非自動車事業を拡充する巨額買収を敢行している。半導体メーカーと自動車メーカーの間で繰り広げられる神経戦を追う。

橋本英二・日本製鉄社長は東日本製鉄所鹿島地区(旧鹿島製鉄所、茨城県)の高炉1基の恒久休止を決断した。だが、構造改革の対象は生産設備の再編成にとどまらない。橋本社長が狙う構造改革の「二の矢」の中身とは何か。

番外編
石炭火力、原子力、洋上風力、バーチャルパワープラント(VPP)……電力会社による巨額の設備投資と、それにひも付く長期の設備メンテナンスを長く請け負ってきた重電メーカーの電力部門は、グリーンバブルでどう変わるのか。米ゼネラル・エレクトリックと洋上風力での提携観測も出る東芝で、長く電力関連ビジネスを率いてきた畠澤守代表執行役専務(東芝エネルギーシステムズ社長)に、乱気流にのみ込まれる電力業界での勝ち残り策について聞いた。

#12
半導体不足で自動車メーカー各社が減産に追い込まれたことで、あらゆる業界が半導体の重要性と、その調達リスクにあらためて向き合うことになっている。半導体業界は売り手市場に傾きつつあるが、そんな半導体の恩恵を日本が受けるための「頼みの綱」となっているのが、パワー半導体だ。三菱電機や東芝はこぞって積極的な投資計画を出すが、その前には米インフィニオンが立ちはだかっている。

#9
鉄鋼業界が最大のピンチを迎えている。需要減や原料高を背景に高炉再編を進めてきたところだったが、今回の脱炭素シフトで、その再編計画は練り直しが必要になりそうだ。今のカーボンニュートラルの潮流は、鉄鋼産業に巨額の投資を強いるばかりか、「日本」という国で製造業を続けるリスクを浮き彫りにしている。

#5
日本の製造業で最も多く二酸化炭素を排出している鉄鋼業界への風当たりはすさまじい。国内3位の神戸製鋼は、日本製鉄とJFEホールディングスのどちらの傘下に入るのか。実は昨年、日本製鉄の中枢では密かに再編案が検討されていたのだが、脱炭素旋風の直撃によってその計画は“幻”と化してしまうかもしれない。鉄鋼メーカー3社の行く末を追う。

#4
日本の3メガバンクグループが環境関連融資に30兆円を投下するという。実際に、グリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローンなど企業の資金調達を目的としたエコ金融商品の展開に積極的だ。だが、最も重要なのは脱炭素への「移行資金」だ。既存事業の膿を出しながらエコシフトを遂げるには、環境分野への新規投資以上に巨額資金が必要となる。30兆円融資どころでは全く足りない資金需要の実態に迫る。

#2
主要国政府による環境補助金の積み上げと、金余りを背景とした巨額マネーのSDGs(持続可能な開発目標)・ESG(環境・社会・企業統治)投資への流入で、資本市場はさながら「グリーンバブル」の様相を呈している。過熱する環境バブルでは、地道に、実直にビジネスを展開しているだけでは成長への切符をつかみ取れない。ブームに翻弄される企業につけ込むファンド・コンサルティング会社が暗躍している。

米中貿易摩擦で業績が落ち込んだところに新型コロナウイルスの感染が拡大し、またもや顧客の設備投資意欲がそがれるのではないかと懸念されたFA(ファクトリーオートメーション)業界。しかし、リーマンショック時の打撃に比べればはるかに影響は軽微ですみそうだ。その理由を、サーボモータやインバータ、ロボットなどに強みを持つ安川電機社長に聞いた。

#8
地方銀行の首脳だけが参加できる地銀頭取三田会は、2014年の初会合の直前、頭取の慶應人脈が突破口となった再編事案が明るみに出たことで、業界の注目組織に躍り出た。ところが、大物が相次ぎ退任。頭取三田会に続いてできた会長三田会でも「大親分」が“失脚”するなど、地銀トップの三田会にかつての輝きはない。むしろ早稲田OBたちの勢力が拡大中だ。

#2
慶應出身者といえば、「余裕と気品」「お金持ち」といったキーワードが浮かぶが実際のところはどうなのか。40万人近い慶應義塾卒業生のデータから経済力が如実に表れる居住地を分析すると、そのゴージャスぶりが浮き彫りになる。また、密な人間関係や意外な“琴線”から、慶應関係者の“生態”を明らかにする。

#49
国内化学最大手の三菱ケミカルホールディングスは2020年、越智仁社長の後継にベルギー出身のジョンマーク・ギルソン氏を招聘すると発表し、産業界を驚かせた。驚愕人事の思惑を、指名委員を務める小林喜光会長に聞いた。

#43
新型コロナウイルスの感染拡大によって旅客需要が蒸発し、航空機関連事業という下支えを失った三菱重工業、川崎重工業、IHI。これら「3重工」は、創業100年を優に超えた今にして、何によって稼ぐべき会社なのか、自問自答する事態に陥っている。

#42
タイヤ業界には、すり減ったタイヤを交換する市販用タイヤという“鉄壁”の収益源がある。にもかかわらず、タイヤ業界は新型コロナウイルスの感染が拡大する前から苦境に立たされていた。業界再編も起こりそうな様相を呈するが、ブリヂストンは収益確保にどう動くのか。
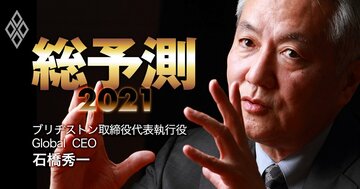
日立製作所による非中核事業の聖域なき整理の象徴である日立御三家・日立化成の売却は、日立に潤沢な成長資金をもたらしたといえる。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の真っただ中ということもあり、買収した側の昭和電工にとっては、巨額買収が波乱の幕開けになりかねない状況だ。

菅義偉首相が「2050年までに温室効果ガスの排出量、実質ゼロ」の目標を掲げたが、世界的な環境に対する関心の高まりによって、環境対応はもはや企業における競争力の根幹を成すようになっている。そんな流れの中で、資金調達ですら「環境配慮」が必須の時代に入っている。

第75回
新型コロナウイルスの感染が拡大してもしなくても、構造改革が待ったなしの状態となっていたのがガラス業界だ。成熟している上、寡占化していて業界再編にも限界がある“超難解”な市場に、最大手のAGCはどう向き合い、これまでどんな活路を見いだそうとしてきたのか。来年、会長職に退く島村琢哉氏に、社長在任の6年間について聞いた。

#13
三菱重工業は10月30日、国産初のジェット旅客機「三菱スペースジェット(旧MRJ)」の開発を事実上、凍結すると発表した。確かに航空機業界はコロナ禍で事業環境がすこぶる悪いが、凍結の理由はそれだけではない。その重大決断の背景には、三菱重工の深刻な“財務的ダメージ”がある。
