榎並利博
新型コロナ感染再拡大への警戒を怠ってはならないが、ワクチン接種の普及によってこれまでの日常が取り戻せる兆しも見えてきた。しかし、ただ時間を巻き戻すだけでなく、コロナ禍によって得た経験や課題を踏まえ、より良い方向へと社会を前進させていくことが重要だ。

新型コロナウイルス感染症の終息の兆しも見えず、社会的不安が広がり始める中、社会的な孤独・孤立が問題化しつつある。高齢者を対象とした国際比較調査では、日本の高齢者の31.3%が「親しい友人がいない」という。これは他国(米、独、スウェーデン)と比較して2倍から3倍の数字だ。特に日本の高齢者男性では40.4%が「親しい友人がいない」と回答し、女性(23.0%)よりも深刻だ。

自宅の空調設備の交換工事を行ったところ、業者から「契約は電子契約でお願いします」と言われた。これまでも見積書や請求書はメールで送られてきたが、昨年の洗面所工事の契約はまだ紙だった。この1年、コロナ禍で対面を避ける傾向が顕著だが、地元の業者に電子契約が普及するほど社会が変わってきたのかと感慨深く思う。

なかなか普及しないと批判されていたマイナンバーカードだが、ここへきて急激に交付率が伸びている。5月1日現在の交付率は30.0%と大台に達し、1年前と比較すると10ポイント以上の伸びだ。さらに、申請ベースでは3月末時点で全人口の約36%になり、赤ちゃんからお年寄りまで3人に1人がマイナンバーカードを保有することになる。

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が最近ビジネス界に浸透している。本来は「デジタルの進展で社会全体が良い方向へ変わる」という漠然とした意味だが、わが国ではより危機感を持った概念として捉えられている。デジタルの力がビジネスの在り方を根底から変えてしまうからだ。

いよいよ今年の3月からマイナンバーカードの健康保険証利用が始まる。個人を特定できるカードを使うことで高額療養費制度が少ない負担で利用でき、自分の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報も確認できるようになる。

87%とはかなり驚異的な数字である。これはマイナポイントについて「知っている」「聞いたことがある」と回答した数字だ。他の調査でも軒並み80%を超えており、認知度の高さは本物のようだ。

今回のコロナ禍で「新しい日常」への速やかな移行が要請される中、オンライン会議や在宅テレワークも「普通のもの」になりつつある。新型コロナ対策や東京オリンピック・パラリンピック、変化する国際情勢への対応など、難しい国政のかじ取りも「新しい日常」の中で迅速に進めてほしいものだ。

徐々に日常が復旧しつつあるとはいえ、新型コロナウイルスがパンデミックを引き起こし、諸外国でロックダウン(都市封鎖)が実施されたことは記憶に新しい。このとき日本ではなぜロックダウンしないのか、なぜできないのかという重要な問題提起がなされた。

新型コロナウイルスの猛威により、わが国の社会はいや応なしに行動や文化の変化を迫られている。4月半ばに全国に緊急事態宣言が発令され、「三つの密」を避けるために通勤や通学の自粛が要請されたことで、働き方や学び方にも影響が及んだ。

「いきいき〇〇〇」。高齢者が老後を「いきいき」と過ごせるよう、このような名称を付けた施設があちこちにある。高齢社会にあってこのようなサービスは大切だが、この30年に及ぶ閉塞感漂う社会を打破するため、若者には高齢者以上に「いきいき」と世の中に変革をもたらしてもらいたい。

「IT後進国・日本」、経営者はデジタル視点で本業の再定義を
昭和末期、日本の半導体産業が米国を席巻し、ジャパン・アズ・ナンバーワンという言葉さえ流行した。当時、日本は世界に先駆けてオンラインシステムを構築し、通信のデジタル化でも先頭を走り、米国にとって大きな脅威と捉えられていた。

超高齢化の日本、次に来るのは「多死社会」。支える仕組みの構築を
今年の敬老の日に合わせた総務省統計局の発表によると、日本の高齢者(65歳以上)の人口が3588万人と過去最多になった。そのうち100歳以上が実に7万人を超え、いまや100歳超のご長寿も珍しくない。総人口に占める高齢者の割合も日本は28.4%と世界で最も高く、2番目のイタリアを5ポイント以上引き離している。

数十年で激変した「世帯構成」、政府が示すサンプルはすでに「標準」ではない
昭和49(1974)年には、このような世帯が14.6%と最も多く、まさに「標準世帯」であった。しかし、その後世帯構成は変化し、現在最も多いのが1人世帯・無業(17.0%)であり、次いで1人世帯・有業(15.7%)、2人世帯・無業(13.7%)と高齢者や単身者の多さが窺われる。また、4人世帯・有業者2人の世帯が6.8%と、専業主婦(主夫)よりも共働き世帯の方が多いようだ。
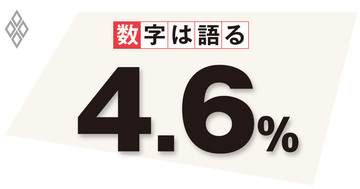
国がテレワーク推進へ東京五輪の混雑緩和と働き方改革の推進に期待
東京五輪・パラリンピックでは、国内外から多くの観戦者や観光客が東京を訪れる。他方、都心部は建設ラッシュが続いており、2020年までに丸の内・大手町のオフィスの7割ほどのスペースが新たに供給され、東京都心部の交通混雑が懸念されている。
