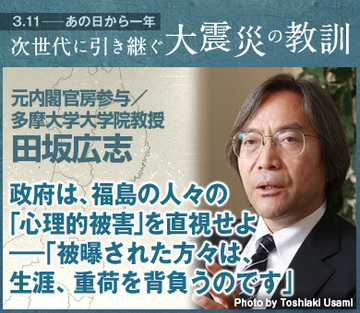翌日、森嶋は部屋に一歩入って足を止めた。
部屋中の視線が集まっている。昨日と同じだ。つまり、誰も抜けなかったということだ。千葉までもが、昨日と同じ席に座っている。
森嶋は優美子の隣に座った。
「昨日、電話がなかったな。自分で残ることに決めたのか」
「電話を期待してたのね。お生憎様。今まで自分の人生は自分で決めてきたわ。でも、誰も抜けなかったというのは驚きね」
「賭けてみようって気になったのかな」
「何に賭けるのよ」
「自分たちが歴史を作れるか。次官になるより遥かに面白そうだろ」
「秤にかけただけよ。元の場所に戻ったときと、もし現実になったときの自分の役割を」
「ジョン・ハンターを知ってるか」
森嶋は優美子に聞いた。
「ユニバーサルファンドのCEOでしょ。リーマンショックとギリシャで大儲けした」
「日本でホテルを借りているそうだ。かなりの数の部屋を」
優美子の顔色が変わった。
「ロバートからの情報?」
「野田理沙さんからだ。昨夜、電話があった」
会ったことは言わなかった。
優美子と理沙は仲がいいように見えて、どこかよそよそしいところがある。根底にライバル意識があるのだろう。
「だったら、確かな情報でしょうね。でも、なぜあなたに」
「財務省では、そういう情報はないのか」
「外務省からでも入ってくればいいんだけど、日本の省庁の情報なんて週刊誌頼りよ。大使や公使は政治家の接待役にすぎないし」
政治家も海外の日本大使館など、海外旅行のときの世話役程度にしか考えていない。島国根性が抜け切らないというか、江戸以来の鎖国精神が続いているというか、外国の脅威などという言葉は明治に置き忘れてきたのだ。
「いよいよヘッジファンドが日本を食い物にしようとしているのか」
「東京のホテルに前線基地を置くつもりなら、そうなんでしょうね」
「政府は何か策を講じないのか。財務省に動きはないのか」
「どうするって言うのよ。ホテルを借り上げているだけで」
「日本経済の危機かも知れないんだ。それを阻止するのも財務省の役割なんだろ」
優美子は考え込んでいる。