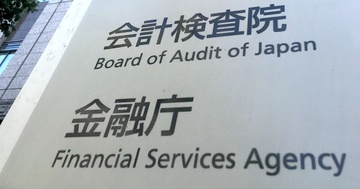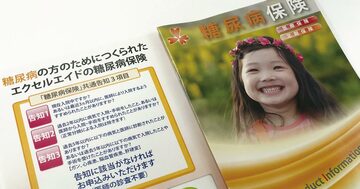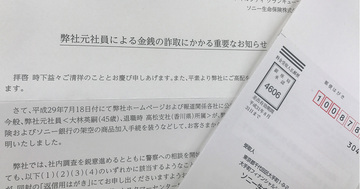「週刊ダイヤモンド」6月15日号「保険」特集のインタビューで述べた通り、この10年を振り返ると、保険の流通チャネル、とりわけ乗り合い代理店を取り巻く環境は激変したといえる。
 TSLABO(体制整備研究所)の長坂誠司代表取締役
TSLABO(体制整備研究所)の長坂誠司代表取締役
民間においては消費者の支持を得た来店型保険ショップの台頭が著しく、営業職員に代表される訪問型を主とした保険販売に大きな変革をもたらした。片や生命保険会社においても日本郵政とアフラック生命保険が資本提携したのに加え、大手生保が代理店チャネル向けの生保子会社を相次いで設立した。まさしく変革の中心にあったのは、保険の流通チャネルといっても過言ではない。
何より特筆すべきは、生保最大手である日本生命保険の動向だろう。訪問販売系代理店や保険ショップを複数社買収したのみならず、募集関連行為従事者であるライフルフィンテック(現LHL)を傘下に収め、中間持ち株会社に据えた。さらには、代理店チャネルへの商品供給を主とする生保子会社、はなさく生命保険を立ち上げて、代理店チャネルの一つの完成形をつくり上げたといえる。
むろん、この間、金融行政をつかさどる金融庁や財務局も大きく変容を遂げた。
直近で言えば、今年2月半ばの“バレンタインショック”と呼ばれる、中小企業経営者向けの節税保険に対する国税庁と金融庁の対応が挙げられる。国税庁が4月に行ったパブリックコメント並びに6月に出した新たな通達に加え、金融庁による募集管理体制の監視が強化され、すなわちプラチナ型といわれた節税保険に対する販売話法は完全に禁止された。いまだ販売再開に慎重な姿勢を保つ生保が多いが、金融庁は違反行為を行う生保が現れないかどうかに監督の目を光らせている。