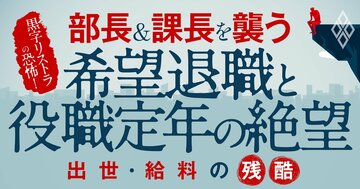日立が「ジョブ型雇用」を
8年前に導入した理由
7大新メガトレンドの中で、多くの人にとってなじみのないのが六つ目の「ジョブ型雇用」だろう。そこで、2012年から段階的にジョブ型雇用の導入を進めてきた日立製作所を例にジョブ型を解説していこう。
多くの企業が採用している「メンバーシップ型雇用」では「適材適所」が基本で、ジョブ型は「適所適材」が基本となる。
どちらも似たようなものだと思うかもしれないが、背景にある考え方を理解すれば、全く違うことが分かってくる。
メンバーシップ型は起点となるのが従業員(人)だ。会社は人に仕事を割り振る考え方をする。そこには終身雇用という前提があり、ゼネラリストを育成するという大方針がある。社内で年に1度行われるジョブローテーションは、メンバーシップ型の雇用政策の代表的な慣習といえるだろう。
一方で、ジョブ型は起点となるのはあくまで仕事。会社はその仕事に最適なスキルと経験を持つ人材を任命する。その際、年齢や社歴は関係ない。もし社内に最適な人材が見つからなければ、外部からヘッドハントすることも厭わない。終身雇用や年功序列とは無縁の制度なのだ。
日立はこうした日本型雇用制度とは正反対ともいえる制度を全世界で運用している。しかし、同社は典型的な日本型レガシー企業だ。そんな同社が、なぜ真っ先にジョブ型へ移行する決断をしたのか。
きっかけは08年度、リーマンショックによって同社史上最大となる7873億円の最終赤字に転落したことだった。今まさにコロナ禍によって構造問題があぶり出された企業のように、日立も一気に今までの付けを払うことになった。
そこからの復活を目指す中で、日立はグローバル化を大きな柱とした。しかし、海外で事業を成功させるには、積極的に現地の人材を採用していかなくてはならない。そこで、雇用も海外のスタンダードであるジョブ型に転換する必要があったのだ。
日立では現在、全職種においてジョブディスクリプション(職務記述書)が整備されている。これはメンバーシップ型にはない、ジョブ型の特徴だ。
ジョブディスクリプションは基本的に誰でも見ることができ、その職種に就くために必要なスキルや経験が明記されている。メンバーシップ型にありがちな、仕事内容は職場の上司や先輩の仕事ぶりから何となく把握するという曖昧さは、ジョブ型にはない。
ジョブディスクリプションが明確になると、大きく三つの変化を誘発する。
一つ目の変化は、従業員が自身のキャリアを主体的に考えるようになること。メンバーシップ型では、会社都合のジョブローテーションによって、自身のキャリアが大きな影響を受ける。ゼネラリスト育成を主眼に置いた雇用慣習では、従業員は専門スキルを身に付けられないため、転職して飛躍しようにも難しい。
一方、ジョブ型では就きたい職種があればどのようなスキルや経験が必要なのかが分かるので、それに向かって努力すればいい。
二つ目の変化は、評価制度の運用がしやすくなることだ。多くの企業が、コロナ禍で急増した在宅勤務中の従業員の評価に苦慮している。職務内容やそれに対する評価基準が曖昧だったためだ。
しかし、ジョブディスクリプションがあれば、従業員に求めることが明確になっているため、オフィスでの仕事ぶりが見えなくても、上司は結果や成果物で部下を評価することができる。評価される従業員も納得がいくはずだ。
三つ目の変化が、海外人材の獲得がしやすくなることだ。ジョブ型が当たり前の海外では、職務内容が明確になっていなければ、人材マーケットでそもそも相手にされない。中畑英信・日立執行役専務兼CHRO(最高人事責任者)は「ポジションが明確なので海外の人材を外部から採用しやすくなった」と話す。
ジョブ型の導入が進むと、給与制度も大きく変わることになる。勤務年数や年齢などではなく、「仕事の内容」を基準に給与が変わるからだ。