競合のソニー・日立は過去最高益
創業103年の名門に訪れた危機
創業103年の名門電機、パナソニックの縮小均衡に歯止めがかからない。2021年3月期決算では、四半世紀ぶりに売上高は7兆円を割り込み、当期純利益は1651億円にとどまった。
「勝ち組」の競合メーカーには、大きく水をあけられている。21年3月期の当期純利益では、ソニーが1兆1718億円、日立製作所が5016億円となり、共に過去最高益を叩き出したのだ。
9年ぶりの社長交代は、組織の閉塞感を打ち破るカンフル剤となるのか。6月末、パナソニックの9代目社長として楠見雄規氏が登板する。
デビュー会見では「社内への配慮」ばかりが目立ったが、楠見氏に近いパナソニック幹部は「真の改革者となるかもしれない」との声も漏れる。社内では、頭脳明晰な合理主義者として知られ、テレビ・自動車事業の構造改革で実績を上げた人物だ。
冒頭の会見でも、プレゼンテーションの中身を注意深く聞くと、「いかに戦略が優れていても、それを実施する力(オペレーション力)がなければ戦略が絵に描いた餅でしかない」(楠見氏)などとも語っており、楠見氏には「改革の腹案」があるのだろう。
楠見氏は、早くも大ばくちに打って出ている。4月下旬、世界最大のサプライチェーンソフトウエア企業である米ブルーヨンダーの買収を、CEOとして決断したのだ。買収金額は実に約7700億円。10月に控えた組織改編に加えて、大型買収という“ショック療法”で巨大組織の変革に挑む。
だが、変革の実現には高い壁が立ちはだかっている。
というのも、事業こそグローバルに展開しているパナソニックだが、その企業風土は極めてドメスティックだからだ。
日本的経営(長期安定雇用や年功序列に代表される日本独自の経営システム)を煮詰めて凝縮させたような会社だと言ってもいい。
内向き志向の組織、事業部の縦割り、人事の硬直性――。津賀一宏社長をはじめとするパナソニックの歴代経営者も、こうした組織の変化対応力をそぐ「三つの呪縛」に苦悶し続けてきた。
今年7月、この「最凶」の呪縛を撲滅する第一弾として、パナソニックは大規模リストラに踏み切るのだ(パナソニック「割増退職金4000万円」の壮絶リストラ、年齢別加算金リスト判明【スクープ完全版】参照)。
バブル末期入社組を標的にした早期退職制度を発動するのだ。事業は人なり。創業者の松下幸之助が雇用の安定を説いたことからもわかるように、パナソニックでは、人員整理をタブー視してきた経緯がある。それでも敢えて、人材の“強制的な”新陳代謝に踏み切るところに、経営陣の危機感がにじみ出ている。
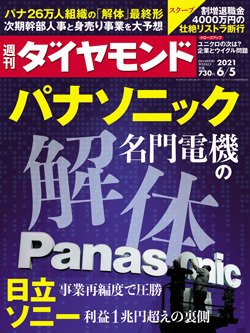
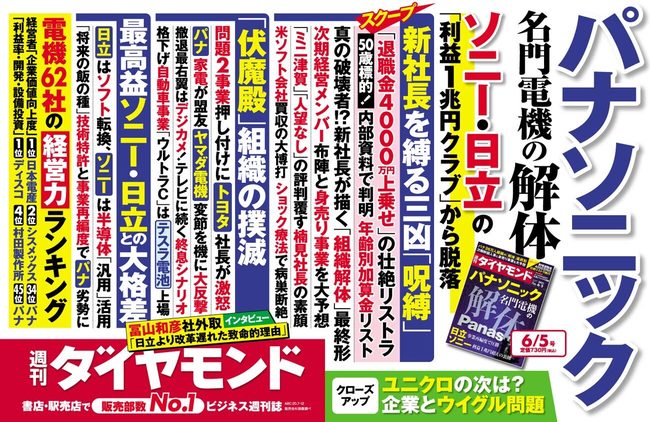
![パナソニック新社長が描く「組織解体」最終形、主要4社の社長人事と“身売り”事業を大予想[見逃し配信]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/360wm/img_a812d8d8f1c35e18d65a572d616b9e3e298908.jpg)






