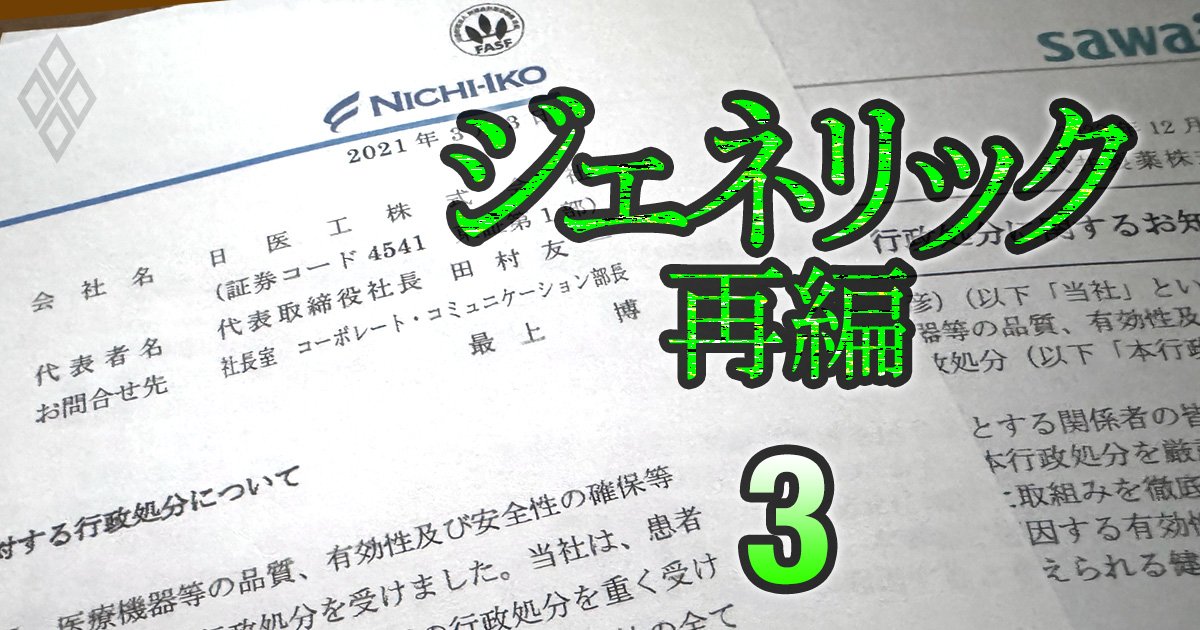裁判に負けて、
中国にすがる香港政府
11月末、反中的言論を繰り返した香港紙「アップル・デイリー」(参考:『香港からリンゴが消えた日』)の社主だった黎智英(ジミー・ライ)被告が国家安全法絡みの裁判で英国人法廷弁護士を起用したことをめぐって、香港律政司(法務省に相当)が起用阻止を求めて法廷に訴えた。その理由は、「外国人には国家安全法は理解できないし、裁判自体が国家の安全に関わる案件で国家機密に触れる」だったが、律政司は最終法院まで3回も敗訴した。
英国の「コモン・ロー」制度を原則継続している香港では、同制度を採る海外から弁護士や裁判官の起用が認められている。実際、(中国全人代が定めた)国家安全法でも、外国人裁判官が「国家安全法指定裁判官」に名を連ねているのである。だから、「外国人には国家安全法は理解できない」という理由はまったく成り立たないものだった。
だが、4回目の敗訴直前に、親中派の大物が「もし法廷で阻止請求が受け入れられなければ、(北京で行われる)全人代で改めて国家安全法の再解釈という手段を取る」とすごんでみせた。そして実際に李長官は、最終法院の判定の直後に「再解釈を全人代に請求した」と発表した。
事態は「香港の司法の独立性を否定するもの」と深刻な懸念が広がった。だが、もともと国家安全法は制定当初から、民主派の最大資金源だったとされる黎被告がターゲットだと言われてきた。だから、李長官にしても律政司にしても、黎被告を打ち落とすためなら、いかなる手段も中国政府の意に沿うと信じていたのであろう。
中国の「大転換」からすれば、
香港は「ささい」な扱い
しかしそれから2週間後、メディアに中国政府から返事はあったかと問われた李長官は「法廷が処理するはずだ」と答えをはぐらかした。そしてその直後に親中派議員が「法の解釈は行われない可能性が高い」と言いだしたのである。
このとき北京では新十条を受けて中央経済工作会議が行われ、景気と経済回復のための経済刺激策が話し合われていた。その結果として発表された新しい方針は、ここ数年政府が厳しい取り締まりの目を向けてきたIT業界や不動産業界を支柱産業とするというもので、ここでも180度の転換が起きている。
結局のところ、中国政府にとって、コロナ対策や経済回復など歴史的大転換のさなかに、香港や親中派の忠誠心やメンツなぞ「小せぇこと」なのだ。そこに気付けないまま、中国のバックアップを信じ、頼りにしてきた香港の親中派は、今後いかにして香港のかじを取っていくのか。なんだか、これまで以上に頼りないことになりそうな予感がする2022年の暮れである。