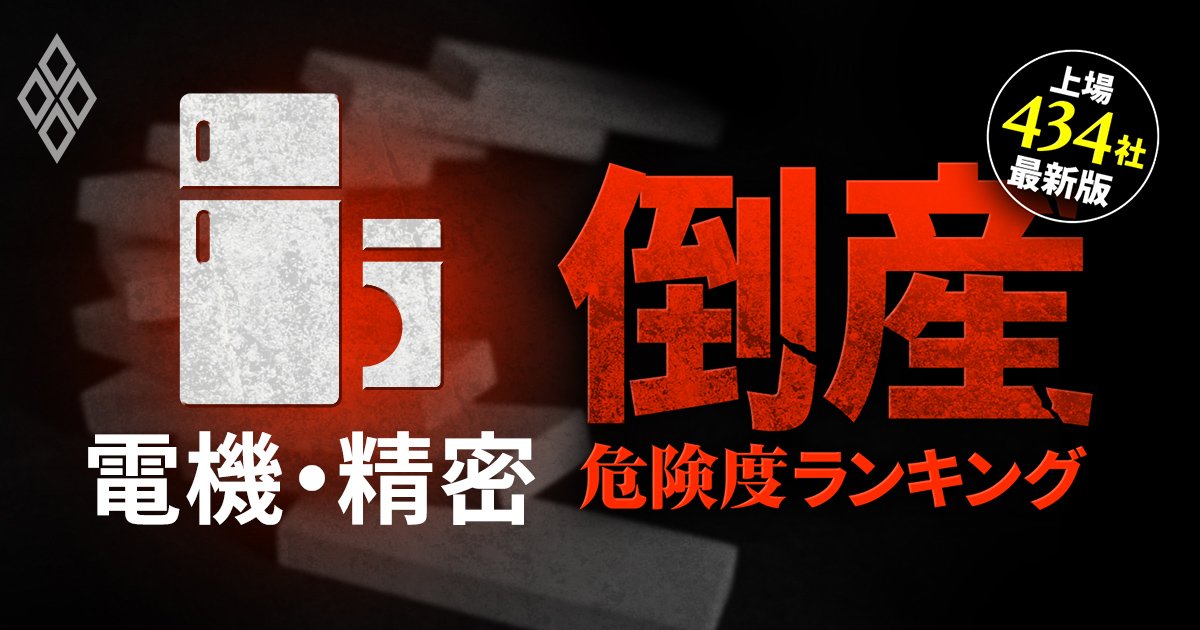宅配ロボットや介護ロボットには参入の壁
飲食業界の一部でようやく始まった配膳ロボットの導入だが、宅配や介護ロボットとなるとさらに高い壁がある。
介護用ロボットは移乗や移動支援の車いすを中心に市場性が見込まれているが、ロボットそのものの機能や仕様とは別の、意外な理由で参入が難しくなっているのだ。
介護現場に詳しい人材コンサルタントの杉本希世志さんは、「ロボット導入に際して、現場は『万が一事故でも起きたら』というストレスを抱えることになります。ただでさえ職員の負担が重い中、ロボットに任せて何か起きたときの責任問題はとても背負いきれるものではありません」と語る。
一方で、中国ではAI(人工知能)を搭載した車いすに目的地を入力すると、複数の車いすをつないで走る「カルガモ走行」が一部で実現している。中国でこうしたことができる理由について、杉本さんは「多少のことには目をつぶるある種の合理性と、走りながら考えることができる国民性があるためでしょう」と述べている。
宅配に関しては、中国では置き場を特定して住民がそこまで配達物を取りに行くのが常態化していたが、近年はエレベーターに乗ってロボットが届けてくれるというサービスが普及し始めた。日本でも深刻なドライバー不足を背景に、「(玄関前など最終配送先までの)ラストワンマイル配送」の実現が待たれており、官民協議会を立ち上げ、自動走行ロボットの導入に向けた検討を進めている。
しかし、安心・安全を最重視する日本では“一足飛びに”とはいかない。経済産業省ロボット政策室によると、「配送ロボットについては一部の商業施設で実用化しているが、宅配ロボットの実証実験は始まっておらず、導入はまだ先のことになります」という。
前出の村田さんは、「日本では業界の連携が難しく、また、こうした試行錯誤の段階でロボットの行動が何らかのトラブルを生むと、一歩前進が余計に困難になる」と話している。