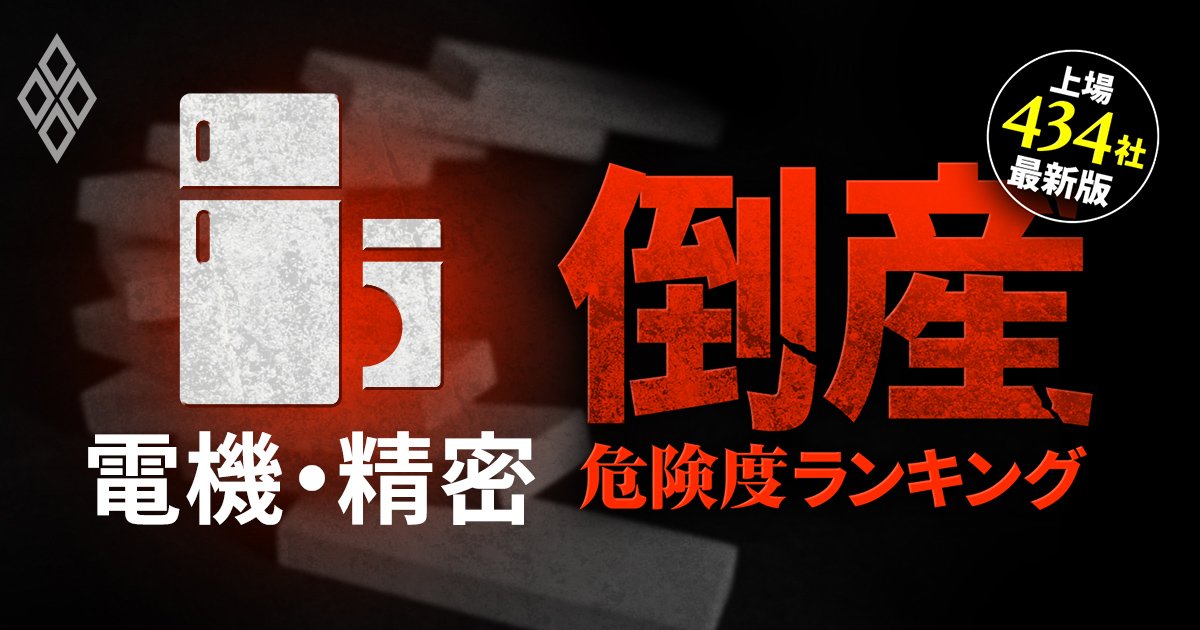サービスロボットがもたらす課題
日本で普及する中国製のサービスロボットだが、その先は必ずしも良いことばかりではない。その一つに“安価な中国製”が仕掛ける価格競争がある。普及黎明(れいめい)期の日本でさえ、すでに過当競争は始まっているのだ。
中国製の配膳ロボットや除菌ロボット、またはAI搭載型案内ロボットは、日本で約200万円台後半から300万円台で販売されているが、これは日本製が全く太刀打ちできない価格であり、さらに価格破壊が進行すれば、日本の技術開発によるサービスロボットの出る幕はほとんどなくなってしまう。村田さんは「ベーシックな機能だけの仕様にすれば、本体価格100万円を切る中国製ロボットさえも出てくる可能性があります」と語っている。
一方、中国の製造業に詳しい日本の技術者は、性能と価格であっという間に世界の市場を席巻した中国の太陽光発電分野を例に挙げ、「日本は中国製を購入して販売する側になった。同じことが、サービスロボットでも起こるでしょう」と嘆息する。
さらに、日本の労働者の、無視できない声もある。「自分たちはクビになってしまうのか」という切実な不安だ。数年前、筆者の住む街の大手食品スーパーのレジが自動化された際、レジ打ちを得意としていた女性パートタイマーさんたちが一斉に姿を消した。白髪交じりの方も多く「これから先の職探しも容易ではないだろう」と考えさせられた。
ちなみに、ドイツではフランクフルトの空港などでの導入はあるが、「ロボットは物を動かすことに対して導入されてはいるが、対人のサービスやサポートでの導入が進むかどうか」とミュンヘン在住のジャーナリストは話している。ドイツでは労働組合の力が強く、政府は生活者が職を失わないよう配慮する一面があるという。
「安くて便利」は中国製品が持つ“不動の価値”だが、サービスロボットの領域では経済合理性以上に、人とロボットの調和がより問われてくるだろう。