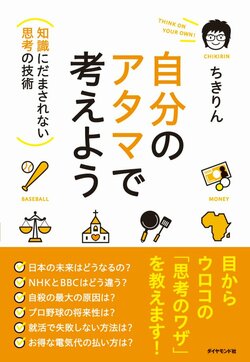「第一志望だった企業に就職できたのに、3年も経たずに辞めてしまった」「働いてみたら、自分の性格に合わなかった」といった就職におけるミスマッチは、いつの時代にも起きていることだ。これは、しっかり企業研究もして万全の態勢で臨んでいたとしても起こりうることではある。しかし、なぜそんな状態に陥ってしまうのだろうか。それは「仕事選びのフィルターが間違っているから」だと、社会派ブロガーのちきりん氏は指摘する。本記事では、ちきりん氏の著書『自分のアタマで考えよう』の内容をもとに、「自分のためのフィルター」を持つことの重要性や、そのフィルターの見つけ方について紹介する。(構成:神代裕子)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
就活に企業研究は必要か
転職経験のある人は、学生の時の就職活動と転職活動で、会社を選ぶ基準が大きく変わったという人も少なくないだろう。
なぜなら、学生時代は「業種」や「企業の規模」など、アバウトなフィルターで仕事を探しがちだが、転職の場合は働く状況をより具体的にイメージするからだ。
筆者も新卒での就職活動の時は、企業研究ばかりして、「こんな有名な企業に入れたらいいな」「この仕事が面白そうだからこの仕事に就きたい」といった漠然としたイメージで企業を探していたように思う。
しかし、そんな探し方だと実際に働いたときに「思ったのと違った!」となるのは仕方がないと言わざるを得ない。
その失敗例の一つとして、ちきりん氏は「『勉強が好きだから』という理由で研究者の道(博士過程への進学)を選ぶパターン」を挙げる。
「勉強が好き」の落とし穴
博士過程へ進学した彼らは、次のようなフィルターの変化を体験することが多いのだという。
・「勉強が好きか嫌いか」
・「その分野について強い興味があるかどうか」
あとから気がついたフィルター
・「狭く深い仕事か、広く浅い仕事か」
・「おもに1人で取り組む仕事か、チームで働く仕事か」
勉強とひと言で言っても、「深く狭く突き詰めるタイプの勉強」と「広く浅く多くを学ぶ勉強」があり、そのふたつは大きく異なる。
「このふたつを分けるフィルターの存在に気がついていないと、自分にはまったく向いていない職業についてしまうことになる」とちきりん氏は指摘する。
しかし、まだ働いたことがない学生が、自分にとって興味のあるフィルターを獲得するのは難しい。
「自分に合ったフィルター」を見つける方法
「自分にとって興味のあるフィルター」を見つけるために、ちきりん氏は「実際に働いてみること」をすすめる。
週2回ほどのアルバイトや、夏休みだけの仕事でもいい。さまざまな体験をすることで、「自分の職業選びに有効なフィルター」が見つけられるという。
ちきりん氏は、自身の体験を次のように語る。
ただ、気をつけたいのが、あくまでもひとつのフィルターは「ある特定個人」にとって有効なのであって、誰にでも使えるわけではない、ということだ。
実際、筆者も学生時代飲食店でアルバイトをしたことがあったが、ちきりん氏と違って「消費者と直接やり取りする仕事は大変だ」と感じたのを覚えている。
今思うと、転職する際に「BtoCの仕事よりもBtoBの仕事の方が自分には合っている」と考えるようになったのは、この時の経験から得たフィルターからだったのだろう。
このように、同じ職業を経験しても、「自分に合ったフィルター」というのは人によって異なるのがわかる。
自分に合った仕事を選ぶためには、まず「自分のためのフィルター」を見つけることが大事なのだ
ビジネスでも重要な「独自のフィルター」
さらにちきりん氏は、「独自のフィルターを持つ重要性は、職業選択だけに当てはまる話ではない」と指摘する。
家電を例に見ると、家電市場において、消費者は長らく「機能」と「価格」というフィルターで商品を選んできた。
しかし近年、そこに「デザイン」というフィルターが欧州のブランドから持ち込まれたことで、市場が変化したのだという。
「機能」は日本製に及ばず、「価格」も割高と言われていた欧州メーカーの商品が、「デザイン」が良いことによって消費者から選ばれるようになっていったのだ。
他にも、企業への投資の基準もここ数年で大きく変化している。
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点から企業を分析して投資する「ESG投資」が注目されるようになったのだ。
この「ESG」がまさに「新しいフィルター」で、投資先として選ばれる企業の基準が変化していると言える。
情勢が目まぐるしく変わる現代において、こういったフィルターの変化についていけるか、新たなフィルターを提案できるかは、企業が生き残っていけるかどうかに直結しているのではないだろうか。
「考える力」で独自の選択基準を見つけ出す
こういった「独自のフィルター」を持つことの意義について、ちきりん氏は次のように語る。
「自分独自のフィルター」を見つけるためにも、「自分の頭で考える力」は不可欠ということだ。
本書には、ちきりん氏が使っているさまざまな「思考力を高めるための手法」が紹介されている。
本記事を読んで「もっと自分の頭で考える力を身につけたい」と感じた人は、一度手に取ってみてはいかがだろうか。
きっと役に立つ方法が見つかるに違いない。