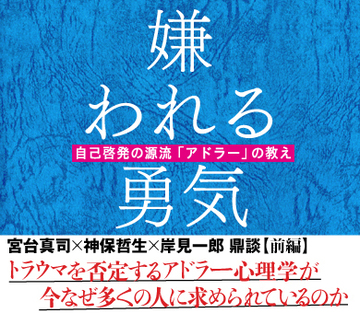世界に多大な影響を与え、長年に渡って今なお読み継がれている古典的名著。そこには、現代の悩みや疑問にも通ずる、普遍的な答えが記されている。しかし、そのなかには非常に難解で、読破する前に挫折してしまうようなものも多い。そんな読者におすすめなのが『読破できない難解な本がわかる本』。難解な名著のエッセンスをわかりやすく解説されていると好評のロングセラーだ。本連載では、本書の内容から「名著の読み解き方」をお伝えしていく。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
万学の祖がとことん考えたらこうなった
「人は誰でも生まれつき知ることを求める」。
これが『形而上学』第一巻の冒頭です。
人間の知的好奇心は、それが役に立たないとわかっていても「知りたいから知る」「思わず考えてしまう」ということです。
これが哲学なのです。
アリストテレスの形而上学では、あらゆる学問に共通する「存在」について説明されます。
アリストテレスは「存在」の最も一般的な形式を10個に分類しました(カテゴリア)。
たとえば、これは猫だ(実体)、うさぎは白い(性質)、重さが200グラムだ(分量)、私の父母(関係)、棚に並んでいる(場所)、昨日見た(時間)、立っている(様態)、本を持っている(所有)、走っている(能動)、壊されている(受動)となります。
そのなかで「何であるか」という問いに対して、「人である」「馬である」などの「馬」や「人」が個物であり「実体」です。
「この馬は速い」「この馬は大きい」という表現ができ、これは「主語と述語」という形式になっています。実体はその同一を保ちながら、様々な性質をもちます。
ソクラテス(実体)が立っている、あるいは座っているというように、実体に述語として、様々な説明が付け加えられるわけです。
実体とは性質や分量において変化しながらもそれ自身は変わらない概念です。
ソクラテスは、若くても歳をとってもソクラテスという実体を維持します。
原因をたどっていくと不動の第一原因につながる
「実体」すなわち、存在する「個物」(コップとかペンなどのこと)は、「形相(けいそう)」と「質料(しつりょう)」によって説明されます。
「形相」は設計図であり、「質料」は材料のことです。
銅でできた彫像は、彫像という「形相」と銅という「質料」が合わさってできています。銅でできたコインは、コインという「形相」と銅という「質料」でできています。
同じ銅という「質料」でできていても、それぞれの「形相」が異なるので、使用目的も異なります
つまり、「形相」は目的を決める内在的な要因ということになります。
質料は形相によって限定されるもの、あるいはまだ限定されていないが形相をとりうるものです(銅は彫像になったりコインになったりする)。
だから、質料は未完成の可能性をもっています(可能態)。一方、形相は、未完成の質料が完成した「現実態」です。
たとえば、樫の実は、見た目はなんの木になるのかはわかりません。でも、生長すれば樫の実は樫の木になるのであって、杉の木にはなりません。
ということは、すべての種子には目的をもった形相がプログラミングされていることになります。
個物は生まれて、育って、同じ形相の個物を産んで終わるという目的をもっています。私たちの行為にもまた、すべて目的があります。
散歩は健康のため、健康は働くため、働くのは給料をもらうため、給料をもらうのは家族を養うため……というようにさかのぼって考えられます。
けれども、これが無限に続くのなら「人生はなんのためにあるのか?」と虚しくなるでしょう。
よって、目的は無限に遂行されてはいけません。もはやそれ以上問うことのできない究極の目的があるはずです。
アリストテレスは、その究極の目的としての存在(不動の動者)が世界を動かしていると考えました。
機械文明が進んだ現在において、結果や利益ばかりが追い求められ、そのなかで忘れ去られているものは、人生の「目的」なのかもしれません。
人間は享楽的なものを求めますが、その本質的な価値を求めることが理想とされます。
「美味しいものを食べる」もいいかもしれませんが、「美味しいもののレシピをつくる」の方が、より本質的な価値に近づきます。
現実の成り立ちを「目的」の観点からながめれば、すべての出来事は一つのことに向かっていっていることがわかる。物事を「どのようにあるか」ではなく、「その目的は?」と考えることで新たな切り口が見える。