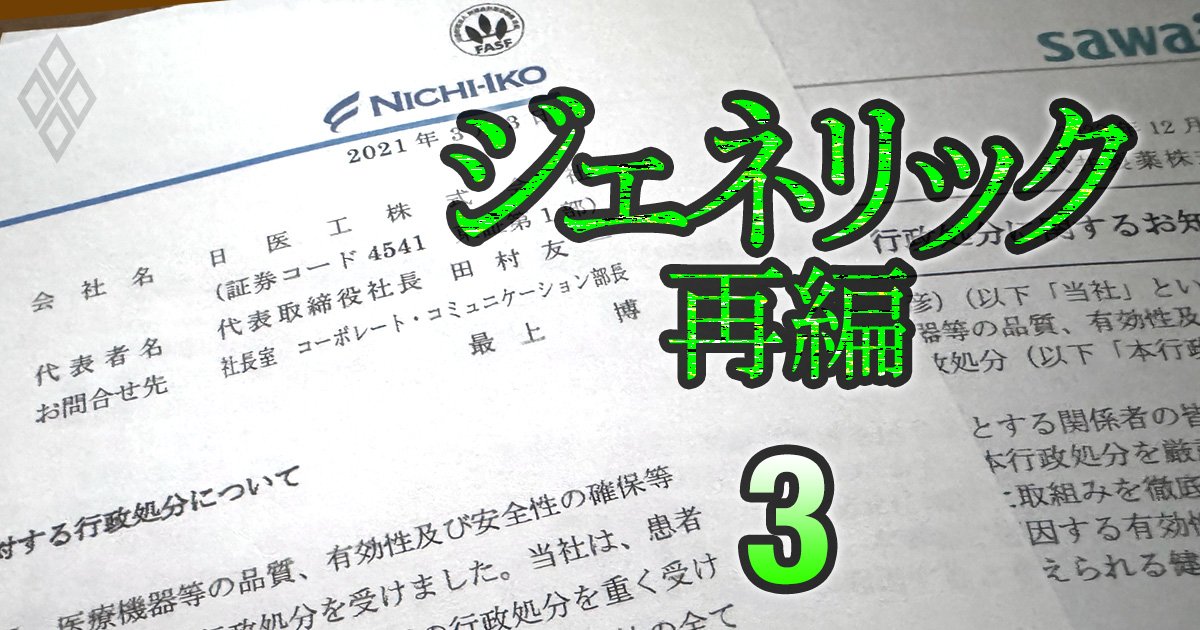オンボーディングと資料の共有が前提となっていれば、新メンバーが加わるたびに現状とドキュメントで異なる部分が見つかり、更新されていきます。するといつもフレッシュな情報をチーム全体で共有することが可能になります。
もう1つ、既存メンバーはオンボーディングを行うことにより、メンタリングスキルを向上させることができるというメリットがあります。硬直化した組織では、若いメンバーが自分からオーナーシップ、リーダーシップを持って仕事を進める機会に、なかなか恵まれないこともあります。しかし、誰かが新しく入ってきてメンタリングする機会があれば、自分がリードしてオーナーシップを持つ、いいきっかけとなります。インターンシップで学生を招き入れる企業も増えているかと思いますので、そうした機会を通じて若手メンバーがメンタリングやオーナーシップ、リーダーシップを持つ経験を積むのもよいのではないでしょうか。
オンボーディングは採用の最後のステップ
「やるのが当たり前」
事業部門が採用に主体的に関わるようになれば、「この人に来てほしい」という候補者を自らスカウトするぐらいの働きかけをするようになり、「苦労して入れた人がパフォーマンスを出すまでが自分の責任」と感じるようになるでしょう。それがうまくいかずに1カ月もたたずに辞められてしまえば、それまでの時間も努力も水の泡になるからです。
採用にどれだけコミットしているかによって、オンボーディングの必要性や感じ方は違ってくると思います。オンボーディングが採用の最後のステップだと思えば、組織の側としては「やるのが当たり前」と考えるようになるでしょう。
スタートアップなどでは、採用が決まって候補者にオファーレターを出しても本当に受け入れてもらえるかわからない、受け入れてくれても入社当日に本人が来ないこともしばしばで、1週間で辞めてしまうこともよくあると聞きます。
CEOやCTOが自分の時間の半分以上を使ってエンジニアをやっと採用できたという場合、形式化されたオンボーディングは実施できなくても、実質的にはその人がパフォーマンスを上げられるところまで、かなり丁寧にケアするはずです。あるスタートアップのCEOは「オンボーディングが終わって初めて、採用が終わったと考えるようにしている。花を持たせるまでが採用だ」と話していました。
採用した人が辞めた、あるいはパフォーマンスが出せなかった場合、人事や会社の責任もあるのかもしれませんが、多くはその組織の問題であり、組織のマネジャーの問題といえます。結局、事業の成功にとって、人材が占める割合は大きいのです。そういう意味では、日本企業では人材重視の意識がまだまだ甘いのではないかと感じます。
(クライス&カンパニー顧問/Tably代表 及川卓也、構成/ムコハタワカコ)