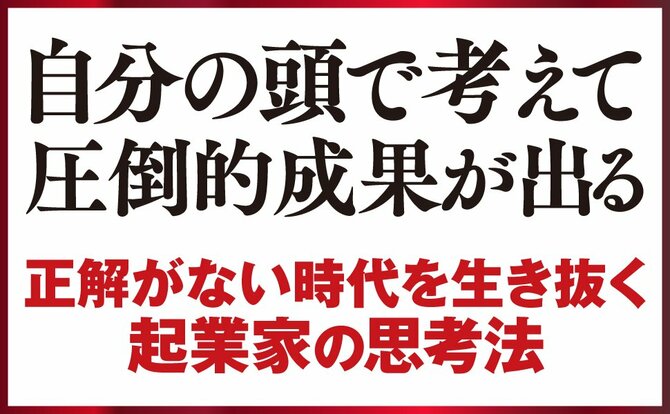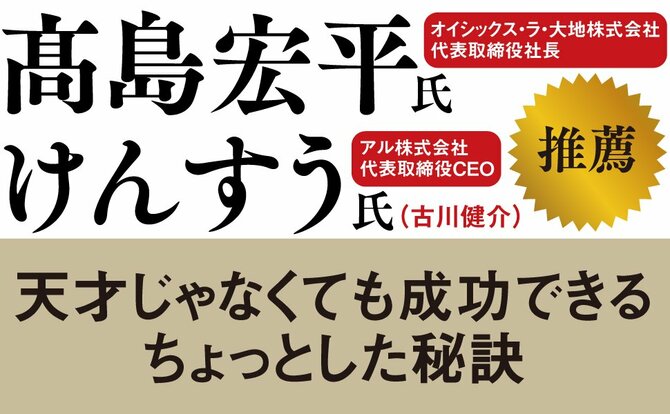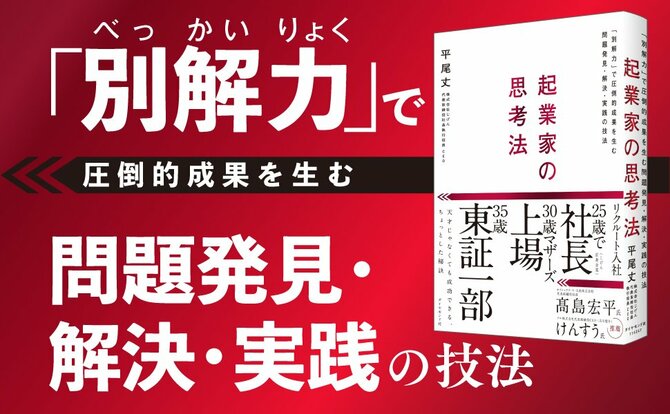転職してきた期待のエースが、うまく機能しない。他の組織では活躍できていたのに、自分の部下になった途端、成果を出せなくなった──。自分の指導方法が悪いのだろうか? 相性がよくないのだろうか? そんなふうに、悩んでいる管理職もいるのではないだろうか。
リクルートに入社し、25歳で社長、30歳で東証マザーズ上場、35歳で東証一部へ。創業以来12期連続で増収増益を達成した気鋭の起業家、株式会社じげん代表取締役社長執行役員CEO・平尾丈氏は、「起業家の思考法を身につけることで、正解がない時代に誰もが圧倒的成果を出すことができる」と語る。
本稿では、平尾氏が執筆した『起業家の思考法 「別解力」で圧倒的成果を生む問題発見・解決・実践の技法』より一部を抜粋・編集して、「優秀なのに、実力を発揮しない部下の扱い」を紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「優秀なのに実力を発揮しない人」
どう指導するのがベスト?
「もったいないなあ」と、見ていてやきもきするような部下は、あなたのまわりにいるだろうか?
コミュニケーション能力が高く、器用で、入社当初から期待されていた。にもかかわらず、実力を発揮しない。どこか手を抜いているように見える。
「この仕事、何のためですか?」と、やたらと聞いてくることも多い。
もっと時間をかければ、もっと自発的に動き、頭をひねれば、成果を出せそうなものなのに、ほどほどのところで手を止めてしまう。
だから、なんだかんだいつも、期待値の90%くらいの結果しか残せない……。
このように、そこそこまではいけても、パフォーマンスを100%以上発揮できない「優等生」型の社員は少なくない。
上司としても、もっと高い目標を与えて背伸びさせるべきなのか、今のままのペースで見守るべきなのか、かなり迷うところではないだろうか。
そのようなタイプの人に、自分の実力を発揮してもらうためには、いったいどうすればいいのだろう?
そんなとき、ぜひ確認してみてほしいことがある。
それは、ただやる気がないのか、それとも、仕事の全体像がわからないからどう動いていいかわからないだけなのか、ということだ。
真面目な人ほど、成果の出し方がわからない
『起業家の思考法』によれば、変化が激しく不確実性が高い「正解がない時代」の今、真面目にコツコツがんばってきた優等生タイプの人ほど、成果の出し方がわからなくなっているという。
過去に結果が出たやり方や、他人の成功パターンはすぐに陳腐化してしまう。
「これなら確実に正解を出せる」とわかっているものに関しては全力で取り組めても、正解がない問いに関しては、ブレーキを踏んでしまう。やる気がないわけではなく、どう取り組めばいいのかわからないだけかもしれないのだ。
そういう「もったいない人材」をグンと成長させるためにまずやるべき第一歩は、「今、取り組むべき問題を明確にする」こと。そして、「自分で問題を発見する力」を身につけてもらうことだ。
デキる上司は「なぜ」を伝えるのがうまい
まずは、「なぜ、この仕事をやるのか」を因数分解して伝えるのがおすすめだ。
本書では、「問題発見力」を高めるためのステップとして、仕事の「目的」を具体的にすることが非常に重要であると綴られている。
「この仕事をやることで、会社にどんな利益をもたらすことができるのか」
「なぜ、チームの中で自分が指示を受けたのか。自分が仕事を終えたあと、上司はこれをどうするのだろう。さらに上の管理職と相談するのだろうか」
などなど、自分がやるべき業務が、どんな仕事の一部なのか、その仕事を仕上げた先に何があるかなど、全体像が把握できるようになるだけでも、働き方はずいぶん変わる。
上司からいちいち指示されなくても、自分で先回りして動けるようになる。逆に言えば、全体像がわからないまま、むやみに動いて上司に迷惑をかけたくないと思ってしまうのも、自然なことだろう。
仕事の価値や意味がわかれば、その仕事にどのように取り組めばいいかがわかります。
全体の価値がわかれば、仕事のやり方が変わってくるのです。何のためかがわかったほうが、人間は折れません。(P.69)
「いいからやれ」が部下の可能性を潰す
「この仕事、何のためですか?」と聞かれて、「いいからやれ」とごまかしてしまったことはないだろうか。
いちいち目的を聞かれたら、「生意気に、噛み付いてきたな」と、ついムッときてしまうかもしれない。
しかし、全体像を把握した上で仕事したいから、聞いているだけかもしれない。
「よりよい仕事をするために全体像を把握したかったのに、一蹴された」という恐怖心を与えることで、「言われたことだけやっておいたほうが無難」と思わせてしまっては、本末転倒である。
ポテンシャルが高いのに実力を発揮しきれていない部下の問題発見力を封じ、より「優等生」的な働き方を促しているのは、もしかすると、上司である自分自身の言葉かもしれないのだ。
「なぜ、この部下にこの仕事をやらせなければならないのか?」
「この仕事をどのように仕上げてもらいたいか?」
「この仕事をやらせることで、部下にどのようになってもらいたいか?」
をあらためて言語化することは、自分自身の「問題発見力」の向上につながる。
本書では、取り組むべき問題を定義し、掘り下げるためのフレームワークが具体的に解説されている。絶対的な正解のない不安定な現代において、「問題発見力」の高い人材がどれだけいるかが、組織の勝敗を分けるのかもしれない。