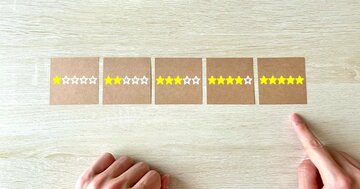世界のビジネスエリートの間では、いくら稼いでいる、どんな贅沢品を持っている、よりも尊敬されるのが「美食」の教養である。単に、高級な店に行けばいいわけではない。料理の背後にある歴史や国の文化、食材の知識、一流シェフを知っていることが最強のビジネスツールになる。そこで本連載では、『美食の教養』の著者であり、イェール大を卒業後、世界127カ国・地域を食べ歩く浜田岳文氏に、食の世界が広がるエピソードを教えてもらう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
なぜ、アメリカで美食は発展しないのか?
アメリカにも良いレストランはありますし、才能あるシェフはたくさんいます。ただ、人口比で考えると、数は少ない。そして、美食、ガストロノミーという観点でいうと、残念な国です。
僕は、アメリカの根本的な問題は、食べ手の意識だと思っています。料理人のせいではありません。語弊があるかもしれませんが、端的にいうと、自分が食べたいものを作れ、という文化なのです。
だから、テイスティングメニューだけの店は、それが当たり前の業態(日本の鮨や割烹)を除けば、全米を探しても数えるほどしかないのです。テイスティングメニューのある店でも、アラカルトの選択肢を設けるのはほぼ必須になっていますし、実際アラカルトを好むお客さんが多い。自分が何を食べるかを人に決められたくない、と考える人が大半なのです。
そういう人たちにとって、料理人は自分の望む「うまい」を提供してくれるサービスプロバイダーでしかありません。クリエイターとしての料理人にリスペクトを持ち、それを味わいたいと思っている人が極めて少ないのです。
NY、LAでも厳しい「食べ手」問題
ニューヨークですら、美食を追求するレストランをやれる才能があるのに、そこに需要がないからカジュアル店で甘んじている料理人がいたりします。地方だとなおさらで、せっかく国内外の名店で修業したのに「うまい」だけの料理をアラカルトでやるカジュアルなレストランを営んでいる、という例がたくさんあります。
ただ、こういうレストランの中には、月に一度だけコースでガストロノミーの色彩が濃い料理を提供する日を作って、少人数の理解がある常連さんに提供しているという店もあります。通常営業でやりたい料理ができていなくても、クリエイターとして心が折れていないのは、本当にすごいことだと思います。だから、料理人が悪いのではなく、食べ手の意識の問題なのです。
そもそも、アメリカ人の多くは、レストランを料理と向き合う場所として認識していないように思います。どちらかというと、家族や友人と楽しい時間を過ごしたり、ビジネスの接待をしたりするためのエンターテインメント施設であって、料理はお洒落な内装や盛り上げてくれるBGMと同じく、そのひとつのアトラクションでしかないのです。
もちろん、誰と食べるかだったり、内装や音楽も大事です。そして、日本のレストランは学ぶべきところがあります。ただ、料理自体を楽しみに訪れるお客さんが少ないと、ガストロノミーを追求するようなレストランがなかなか成り立たないのも不思議ではありません。
アメリカの大都市で、一番この傾向が強いのが、ロサンゼルスではないかと思います。もともと、テイスティングメニューのみの店が皆無に近かったのが、ようやくここ10年で機が熟し、世界のベストレストラン50にランクインが期待されるような意欲的な店も登場してきました。
ただ、残念ながら、コロナ禍でそれらの店は壊滅しました。ようやく2024年になって再開しつつある店もありますが、ファインダイニングを諦め、カジュアルレストランに業態を転換して成功している店もあります。ビジネスの観点からは繁盛しているのはいいことですが、シェフが本当にやりたいことが絶たれてしまい、才能のあるシェフが美食を追求できなくなってしまったのは、料理界にとっても損失だと思っています。