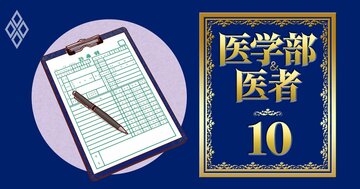そのうちの1つが、医療保険の制度がどうなっているかとか、医療費をどうやって抑えていくのかといった医療経済についての知識です。
実は私は東京医科歯科大学と一橋大学の合同授業で、毎年のように総合診療が医療費抑制にどう貢献できるのかを医者の立場から学生たちに教えています。こういうテーマは医学部の授業ではほとんど扱われないので、東京医科歯科大学からの申し出で一橋大学との合同授業を設けるようになったのです。ほかにも審議会で医療政策に関わっているような人など錚々たる面々が講師として集まっていて、とても充実した内容だと思います。
ところがこの授業を聞きにくるのは看護学を専攻している学生や保健衛生学科の学生だけで、医者の卵である医学部医学科の学生はただの1人もいない年がほとんどです。
最初の頃の授業は一橋の都心部のキャンパスだったので、もしかすると医学部のほかの授業と時間が重なってしまったのではないかという話になり、会場を東京医科歯科大学にしたり、授業の開始時間を18時半にしたりという配慮をして改めて仕切り直したのですが、結果は同じでした。
医学部の学生は医学以外には全く興味がないのか、まともな医者になる気はないのか、と腹立たしく思ったりもするのですが、彼らはもしかすると医学を学ぶことに精いっぱいで、医者になるのに役立ちそうなことを幅広く学ぼうという意欲や余裕を持てずにいるのかもしれません。
アメリカの大学には
基本的に医学部がない
意外に知られていませんが、アメリカの大学には基本的に医学部はありません。
医者になりたい人は、大学を卒業したあとに日本でいうところの大学院にあたるメディカルスクールで学びます。そこで4年間の課程を修めるとM.D.(編集部注/Medical Doctor)の学位を得ることができ、そのうえでUSMLE(United States Medical Licensing Examination)という米国医師免許試験を受けて合格すれば医師になれます。
また、メディカルスクールで学ぶにあたって基本的には大学での専攻は問われないので、例えば演劇を大学で学んだあとに、医者を目指すということもできます。