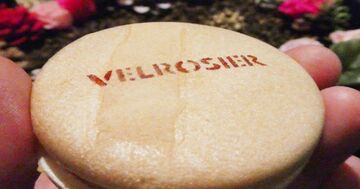2月の京都は降雪で「雪見梅」も。寒波が訪れれば、梅と雪の共演が再び見られるかも
2月の京都は降雪で「雪見梅」も。寒波が訪れれば、梅と雪の共演が再び見られるかも
節分が過ぎ、暦の上では春を迎えました。今回は京都随一の梅名所である北野天満宮をはじめ、無料で梅観賞が楽しめる穴場までご紹介します。梅は桜に比べて存在感が控えめですが、花びらの愛らしい形や品種ごとに異なる多様な香りが魅力。早春の彩りと香りをめでながら、まだまだ続く冬の寒さを乗り越えましょう!(らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部)
バラ科の「梅」は彩りも香りもさまざま
「節分」が過ぎて暦の上では春を迎えました。今年は、「節分の日って毎年2月3日と決まっているわけではない」という話題をよく耳にしました。地球が太陽の周りを一周する公転に要する日数、つまり一年間は「365日」といわれていますが、小数点以下に微妙な端数が生じるため、4年に一度のうるう年以外にも、端数が積もり積もったずれを調整する必要が出てくるということです。前回そのずれを調整したのが4年前の2021年。そのもう一つ前は、今から128年も前の1897(明治30)年だったのだそう。ちなみに、次に節分が2月2日となるのは4年後の2029年ですので心しておきましょう。
さて。春のはじまりを飾るのにふさわしい花といえば、梅でしょうか。平安時代に編まれた『古今和歌集』では、桜にまつわる歌が約140首、梅が約20首でしたが、それより昔の奈良時代に編まれた『万葉集』では、桜が約40首、梅が約130首。歌の数については諸説ありますが、古くから愛された花であったことがうかがえます。
一重や八重といった花びらの重なり、紅、淡い緋色、乳白色、純白といった色彩など、一言で「梅」といってもバリエーションはさまざまです。楚々とした香り、甘やかな香り、妖艶な香りなどバラを彷彿(ほうふつ)とさせるほど多彩なのは、梅もバラ科に属するからでしょうか。
今回は、早春の香りを求めて梅の名所を訪ねてみましょう。見頃の情報は、京都市が運営するウェブサイト「京都観光Navi」内の「梅だより」でチェックするといいですよ。