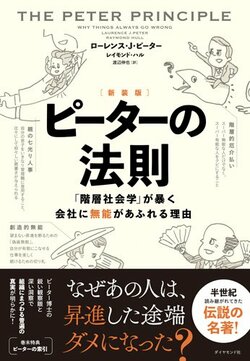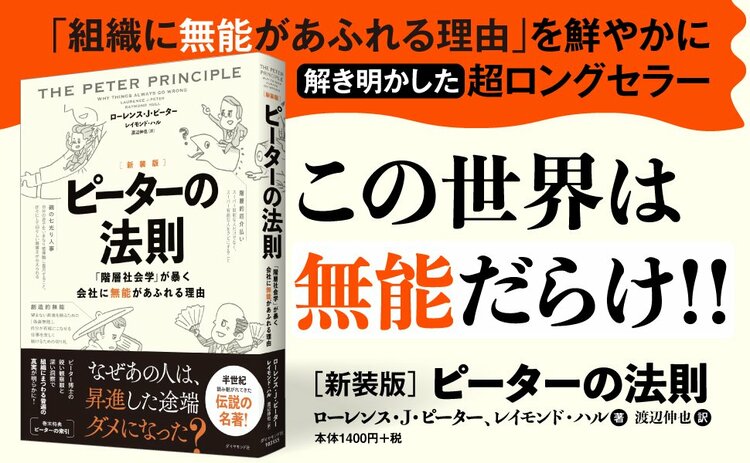階層社会では、人は昇進を重ねると、おのおのの無能レベルに到達してしまう。そんな驚くべき法則を唱え、世界的なベストセラーになったのが、『ピーターの法則』だ。必然的に「世の中のあらゆるポストは職責を果たせない無能な人間によって占められることになる」というメッセージは大きな衝撃を与えることになった。では、そんな世界で個々人が組織で生き残るための知恵とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
昇進した途端、ダメになる理由とは?
帯の文言には、「なぜあの人は、昇進した途端ダメになった?」とある。
企業社会では、そうした声が数多く飛び交っているからに他ならないからだろう。そしてその理由が、豊富な実例とともに、明快かつシニカルに解説されていく。
原著の刊行は1969年。邦訳が出たのが1970年。2018年には、新装版が発売されている。
畳み掛けるようにメッセージしてくるのは、「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する」というピーターの法則。
そして、「やがて、あらゆるポストは、職責を果たせない無能な人間によって占められる」というピーターの必然だ。
どういうことなのか。
仕事で有能ぶりを発揮すれば、昇進という報奨が待ち構えていることが多い。しかし、である。
もし昇進によって、自分の能力が活かせなくなってしまったとしたら? あるいは、昇進した先の仕事が自分の能力を超えたものだったとしたら?
多くの人が、知っておいたほうがいいことがある。
修理工はなぜ、無能な作業班長になったのか
昇進することは、仕事人として素晴らしいこと。そんなふうに思っている人は少なくないだろう。
チームを率いることになれば、周囲からは「あいつはリーダーになったんだな」という尊敬の目で見てもらえる。上司からは、褒め称えられ、部下からは憧れの眼差しで見つめられるかもしれない。
もちろん、給料も上がることになる。これまでの頑張りが認められ、それまで以上の収入を手にすることができるようになるのだ。だから、多くの人は昇進を目指すし、上司は部下を昇進させようと努力する。
しかし、本当に昇進は素晴らしいことなのか。わかりやすいケースが本書で紹介されている。
ティンカーは修理工としては、とても優れていた。しかし、作業班長の仕事は、修理工の仕事とは異なる。自分でエンジンを分解して鼻の頭を真っ黒にしている場合ではなくなるのだ。それは、修理工の仕事なのである。
作業班長がやらなければいけないのは、他の修理工に仕事を割り当てることであり、仕事量やスケジュールを管理すること。
結果的に、ティンカーは昇進したことで、「無能」の烙印を押されることになってしまった。修理工としては有能だったのに。
ティンカーは、自分が満足できないかぎりは作業の終了を宣言しません。絶えず修理作業に首を突っ込むので、彼が机の前で仕事をしている姿などめったに拝むことはできません。(中略)
こうなると、工場は仕事がどんどんたまって混乱し、納車が遅れるのも当然のなりゆきということになります。(P.24)
顧客は修理の完璧さより、約束した納期を守ることを重要視していることを、ティンカーは理解できなかった。
修理工たちにとっては、車のエンジンよりも仕事をして稼ぐことのほうが大事だということにも、考えがまわらなかった。
結果として、ティンカーは顧客と部下のどちらの支持も得られず、無能な作業班長になってしまったのである。
有能だから、次の昇進のチャンスを手に入れられる
本書では、「この事態は、遅かれ早かれ、あらゆる階層社会の、あらゆる人々に起こりうる」と記されている。
先のティンカーは、作業班長で無能ぶりを明らかにしてしまったが、仮に作業班長でも有能だったとして、その次のポジションとしてはどうか。
有能な人は、常に昇進のチャンスを手にすることになる。しかし、それはいずれ自分が無能ぶりをさらけだすポジションにぶつかることを意味する、というのだ。
オーバル、シリンダー、エリプス、キューブの四人にはどこかしら欠点があり、彼らに任せるわけにはいきません。そこで、この作業に最も有能なスフィアを班長に登用することにしました。
さて、そのスフィアは作業班長としても有能であることが証明されたとしましょう。すると、総職長のレグリーが工場長に昇進したときには、スフィアがその空席となったポストに昇格すると予想できます。(P.26)
このとき、もしスフィアが作業班長として無能であれば、もう昇進の声はかからない。つまりは、作業班長の段階で、「無能レベル」に達してしまったということだ。そうすると、もう次のチャンスはない。
一方、班長になれなかったオーバルやシリンダーのような従業員の場合は、階層の最も下ですでに無能レベルに達しているので、昇進することはない。
有能レベルから昇進し、次のレベルでも有能でいられる人もいる。課長から部長になるのもそうだ。
だが、部長が必ずしも次のポジションに進めるわけではない。新しい地位で有能と認められれば、さらに次の昇進が待っている。そして、やがて最後の昇進は、有能レベルから無能レベルへの昇進になっていかざるを得ないというのである。
職業にまつわる夥しい数の無能の事例を分析した結果から導き出された結論が、次の「ピーターの法則」なのだ。
ビジネス界、産業界、労働界、政界、官公庁、軍隊、宗教界、教育界といった世界に従事する人は、一人残らず、このピーターの法則の影響下に置かれるという。その支配から逃れることはできない、と。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。