リーダーが戦場から逃げたら?→歴史に残った“あの夜の選択”
「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
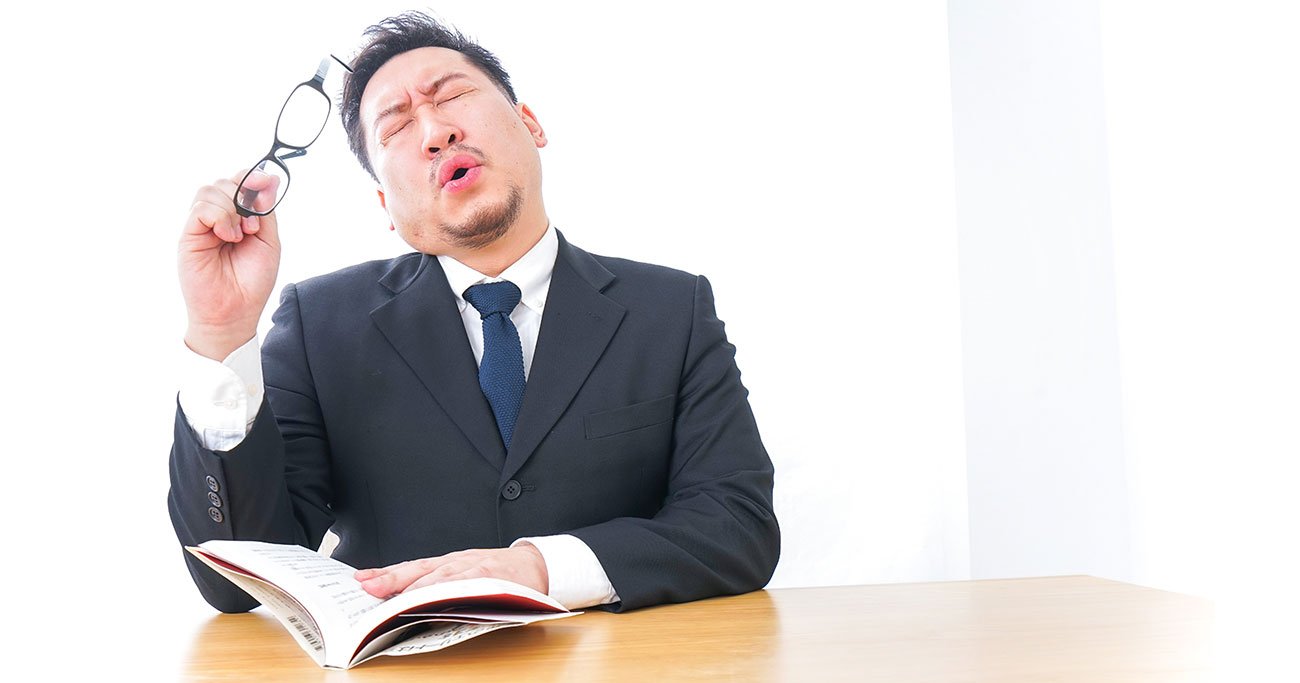 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
衝撃の「敵前逃亡」
幕府軍が厳しい状況に追い込まれたことで、慶喜は戦いに勝てないと判断したのでしょう。
なんと、多くの家臣が戦っているのを放置したまま、少数の側近や老中、会津・桑名藩主を連れて、ひそかに大坂城を脱出。八軒家や浜船着場から小舟で天保山沖(大阪湾)に停泊中の徳川幕府の軍艦「開陽丸」に乗って、江戸に逃げ帰ってしまったのです。
側近の罷免、盟友の切り捨て
当然のことながら、リーダーを失った幕府軍は総崩れとなり、大坂城を焼き払ったうえで、江戸に向かって退却していきました。
江戸に戻った慶喜は、ともに戻った側近を罷免したり、幕府側の主力として尽力した会津・桑名藩主を江戸から立ち退くように求めたりしました。
会津藩にのしかかる悲劇
その後、会津藩主・松平容保(1835~93年)は、失意のうちに会津に戻りましたが、会津を攻めてきた新政府軍と江戸幕府の身代わりのように壮絶な戦いを繰り広げ、多くの悲劇を味わうこととなります。
江戸城、戦わずして明け渡される
慶喜は徹底的に新政府に従う姿勢を示した結果、江戸城は戦うことなく無血開城され、江戸幕府は265年の歴史を終えることとなったのです。
慶喜は本当に「無責任な将軍」なのか?
このように説明すると、慶喜はなんとリーダーシップに欠ける人物なのかと思われるかもしれませんが、その決断すべてが否定されるものではないと私は考えています。
内戦を回避し、日本を守った判断
欧米諸国の海外進出による植民地化が広がっていた時代です。新政府軍との内戦が長引いていたら、当時隆盛を極めていたイギリスやフランスなどが日本を攻め入り、植民地化していた可能性はゼロではありません。
幕府軍は、まだまだ新政府軍と戦えましたが、内戦を長引かせて泥沼化するよりも、天皇を中心とした新体制に移行することを優先した慶喜の決断は、結果的には優れた判断だと思うのです。
「反省」と「評価」のはざまで
そのため、じつはこの話を「徳川慶喜の反省」とすることに私は当初迷いました。しかし、少なくとも多くの家臣を残して敵前逃亡したことは、リーダーとして許されることではありません。
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。










