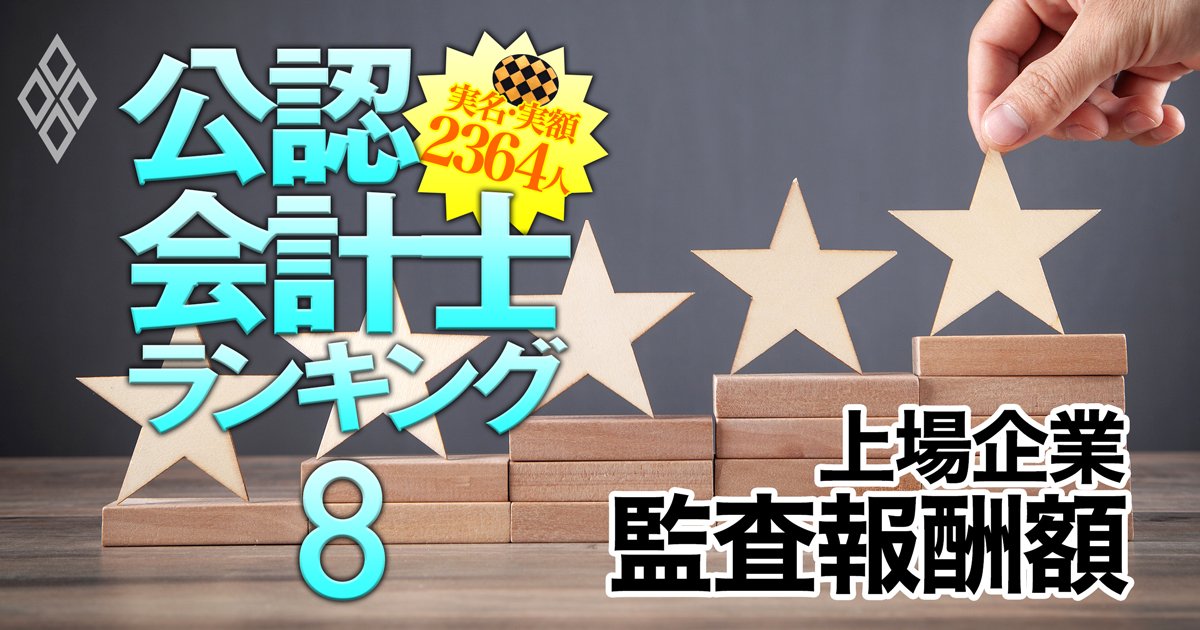また、都道府県別で単純に除算して算出した訪問介護の市場撤退率は、徳島県(企業数254社、倒産・廃業計11件)の4.33%が最大だった。続いて鳥取県(71社、3件)の4.22%、岩手県(178社、6件)の3.37%だった。
企業数が少ない県は市場撤退率が高くなりやすいが、都市部より地方の市場撤退率が高い傾向が強く出ている。これは高齢化が進む中で、地方の中心では大手との競合で利用者の獲得が難しい上に、中心を離れると小規模事業者がメインになるが、訪問地の距離の長さなどで効率が悪く、経営が悪化しやすいことがあげられる。
訪問介護業界は、賃上げが進む他産業との給与の差が広がり、ヘルパーの採用や流出を止めることが難しい。さらに、マイナス改定やコスト上昇で事業継続すら難しい事業者が増えている。
高齢化が加速し、今後も市場拡大を見込まれる訪問介護事業だが、効率の良い都市部でも大手との競争が激しくなっている。また、効率の悪い地方は大手の進出が少ないが、コスト増で採算性が低下している小規模事業者が支えているのが実情だ。小規模事業者の息切れは、訪問介護サービスの途絶を意味する。都市部も地方も、“介護難民”リスクと背中合わせともいえる。
報酬改定や小規模事業者の効率化、人材採用の支援、外国人従事者の定着、事業者同士の連携など、政府と自治体主導の伴走支援がなければ、尊厳を守る老後の人生設計が描けなくなっている。