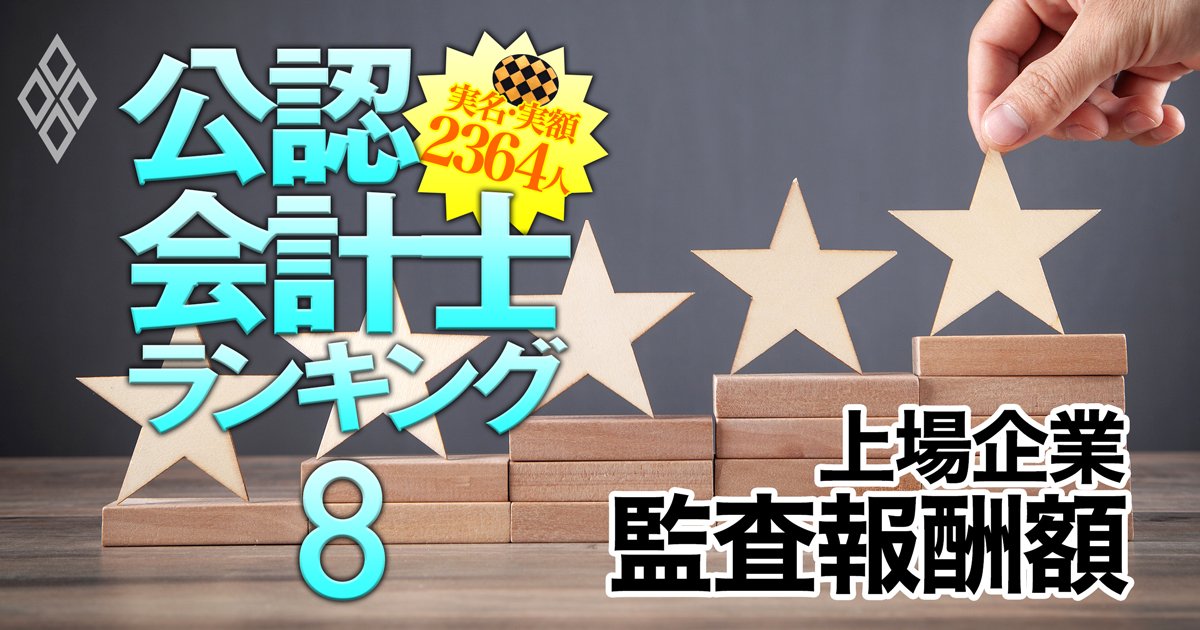リカード派の貿易理論は
自由貿易の犠牲者を救えたか
世界の経済学者の圧倒的多数は、関税なき自由貿易こそ望ましいと信じている。にもかかわらず、トランプ大統領はなぜ関税引き上げに向かうのか。
経済学者の信念の源流は、19世紀初頭に英国の経済学者デヴィッド・リカードが提唱した説に遡る。
リカードは、英国とポルトガルという2つの国を例として挙げた。英国は産業設備が充実し毛織物の生産にたけている。一方、ポルトガルには温暖な気候と肥沃な土壌がありワインの生産に適している。
貿易がないとすると、ポルトガル人はおいしいワインを楽しめるが、毛織物は入手できない。英国には良質の毛織物はあるがワインはない。であれば、お互いに得意な商品をもう一方の国に提供し、それと引き換えに相手の得意な商品を受け取ってはどうか。
これが自由貿易であり、これにより、英国でもポルトガルでも、人々はワインと毛織物の両方を手にすることができ、豊かな生活を楽しめる。
このような根拠から、リカード派は、自由貿易により両国のすべての人々の生活を改善させることができると説く。
本当にそうだろうか。
貿易にメリットがあるのは間違いないが、果たしてそのメリットがすべての人に均等にもたらされるかといえば、その保証はない。各国の不得手な産業は海外からの輸入品の侵食を受け、その産業で元々働いていた労働者は職を失うからだ。貿易のメリットどころか、彼らは自由貿易の犠牲者だ。
カギはいかにして“取り残された労働者”を救うかだ。リカード支持派は、その国の得意な産業で獲得した莫大な利益を増税で吸い上げ、それを不得意な産業で職を失った労働者に回すという所得補填を行うことによって、すべての労働者の生活が改善すると説く。
では、そうした所得補填は実際に行われたのか。欧州諸国では程度の差こそあれ、おおむね所得補填が行われたと評価できる。
これに対して米国では、所得補填が不十分で、結果として不得意な分野(衣類や鉄鋼などのモノづくりの産業)で働く労働者と得意分野(金融や情報通信などのサービス産業)で働く労働者との間で著しい所得格差が生じた。
トランプ再選を支え、関税引き上げを支持してきたのは不得手な産業で働いてきた労働者たちだ。関税を引き上げれば中国からのモノの流入は止まるかもしれない。しかしそれによって米国の不得手な産業の雇用が復活するかといえば、おそらくそうではない。その産業で働く米国労働者の技能は、世界基準からすると相対的に低下しており、その再構築は一朝一夕にはできないからだ。
経済のロジックで言えば、格差是正の王道は、関税ではなく、リカード派の提唱する所得補填だ。しかし政治のロジックは全く別物で、その方向に向かう可能性は残念ながら低い。
日本社会が選択した
「賃金デフレ」という独自の道
こうした中で興味深いのは日本だ。日本はグローバル化が進む中で、米国とも欧州とも異なる、第三の道を歩んできた。日本では不得手な産業での雇用が大きく減らず、これが格差の拡大を抑えた。
なぜそんな芸当が可能だったのかといえば、不得手な産業で賃金を抑制したからだ。
日本は、2000年ごろから、春闘での賃上げを控え、労働者の賃金を毎年据え置くという「賃金デフレ」へと向かい、それによって中国の労働者の賃金に近づけてきた。その代償として労働者の働く意欲が失せ、生産性が停滞したものの、兎にも角にも雇用は維持された(詳しくは拙著『物価を考える』を参照)。
米欧日が三者三様の国内事情を抱える中、自由貿易の旗を降ろすことなく、前に進むことができるのか。世界経済は大きな岐路に差し掛かっている。
最後に、トランプ関税が日本を含む各国の物価にどのような影響を及ぼすかを展望してみよう。