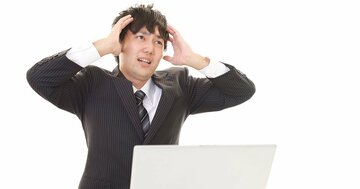ビジネス環境や働き方が大きく変化する中、働く現場では「人と組織」をめぐる課題が複雑化している。近年では、個人の学習・変化を促す「人材開発」とともに、「組織開発」というアプローチが話題になっており、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)のような入門書も刊行された。今回は、こうした「人と組織のあいだに渦巻くモヤモヤ」に正面から切り込んだ話題作『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』の著者であり、気鋭の組織づくりコンサルファームMIMIGURI代表でもある安斎勇樹さんに、「自由に発言していいはずの会議が、なぜ“お通夜”のようになってしまうのか」について話を伺った。(企画:ダイヤモンド社書籍編集局)
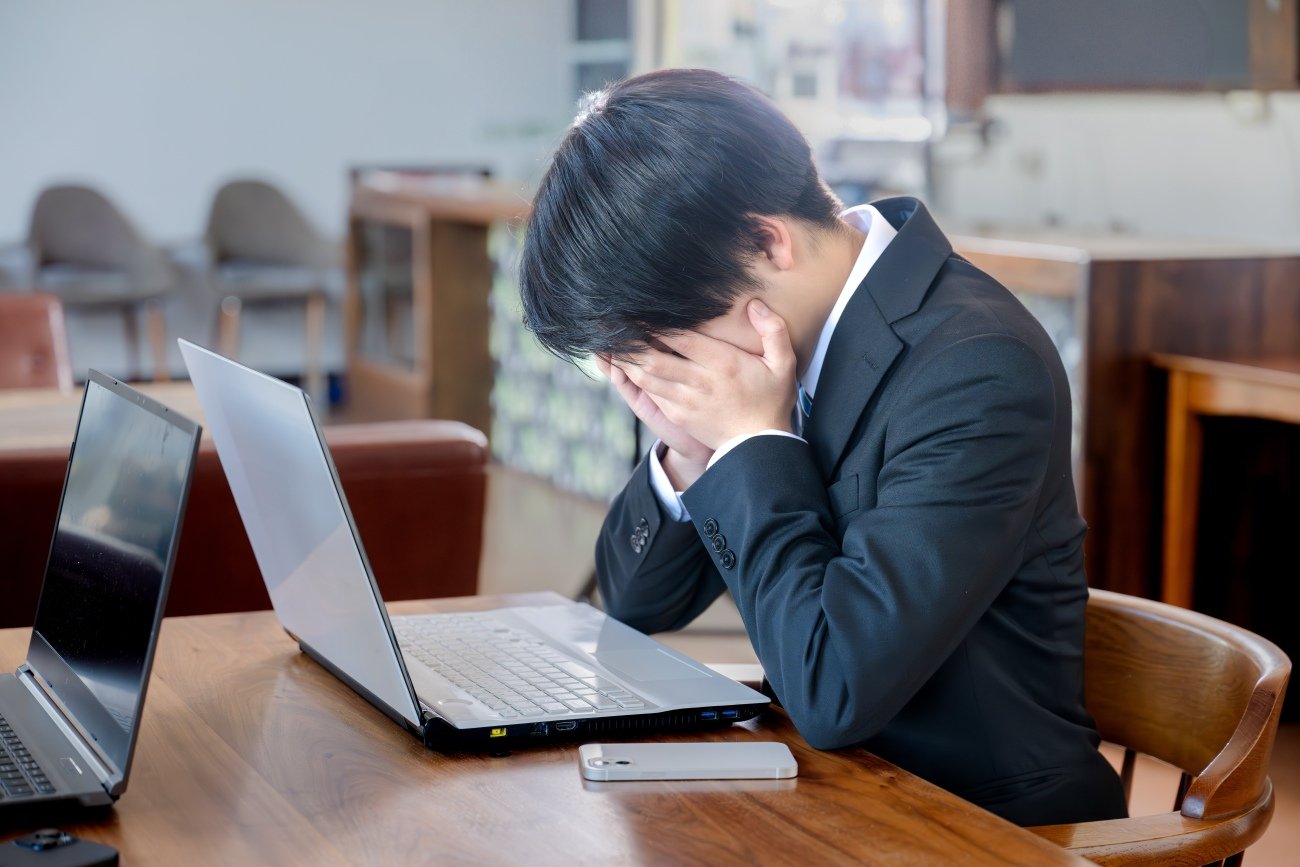 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「お通夜会議」の原因は
“個人のやる気”ではない
──自由に意見を言っていいよと言われても、誰も何も発言しない──。そんな“お通夜会議”が蔓延しています。いったい何が起きているのか……教えてください。
安斎勇樹(以下、安斎) 会議のファシリテーターが「何かいいアイデアない?」「なんでもいいから意見を」と投げかける。でも誰も反応せず、沈黙が続く……。こういう光景は、最近ますます増えていると思います。
ZoomやTeamsなどのミーティングツールで、リーダーや司会をやっている人だけが画面オンでしゃべっていて、他の参加者はカメラオフ・ミュートのまま。真っ暗闇に向かってひとりごとを言っているような状態です。
そうなると、リーダーは「自分は責任感を持って進行しているのに」「企画のたたき台も持ってきてるのに」と思い始める。「最近の若いやつは意見がない」「やる気がない」「アイデア発想力がない」と、会議がうまくいかない理由を、心構えやモチベーションといった内面的な要因に帰属させてしまう。
でも実は、そうじゃないんです。人が主体的になれないのは、環境側の問題なんです。
学校の授業と同じで、儀式的なフォーマットの中で「遠慮なく質問して」と言われても、言えるわけがない。そんな重苦しい空気の中で「なんでも聞いてね」なんて言われても、発言なんてできない。
でも、会議の時間が終われば、けっこうみんなふつうにしゃべっていたりする。つまり、環境さえ変われば、人はもともと主体的に動けるはずなんです。
意見が出る場を「設計」する
安斎 だから、「もっと主体性を出せ」という方向に期待するのではなくて、意見が自然に出てしまうような空気づくり、場づくりをしないといけない。
たとえば「チェックイン」。会議の冒頭でひとことずつ全員が話す時間をとるとか、軽く雑談するとか。いきなり本題に入るんじゃなくて、一度口を開いてから議論に入るだけで、意見の出やすさは全然違います。
あと、「問いかけの仕方」も大事ですね。「なんでもいいからいい意見ない?」という問いかけは、本人としてはハードルを下げているつもりかもしれないけれど、それって真っ白なキャンバスに「なんでもいいからうまい絵を描いて」と言われているのと同じなんですよ。
だから、たとえば「このアイデア、100点満点でいうと何点?」と聞いてみる。60点、70点、80点……それなら誰でも答えられる。
で、「高得点をつけた人はなぜそう思いましたか?」「40点をつけた◯◯さんは、どこが引っかかったんでしょうか?」と聞いてみる。
あるいは、「さらに10点上げるとしたら、何をすればいいと思いますか?」と聞いてみる。
「なんでもいいので改善案を出してください」と問いかけなくても、結果的に改善案が出てくるような問いかけになっているんですよね。
話し合いたいアジェンダに向けて、どう足場をかけていくか──それがファシリテーションの基本的な考え方です。そのためには、最初からふわっとした問いを投げていてはうまくいかないんですね。