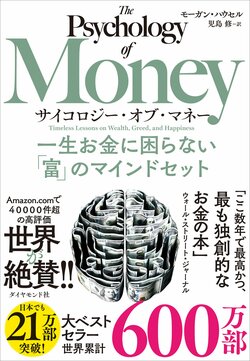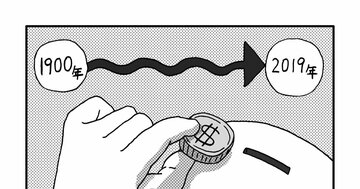2020年秋にアメリカで発売されると、たちまちのうちに大ヒットに。世界中で翻訳され、実に600万部を超える大ベストセラーになったのが、『サイコロジー・オブ・マネー』だ。日本では2021年に翻訳刊行され、“一生お金に困らない「富」のマインドセット”というサブタイトルが付けられている。お金との向き合い方についてハッとさせられる、世界が絶賛した20のマインドセットとは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
専門知識がない普通の人でも、裕福になれる
誰しも資産づくりを成功させたいと思っている。
では、どうすればうまく資産を築けるのか。リスクとはどう向き合えばいいのか。なぜ投資に失敗する人が出てくるのか。投資で本当にやってはいけないことは何か。貯金をしなければいけない理由とは。お金を持つことで、人が本当に求めていることとは……。
お金に対するさまざまな思いに対して、鋭い示唆を次々に与えてくれるのが本書だ。
著者のモーガン・ハウセルは、ベンチャーキャピタルでパートナーを務める金融プロフェッショナルである一方、ウォール・ストリート・ジャーナルなどのメディアに記事を寄稿するコラムニストとしても活躍している。
そんな著者が、お金と人間の関係についての普遍的な教訓をまとめた本書は、世界中で話題になった。
なるほど、そうだったのか、こう考えるといいのか、という驚きのエピソードが次々に続いていく。
著者は冒頭で、この本で何を言いたいのかを伝える。
資産づくりには、マネーに関連した豊富な専門知識が必要なのではないか、と考えている人が少なくないかもしれない。
また、天才的なマネーの才覚がある人が、投資に成功していると考えている人もいるかもしれない。しかし、著者はそうは考えていない。
天才も、感情をコントロールできなければ破産することがある。逆に、金融の専門知識がない普通の人でも、ごく単純な行動を実践すれば裕福になれることがあるというのだ。
それが、実例を挙げて紹介されている。
1人のアメリカ人男性の死が、国際的なニュースになった
2014年、92歳で亡くなったアメリカ人男性の死が、国際的なニュースになった。バーモント州生まれで、家族で高校を卒業したのは彼が初めて。家が貧しく交通費がなかったため、学校には毎日ヒッチハイクをして通っていたという。
彼はガソリンスタンドで接客と自動車整備の仕事を25年間務め、その後は百貨店のJCペニーで清掃員として17年間パートタイムで働いていた。
38歳のときに2LDKの家を1万2000ドルで購入し、生涯そこに住み続けた。50歳で妻を亡くしたが、再婚はしなかった。一番の趣味は薪を割ることだった。まわりの人たちは、彼について特筆すべきことは何もないと口を揃えた。
その名を、ロナルド・ジェームス・リードという。この田舎の地味な清掃員の死が、国際的なニュースになったのには理由がある。
日本円で約12億円もの巨額な資産だ。清掃員だった彼が、いったいなぜこれほどの巨額な資産を手に入れることができたのか。宝くじが当たったわけではない。遺産があったわけでもない。まわりの知人たちは当然、驚いた。
やがて、これほどまでの巨額な資産が残った理由が明らかになる。
清掃員だったリードはただそれだけで、莫大な遺産を寄付する慈善家になったのだ。(P.6)
一方、リードとは何もかもが正反対の人間を、次に著者は紹介する。リードが亡くなる数ヵ月前、話題になったリチャード・フスコーンという男性だ。
ハーバード大学卒。MBA取得。順調にキャリアを歩み、大手金融機関のメリルリンチでエグゼクティブに。大成功を収めて、40代の若さで引退して慈善家になった。
ところが、ほどなくして、フスコーンの人生は絶頂から転落する。多額の借金をして、建坪500坪の屋敷を増築。バスルームが11室、エレベーターが2基、プールが2面、ガレージが7棟あり、月の維持費が9万ドル以上もかかる豪邸になった。
そこに2008年の世界金融危機が発生した。現金に換えにくい流動性の低い資産を保有していたことが災いして、多額の負債を抱えて破産に追い込まれたのだ。言ってみれば、才能あふれた金融のプロがである。
ファイナンスの世界では、「逆転」が起こせる
この対照的な2人を冒頭で紹介したことについて、著者は「リードのようになれ、フスコーンのようになるな、と言いたいのではない(ただし、もちろんそれは悪くないアドバイスではある)」と記している。
著者のメッセージの中心はそこにはない。伝えようとしたのは、「このような逆転はファイナンスの世界にしか起こり得ない」ということだ。
私にはその例が思いつかない。(P.8)
なぜファイナンスの世界では、学位もなく、専門的訓練も受けておらず、経歴も実務経験もなく、人脈もない清掃員のリードが、最高レベルの学歴、専門的知識、人脈をもつトップエリートのフスコーンに負けない成果を出すことができたのか。
それは2つの理由から説明できると著者は記す。
もう1つの理由は(私はこちらのほうがより一般的だと考えている)、経済的な成功は「ハードサイエンス(物理学や数学などの分野)」では得られない、というものだ。(P.9)
経済的な成功をもたらすのは、何を知っているかという知識ではなく、どう振る舞うかこそが問題なのだ。だから冒頭の「頭の良さより、行動が大切だ」なのである。
そして、どう振る舞うかが重要な「ソフトスキル」を著者は「サイコロジー・オブ・マネー(お金の心理学)」と呼んだ。複雑で測定が難しい人間の心理や行動が大きく関わっているからである。
それは、「半年分の生活資金を用意すべき」「給料の10%を貯蓄すべき」などのアドバイスが溢れるパーソナル・ファイナンスの世界にも当てはまる。(P.9-10)
だが、「何をすべきかを知っていることと、その人が実際に取る行動はまったくの別物」だ。
あらゆるメディアで、これだけ金融知識が得られる状況になったのに、果たして人々の投資の腕は上がったのか。
問題はファイナンスにあるのではない。人間そのものにある。だから、人間そのもの(人間心理)を学ぶ必要があるのだ。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。