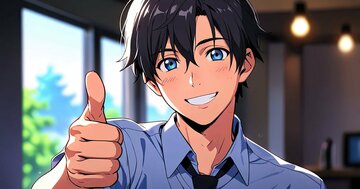好決算でも買ってはいけない!“高値づかみ”を防ぐためのチェックポイント
株式投資の世界では、「決算後に株価が大きく動く銘柄にどう乗るか」が勝負を分けることがあります。その波に“後乗り”しても、しっかり利益を狙える――それが『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社)の著者・kenmo氏が実践する投資法の1つ「決算モメンタム投資」。会社員として働きながら、わずか5年で資産を1億円に増やしたkenmo氏。IR資料や決算短信をコツコツ読み込み、業績と株価チャートを冷静に見極めながら、着実に資産を積み上げてきた。第3回のインタビューでは、「決算モメンタム投資」の中身、銘柄選びの視点、エントリー&エグジットの判断軸を一問一答形式で深掘りします。
 イラスト:ひらのんさ
イラスト:ひらのんさ
決算発表後に“後乗り”で利益を狙う投資法とは?
Q:「決算モメンタム投資」とは、どんな投資法なのでしょうか?
A:ひと言で言えば、「決算発表をきっかけにして株価が上昇し始めた銘柄に、後から乗っていく」投資法です。
決算モメンタムの本質は、「後から買いたい人が出てくるか」ということ。具体的には「このあとさらに良いニュースが出てきそう(好決算や増配など)」、そして「投資家の買い意欲が十分か(手元にキャッシュのある投資家が多そうか)」にあります。
株価って、決算を起点に上昇を始めることが結構多いんですよ。株価が上がっていくためには、その企業を自分だけが良いと思っているだけじゃ駄目で、多くの投資家がその株を良いな、買いたいなと思う「きっかけ」が必要です。決算発表がその「きっかけ」となるケースが多くあるんです。
決算の内容が良いと、多くの投資家が一斉にその銘柄に群がります。一過性の内容だとすぐに売られてしまうこともありますが、「今後さらに良くなりそうだ」と投資家が期待を持てる銘柄は、後から買ってくれる投資家がどんどん出てくるので、さらに上昇トレンドを継続することがあります。
決算モメンタム投資とは、その兆しを敏感に察知し、上昇トレンドを作りそうな銘柄にいち早く飛び乗る戦略です。
“未来のヒント”は決算短信とIR資料にある
Q:「今後さらに良くなりそうだ」とはどこから読み取るのですか?
A:これまで100点の決算を出していた会社が100点の決算を出すのでは駄目なんです。確かに好決算なのですが、すでにその会社が良いということが皆分かっていますので、そこまで大きなサプライズではありません。
30点の決算を出していた会社が50点の決算を出して、さらに今後70点くらいまではいくんじゃないか、そういう銘柄のほうがチャンスがあります。
たとえば、「売上総利益率」が改善しているとか、特定のセグメントの「売上高」が急速に伸びているとか、そういった変化の兆しにいち早く気付いてその背景情報をチェックするような感じです。
IR資料も必ず読みますし、IR資料だけでは分からないところは企業のIRに問い合わせもします。
決算モメンタム投資が機能しやすいタイミングを狙え
Q:「投資家の買い意欲が十分か」という点も考慮するのですか?
A:仮に企業が好決算を出したとしても、多くの投資家が株をパンパンにもっている状態では、投資家の買い余力がないため後から買ってくる人がいません。むしろ、好決算であっても買い余力をつくるために売られてしまう銘柄まで出てきます。
投資家の買い意欲が十分な状況というので、分かりやすいのは全体相場の暴落直後です。
2020年3月のコロナショックや2024年8月の植田日銀ショック、2025年4月のトランプ関税ショックなど、全体相場の暴落直後は、リスク回避のために手元にキャッシュを増やしていた投資家も多いため、好決算銘柄に買いが入りやすくなる傾向にあります。
業績×株価チャート=モメンタムの兆しを見抜く
Q:業績だけでなく、株価チャートも重視されるんですよね?
A:中長期的に株価が右肩下がりの銘柄だと、高値づかみをしている投資家が多いため思うようにモメンタムがつかないことがあります。
株価の“水準訂正”がまだ済んでいなく売りたい人たちがまだ多い可能性があると判断し、決算モメンタム投資の対象からは外します。
また、株価が1~2年ずっと右肩上がりとなっている銘柄も、既に買っている投資家が多いので決算モメンタム投資が機能しにくくなります。
株価がしばらく横ばいか、緩やかな上昇基調にある銘柄を選定することが多いです。
決算モメンタム投資をするなら
「決算スケジュール」は必ずチェック
Q:具体的な銘柄選定は、どのようにしていますか?
A:1か月前くらいから決算スケジュールをチェックし、気になる銘柄を「会社四季報」やIR動画、各種レポートなどで予習しておきます。
この決算が出たらこうしようといったシミュレーションまでできるとベストですが、すべての銘柄では無理なので、その時々のテーマや時流に乗った銘柄等を重点的にフォローしていきます。
場合によっては決算前に少しエントリーすることもあります。決算シーズンが始まったら、毎日PTS(私設取引システム)ランキングや決算内容をチェックし、決算後の反応を見つつ戦略を立てていきます。
予習していたセクターとはまったく別のセクターの決算反応が良いこともあるので、決算序盤戦の物色対象を見て後半戦の戦略を立てるなど、臨機応変な対応が必要です。
また、前半戦で決算後の反応が思わしくないと見たら、後半戦の決算モメンタム投資を控えるといった判断もあります。