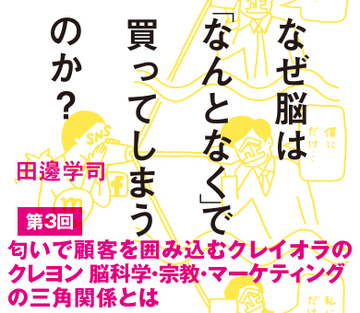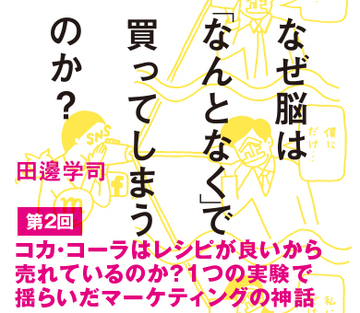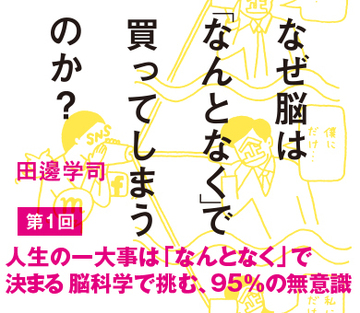各企業は、他社を追い越し、追い抜くために、マーケティングリサーチに勤しんでいる。にもかかわらず、店頭には似たような商品ばかりが並び、消費者は違いがあることすら気づいていないこともあるだろう。
いま、脳科学とマーケティングが融合した「ニューロマーケティング」が注目を浴びている。アンケートやグループ・インタビューからは読み取れない、言葉にできない消費者の“ホンネ”とは。「なんとなく」の正体に脳科学で迫る。
「なんとなく」で命も捧げてしまう脳の仕組み
人間は言葉を発明し、文法を持ち、発話を文字に置き換え、脳に言語の発話と解読を司る領域を構築した。これが人間を人間たらしめる文明の始まりである。言葉を使って様々な抽象的な感情や考えをありありと知覚できるようになった。
泡があふれそうなビールグラスの縁に、唇がすばやく吸い付けられる。熱いヤカンに触れると指が耳たぶへ飛んで行く。目の前の現実に対して、行動で対処しようというのは人間も動物も同じだ。しかし、人間はより抽象的で曖昧な、触れることもできないものに膨大エネルギーや時間を使ったり、ときに命をかけることすらある。
「恋愛」という概念で食事がのどを通らなくなる。「エコ」という概念で巨大な産業が動き出す。また、「お金」は抽象的概念の権化と言ってもよく、人間はこの紙切れに生死をかけてしまう。
それではいったい、何がこうした抽象的な概念をリアリティに変換しているのだろうか。その鍵を握るのが、「メタファー(喩え)」である。
「メタファー」というと、コピーライターや小説家のような文学的センスを持つ限られた人たちの専売特許だと思い浮かべがちだが、多くの言語学者や心理学者によると、メタファーとは人間の認知の仕組みそのものであり、メタファーなくしては何も思考できないと言われるくらい、人間の基本システムの一部として機能しているものと考えられている。
「輪になって踊る」、日常会話に紛れ込むメタファー
脳の中でメタファーを司ると言われるのは「角回」という部位である。「下頭頂葉」という部位に位置し、触覚・聴覚・視覚の交差的な役割を担う。また、言語を司る部位にも近い。つまり、身体感覚と言語を結びつけるこの部位がメタファーの理解や活用を担っているのである。
ちなみに、この部位を損傷した人は簡単なメタファーでも理解に苦しむという。たとえば、校庭に集まっている小学生に「輪になって踊ろう」と指示すれば、難なく丸い円陣が組まれるだろう。しかし、一部の自閉症の人には、何が「輪」なのかが今ひとつぴんとこない、といったことが起こるそうだ。
「輪」の定義の厳密性から考えれば、人間は輪そのものになることはできない。これを「複数の人が相互の配置関係によって輪のような“状態”をつくる」というところまでさかのぼって考え、ようやく「そうか、『輪になる』という表現自体が喩えになっていたのか」と気づくくらい、私たちは生活のなかで当たり前にメタファーを使用している。
メタファーは、乳幼児の段階から活用して使い始めている。はじめは、積み木や粘土などを「マンマ(食事)」「ブーブ(車)」など、モノに見立てた発話が爆発的に増える。あるモノを“何か”に見立てる喩えはその後減少するが、メタファーの質は、そうした直接的な見立てから抽象的な例えに移行し、4歳半ばを境に、より抽象的なメタファーの使用が逆転して増えてくるという。
「たとえば四歳児のクラスでは何でもできる強い父を『スーパーマンみたいや』、色ぬりしたあとのポスターカラーを混ぜた水を『悪魔のジュースや』、色の重ね合わせの妙を『あっ、この色と色結婚しとる』」
(『月刊言語』2002年7月号、岩田純一「乳幼児の発達とメタファー」より)
人間は2歳から様々な世界の「見立て」を始め、それをテンプレートにして、より抽象的なものを喩えて咀嚼していく。やがては、喩えの抽象度を増しながら、いちいち喩えを考えなくてもいいようにイディオムに内蔵されていき、より複雑な状況や感情、概念を即座に自分の中に取り入れて伝えるようになる。こうなると、もはや自分が発する言葉の中にメタファーがふんだんに盛り込まれていることすら気づかないようになってくる。