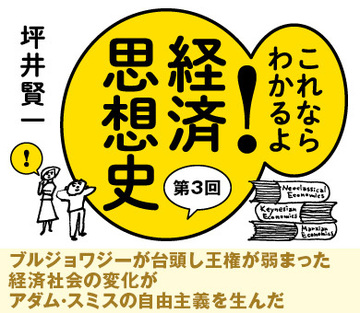さて今回からは、マルクス経済学とほぼ同時期にうまれた新古典派経済学について紹介していきます。新古典派の皮切りといえる限界効用理論を説明する前に、ドイツで主流だった歴史学派から解説していきます。
古典派経済学では、放っておけば需要と供給が一致する市場の均衡点で最適な価格と数量が決まる、と考えるのでしたね。さらに、最初に販売するときの価値(価格)は、投下する労働量で決定される、とする労働価値説はマルクス経済学でも踏襲していました。
しかし、ベーム=バヴェルクが指摘していたように、熟練工と未熟練工では同じ労働時間でも価値は違うはずです。そこで、発想をまったく変えて、買う側(需要側)の欲望の度合いが価値を決めるのではないか、と考える経済学者が出てきました。同時に、数量を扱う経済学にとっては数学が重要だとする経済学者も増えてきます。
こうして、人間の欲望を数学で理論化しようという研究が始まります。これが新古典派経済学の出発点です。
経済学史では、新古典派経済学の皮切りは1871年、限界効用理論(後述)の登場です。なんと3ヵ国の3人の経済学者からほぼ同時に同じ理論が発表されます。これ以降に発展した新古典派経済学が、現代の主流経済学となっています。
舞台は19世紀末、英国、ロシア、フランス、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国の利害が衝突し、またそれぞれの帝国の内部では被支配地域で民族独立運動や社会主義運動が激化していた動乱の時代です。マルクスがロンドンで『資本論』第1巻を出版したころであり、英国の代表的な古典派経済学者であるJ・S・ミルが自伝を書いた時期でもある。
古典派経済学は欧米の大学で広く教えられていましたが、ドイツだけは状況が違っていました。
人口が多く領域も広大なドイツ圏では、1871年のドイツ帝国の成立前後の主流は古典派ではなく、ドイツ歴史学派の経済学でした。歴史学派はベルリン大学など、有力な大学で強い影響力を持っていました。新古典派を説明する前に、歴史学派を避けて通れないので、ここから話を始めます。
マルクス派のヒルファーディンクと新古典派のベーム=バヴェルクの論争を先んじて紹介しましたね。19世紀末から20世紀初頭のドイツ圏では歴史学派と新古典派が並立し、マルクス経済学も力をもってきました。英国やフランスより複雑だったのです。
受講者 ドイツ圏とは、ドイツのプロイセンやバイエルンといった多くの王国と、ハプスブルク家が支配するオーストリア帝国のことでしょうか。どうしてドイツだけ古典派経済学やマルクス経済学ではなく、歴史学派が主流になったのですか。
ドイツは国民国家として統一されるのが遅かったからです。幕藩体制から明治維新を経て日本が近代国家となった時期も同じです。