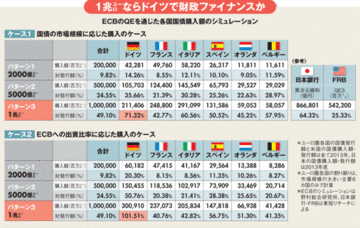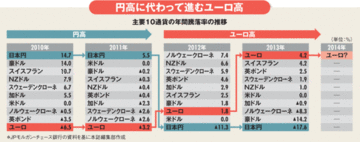21世紀は中国の世紀であり、米国は落日の大国と言われる。しかし、果たしてそうなのだろうか。米スタンフォード大学の古参経済学者、ジェームス・ハウエル教授は、2006年のインタビューで、過去2000年を振り返りながら、東西再逆転が一朝一夕にはいかない歴史的根拠を語った。
現存する統計資料をかき集めて、過去2000年の世界経済の勢力図を俯瞰したとする。エコノミストならずとも、4つのグローバルパワーの栄枯盛衰に目を奪われることだろう。その4強とは、中国、インド、欧州、そして米国である。
OECDのレポートによれば、中国とインドは紀元元年から19世紀初頭まではそれぞれ世界経済の2~3割強を占める二大経済大国だった。ところが大航海時代と産業革命を経て急速に力をつけた欧州に追い落とされ、その後凋落。復調著しい今でも1割前後を占めるにとどまっている(購買力平価ベースで2003年は中国が約13%、インドが約6%)。そして、欧州の後を襲ったのは、20世紀に急成長を遂げた米国。現在はこの欧米に日本を加えた、旧西側先進国で世界経済の5割以上を占めている。
前置きがやや長くなったが、私がここで指摘したいことは明快だ。今後の世界経済の勢力図を占ううえでの長期的視野の重要性である。
未来の経済大国といわれる中国とインドが2000年間の曲線(GDPの世界シェア推移)を見る限り、まだ低位を這(は)っていることは何を示すのか。落日の大国といわれてはいるが、米国の上昇曲線を欧州の過去の伸びと見比べると、まだ上に向かいそうに見えるのは錯覚なのか。むろん過去は過去。トレンドは非連続かもしれない。だが、少なくとも東西再逆転が一朝一夕にはいかないことを2000年の歴史は物語っている。
俗説の疑問点は、別の視点からも見えてくる。人口統計だ。