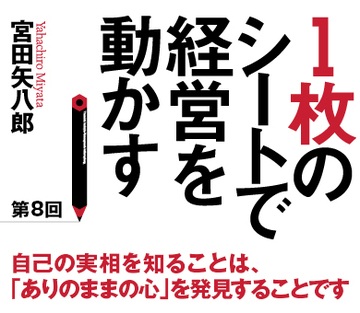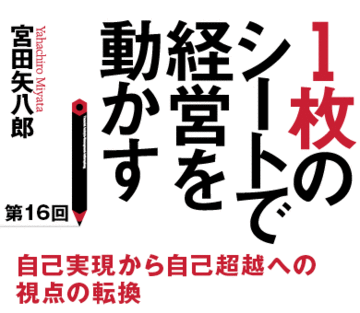自己の皮むきをやっていったら、自己の意識はあっても自己の実体には出会えなかった。これを釈迦は「自己不在」と表現した(「『アートマン』という迷いは存在しない」『感興の言葉 ウダーナヴァルガ』15章4)。では、そこにあったものは何か? 「不生なるもの」「作られざるもの」だった。これが第8回の内容でした。その続きです。
もともと心を正確に把握することなど無理なのですが、せめて近い処まで行きたいと思います。
私の理解では、これまでにも述べて来ましたように、人間には「心」がない、あるいは、人間は頭脳ロボット、知性動物とでも表現すべき状態にあって、せいぜい言えて、「心の器」しかないというものです。もちろん、怒りや悲しみや欲望といった本能的感情はありますが、私の視点からは、これは「心もどき」状態、「疑似心」とでも言うべき現象です。
そこで、人間には「心の器」しかないというのが現実の状態なら、どのような状態が本来の姿なのかということになります。結論を先取りして言えば、心は人間が一定の状態のもとに置かれたとき正常に機能する。言い換えれば、自己超越の状況下で初めて,心は正常に機能するということです。これを「境涯の変化」と表現したいと思います。
【本当の心の発見1】
日本の曹洞宗の開祖、道元(1200~1253)に次のような言葉があります。中国での修行を振り返って、道元はこう言うのです。
「山僧叢林を歴ること多からず、只是等閑に天童禅師に見えて、当下に眼横鼻直なることを認得して、人に瞞かれず、便乃空手にして郷に還る、所以に一毫も仏法なし」(『道元禅師語録』講談社学術文庫、1990)。
要するに、中国で多くの善知識やお寺を訪ねたわけではなく、ただ天童如浄禅師にお会いしてすぐに眼は横に鼻はまっすぐについているという、当たり前の世界を悟った。したがって、「空手還郷」し、仏法なるものは一つも持ち帰らなかった。そのような意味です。
別に、「柔軟心」を得て帰ったという言葉もあります(『宝慶記』31)。道元においては、わが心が当たり前の処に落ち着いた、そこで安心を得た、それこそが仏法そのものだというのです。
心が正しい位置に置かれれば、人間は誰に教えられなくてもその事実を知る。自我の囚われを脱した心には、同じ景色が映っても以前とは天地の差であると。そこに至るプロセスの核心が解脱ですが、道元はこれを「身心脱落」と表現しました。
【本当の心の発見2】
さて、本書で「ありのままの心」と表現した、懺悔という心の動き――後悔の念とともに本当の自分が明らかに自覚された状態――はどうとらえれば良いのでしょう。
これはもともと人間の理解を超えた経験ではあるのですが、比喩として言えば、「心の器」の中に「本当の心」が「入って」、それが「自分の心」として精神現象――悲しみ、苦しみ、後悔、謝罪、回心等――を体験する。
読者におかれては、既に第19回 イエスの贖罪 を読んでおられるので、この「本当の心」を「聖霊」――神の心――と言い換えれば、思い出していただけると思います。この経験をパウロは次のような表現で述べています。「御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら(中略)、御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのためにとりなしてくださいます」(ローマ人への手紙8-23~26)。
懺悔の中で来し方の諸々を反省し、自分の根源悪――盲目的な生存本能としての自我――が自覚され、明るみに出され、イエスの贖罪に合わせられて断罪されるとき、自我の根切りが行われるのです。
「問題」――罪の醜さが見え――、「解答」――救いの構造が見える――。両者の重さがつり合って、一人の人間の心の視野の中で両者が対置されたとき、そこに「全部が見えた!」という現象が起きる。それが「大疑団」解消の大きなステップです。
【本当の心の発見3】
繰り返しになりますが、人の心は本来、神秘そのもので、これを正確に把握できる人はいないのです。しかし、同時に心の問題の解決ほど重要なものは世の中にはありません。
なぜなら、世の中で最も恐ろしいもの、恐るべきものは心だからです。人の心は百年でも千年でも万年でも、永遠に固着する(凝り固まる)からです。正確には理解できないのですが、心には永遠という性質があるように思われます。確かに、心には過去も未来もなく、永遠の「今」しかない。苦しみや悲しみ、怒りや拒絶の心が固着すれば、それが地獄です。本人も苦しみ、その感情が向けられた人間も永遠に苦しむ。心がすべてから切り離され、何の助けもなく、苦しみ続ける。その悲惨さを想像してください。
これをどのように溶解させ、大安心を得させるかという人類最大の課題に答えを与えたのがイエスの贖罪であり、その中心にあるのが懺悔――神の懺悔に合わせて、人の心が懺悔する――であり、その奥にあるのが信仰なのです。このような事情のゆえに、キリスト教では「救済」(注1)というのです。
因縁果。苦しみという結果をもたらす因縁という借金の返済、それをどう果たすか? 苦しみからの解放こそが釈迦の原点でしたが、因縁解消の条件を釈迦は「就着を捨て去る」としか言っていません。しかし、その結果、涅槃・ニルヴァーナ――安らぎ――を得たと(「苦しみは執著の条件から生ずるものである。執著の条件がすべて滅びたならば、苦しみの起こることはない」『感興の言葉 ウダーナヴァルガ』32章37)。結局、釈迦は求道と修行の結果として、我知らずそのような境涯に押し上げられたのだと受け止めるしかありません(注2)。
結論です。人間にとって当たり前のはずの心が、実はまったく人間の自由にならないもので、人間にとっては神秘そのものなのです。
本当の心とは「神の心」――キリスト教の表現では「聖霊」――が「器としての心」に入り、懺悔と信仰によってへばり付き固着する因縁を切り離して、心が本来の姿、本来のあり方に落ち着いた時、その状態を「本当の心」、自己超越の境涯というのです。
1.第19回の注3で述べたように、イエスの贖罪――福音――はいわば多面体で、人間の様々な要求に対応するいくつかの局面を持っています。キリストを見上げつつ生きて人生経験の中で徐々に人格陶冶されるというような場合は良いが、時間的にも、能力的にも、罪の深刻さにおいても、とてもそれでは間に合わぬというような場合、イエスの身代わりの死という神の愛を信じるなら、ただそれだけの最低の条件で救おうというのが「救済の福音」なのです。
これはいわば緊急避難的な救済措置で、そこには限界ギリギリまで譲歩しても霊魂を救おうという神の愛が見て取れます。
わがため十字架の/患難(なや)みと恥を
受けさせ給ひし/わが主の愛よ
血潮の功に/滅びの火より
逃れしわが身は/歌わざらめや(『聖歌』280)
2.禅宗二祖、慧可断臂の伝承を思い出します。心の苦しみから何とか逃れたいと師事を申し出る慧可に対して、達磨はその苦しむ心を持ってこいと言います。苦しみは痛みを伴う現実の経験ですが、持って来いと言われても、持ち出して人の前に置けるようなものではありません。彼は「心不可得」(心を捉えることはできません)と達磨に言うと、達磨は「汝がために安心し了んぬ」(私は、お前のために安心の境涯を体得しており、それを伝えることが出来る)と言うのです。
「境涯の変化」こそが自己超越で、それは人から人によってのみ伝えられてゆくもののようです。