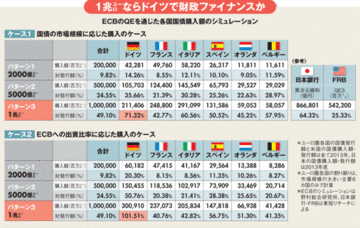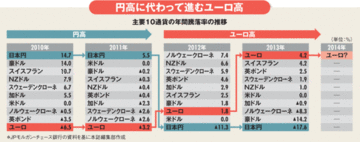米政府の惜しみない支援によって復活を遂げていた世界金融の中心地、ウォール街。しかしオバマ大統領の隠し球、ポール・ボルカーが20年ぶりに表舞台に戻ってきたことで、規制強化という荒波にのみ込まれ、大きな変革を迫られている。はたして米国金融は変われるのか。「週刊ダイヤモンド」2010年4月17日号の特集「ウォール街 復活の光と影」から、徹底した現地取材に基づく主要記事群を4回に分けて再掲載する。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 池田光史、田島靖久)
※本文及び図表類は2010年4月17日号の本誌掲載時のまま再掲載しています。
「住宅や高級車などの高額商品を買わないように」「長期旅行に行かないように」「休暇の行き先を上司に伝えるように」──。
昨年末のボーナス支給日、米金融最大手の一つ、ゴールドマン・サックスの社員たちが会社から受け取ったメールには、トップのメッセージや業績データに続いて、こんな“注文”がずらりと並んでいた。
当時のゴールドマンは、社員の高額報酬をめぐって、世論の厳しい批判にさらされていた。賞与の原資が200億ドル(約1兆8000億円)に達し、1人平均80万ドル(約7200万円)近くになると伝えられていたためだ。
日本と違って、確定申告制度の米国は納税者意識が高く、税金の使い道に関してはとかく敏感。すでに全額返済していたものの、100億ドルもの公的資金という名の税金を注入してもらいながら、それで稼いで多額のボーナスをもらうなんて──。日に日に高まるそうした声を背景に、目立つ行為は慎むように呼びかけていたのだ。
ゴールドマンのトップがこうした心配をしなければならないくらい、世界金融の中心地、ニューヨークのウォール街は、金融危機から1年半あまりで完全に息を吹き返したかのようだ。
一時は、五つあった米大手投資銀行が合従連衡(がっしょうれんこう)のすえ、ゴールドマンとモルガン・スタンレーの2社となり、それも銀行持ち株会社に転換したことで、「ウォール街の終焉」「投資銀行の死」などと呼ばれたりした。
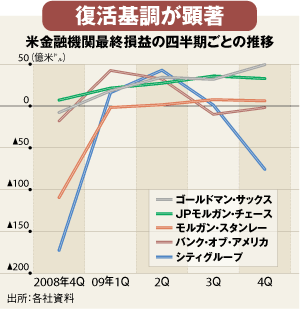

だが、米政府と金融当局が公的資金注入など、持ちうる政策を総動員して事態の収拾に当たった結果、金融機関は有利な条件を最大限利用して業績を回復させた。
たとえばゴールドマンは、2009年4~6月期、10~12月期と相次いで過去最高益記録を塗り替え、通期の最終損益は前年比497.4%と、急回復ぶりを見せつけた。
それ以外も、一部、シティグループのようにもたついているところもあるが、おおむね増収増益を果たし、回復基調は鮮明。ダウ平均株価も1万ドル台を回復して底堅く推移しており、ウォール街では「金融危機は過去のもの」(投資銀行幹部)となっている(右のグラフ参照)。