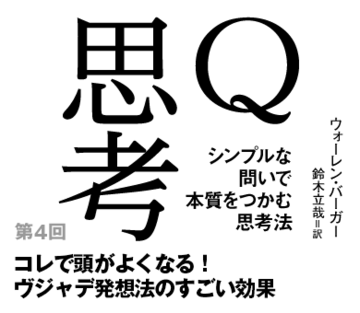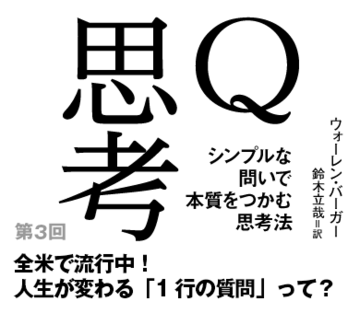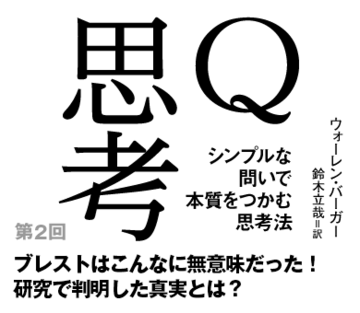「では、どうすべきか」は言えなくていい
挑戦的質問には、その場の雰囲気を壊す要素がある。
「それは、争いのもとになりやすいんです」とハーバード大学で学生イノベーション・プログラムを指導しているポール・ボッチノは指摘する。ボッチノのプログラムは、最も聡明で創造的な大学生たちに人気があるが、彼らでさえ、指示されたことの多くを一つの質問も発することなく受け入れる傾向があるという。ボッチノの主な仕事の一つは、学生たちに「現職の者たちは現状維持に関心があるということを理解せよ」と説くことだ。「優れた質問をするには、『そうである必要はない』と言える能力を持たなければならないのです」
これは多くの学校で教えられている「どんな疑問や質問にも正しい答えがあり、それを受け入れたほうが(そして覚えたほうが)よい」という姿勢に反するものだ。デボラ・マイヤーが疑問を抱くことを奨励するセントラルパーク・イーストの学校を設立したころ、生徒たちに教えた最初の「思考の習慣」は、「何が『真』かをどうやって知るのか?」を問い続けることだった。マイヤーは子どもたちが教わったこと、言われたことすべてに疑問を抱いてほしいと思っていた。
コメディアンのジョージ・カーリンは(娘のケリーによると)死ぬまで権威を信じていなかった。彼の保護者に対する助言は、「子どもたちに読書だけを教えてはいけません。読んだものを疑うよう教えてください。あらゆるものに疑問を抱くよう指導してください」というものだった。
長年の訓練によって「専門家から与えられた答え」を受け入れるべきだという考え方が染みついてしまっている人たちが専門家に疑問を抱くのに慣れる唯一の方法は、質問を何度も何度も繰り返すことだとボッチノは言う。
挑戦的質問をするときに慣れなければならないことの一つは、「どうしてあなたは、自分が専門家よりものを知っていると思うんだね?」という典型的な反論を受けることだ(答えは、「たしかに自分のほうが知っていることは少ない。だがそのほうがいいときもある」だ)。
挑戦的質問をする人が受けるもう一つの反論は、「わかった、天才君。では、どうすべきだというのかね?」というものだ。この問いには「これまでのやり方に異議を唱えるのであれば、その人は対案を出すべきだ」という発想が隠れている。
けれども、仮にどうすればいいかを知らなかったとしても、「なぜ?」「もし〜だったら?」という質問をすることは重要である。優れた対案を得るには時間と労力がかかるかもしれないが、何にせよどこかの時点で始めなければならない。そして往々にして現状に対する疑問や質問がその出発点になるのだ。
(本連載は、書籍『Q思考――シンプルな問いで本質をつかむ思考法』より引用しています)