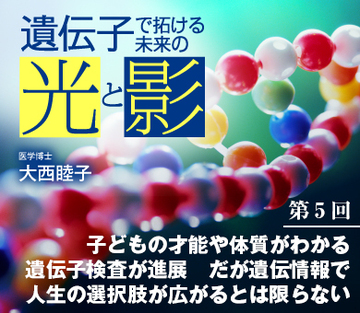記事検索
「数学」の検索結果:2361-2380/2844件
第12回
【0歳からの赤ちゃん教育5】歩きはじめると、真の知能が芽ばえる<第5期・二足歩行期――歩きはじめるころ以降>
話題沸騰の注目の新刊『赤ちゃん教育――頭のいい子は歩くまでに決まる』。著者の「脳科学の権威」久保田競博士と、「脳科学おばあちゃん」久保田カヨ子先生に、第5期【二足歩行期】の骨子を紹介してもらおう。
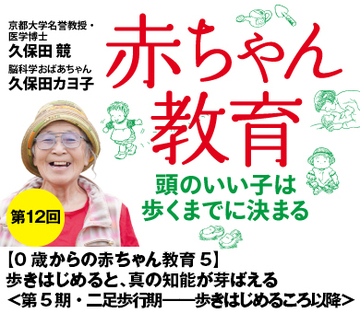
第79回
役員報酬が10億円を突破!カリスマ経営者の経営哲学と人生観
今回ご紹介する『ルネッサンス――再生への挑戦』には、今季決算で10億円を超える役員報酬を受け取ったカルロス・ゴーン氏の半生が事細かく書かれています。その内容を少しお見せしましょう。
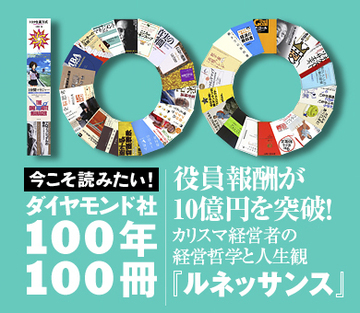
第7回
ドイツ圏、英国、フランスでほぼ同時に、人の欲望を数値化しようと新古典派経済学が出発
さて今回からは、マルクス経済学とほぼ同時期にうまれた新古典派経済学について紹介していきます。新古典派の皮切りといえる限界効用理論を説明する前に、ドイツで主流だった歴史学派から解説していきます。
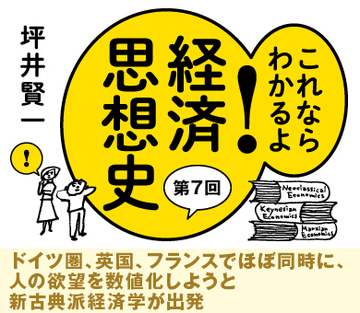
第21回
予防医学としての遺伝子検査については、すでに活発に議論されてきているが、その陰で流行の兆しを見せている別の分野の遺伝子検査がある。能力特性を判定する遺伝子検査がそれである。

第78回
ビットコインは広まるか?仮想通貨の実態を多角的に論じた良書
今回ご紹介する『仮想通貨革命』を読めば、仮想通貨の仕組みから意義まで深く理解することができます。その中身をちょっとだけご紹介しましょう。
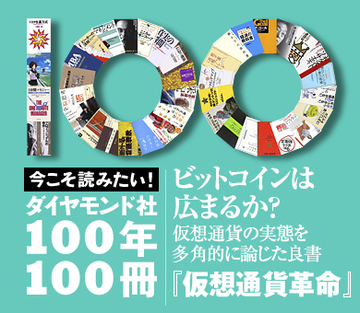
中学入試偏差値が低く、入学しやすくても、6年後の大学合格実績は高い「お得な中高一貫校」のランキング。それを基に、教育がしっかりした学校を紹介する。

日本は、その科学技術力でこれまでの経済成長を支えてきた。そのために必要な逸材の育成を、国や経済界は大学に求めている。その筆頭は東京大学で、創設以来、国の根幹の担い手輩出を求められてきた。今年4月に就任した新総長に、人材育成策やそのための環境整備など、現在の課題の解決策を中心に聞いた。

第4回
会社を縛る「共通のものさし」が、無責任と思考停止を招く
鎌倉投信・新井和宏氏とライフネット生命・出口治明氏。フィールドは違えど共に金融の常識を変えてきた2人の特別対談! 指標、基準を厳格化していくことで無責任・思考停止社会が生まれる――2人の洞察が冴えわたる最終回。
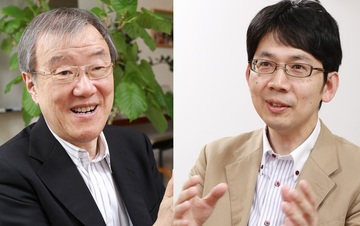
第3回
ブルジョワジーが台頭し王権が弱まった経済社会の変化がアダム・スミスの自由主義を生んだ
前回まで、基本となる3つの経済思想と、それに対応する政治思想について整理してきました。今回からはいよいよ、個々の経済思想の説明に入っていきましょう。まずは、経済学のはじまりともいえる「古典派経済学」からです。
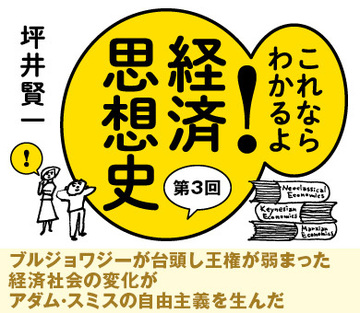
第8回
『伝え方が9割』は子を持つ親にこそ読んでほしい【佐々木圭一×坪田信貴】(後編)
●万部突破のベストセラー『伝え方が9割』の著者であり、第2弾である『伝え方が9割(2)』も好調の佐々木圭一氏と、著書『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』を映画化した『ビリギャル』が大ヒット中の坪田信貴さんとの対談が、1年ぶりに実現しました。後半戦は、佐々木氏の新刊『伝え方が9割(2)』についてです。
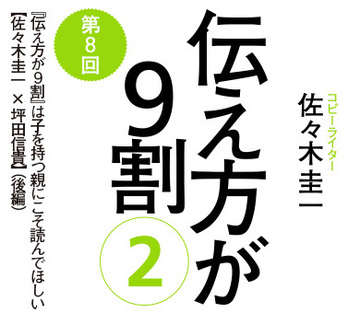
第1回
今も昔も基本となっている3つの経済思想と3つの政治思想とは?
経済思想史として、どうして経済学が誕生し、いろいろな理論が登場しては議論を巻き起こして次々に変化していくのかという背景を知ると、現代の経済への理解も深まります。まずは「経済学」って何なのか?という話題から経済思想史の授業を始めます!

デジタルを用いて表現の可能性を追求するチームラボ。代表の猪子寿之氏は、メディアの未来をどのように見ているのか。話はインターネットの可能性から知の本質までに及んだ。『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』7月号でのインタビュー記事から抜粋してお届けする。

時代の変化とともに、中学受験を取り巻く状況も年々変化していく。そこで、中学受験のエキスパートである二人が、学校を取り巻く最新のニュースに注目。大学入試改革がもたらす影響と、私立中高一貫校の教育の魅力を紹介する。
![[スペシャル対談] 森上展安×中曽根陽子大学入試改革と私学教育の魅力](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/1/8/360wm/img_1881fa2c61c91c5997023887c1ac0928337429.jpg)
第113講
本当の答えは外から来るのではなく、自分自身を見つめることで得られる…といった経験はないでしょうか?SF小説、リーマン予想、電波の例から得られることを挙げてみます。
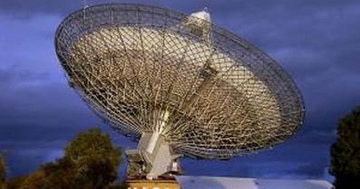
第3回
もしあなたが海外でMBAを取得し、外資系金融機関に勤務したとしたら次のキャリアにはどんな選択をするだろうか。今回紹介する長銀OBの近藤健志さんが選んだのは、意外なことに、中高一貫校の英語教師だった。

第17回
【特別対談】日本の一流商社の名前が通用しないMBAで気づかされた世界の多様性
ハーバード大学卒業後、マッキンゼー、BIS、OECD等を経て、現在は京都大学の教壇に立つ河合江理子氏と、ボストン・コンサルティング・グループ、ゴールドマンサックス証券等を経て、スター・マイカ代表取締役会長を務める水永政志氏の対談。これからの時代に求められる人材像などが語られた。

第5回(最終回)
日系企業が人事データの活用を進めていくために必要な要件は何か。今回は、効果的な分析テーマ選定のためのヒントと、分析者自身に求められる素養、教育体制について解説する。

この春、進学や進級祝いで子どもにスマホを買い与えた保護者も多いかもしれない。彼らの多くがハマっているのが、無料アプリ「LINE」だが、このトレンドに対して不安を指摘する声も多い。いったい子どもたちは、LINEで何をしているのか。

第9回
公務員試験必勝学習法(1)学習スケジュールの立て方 その1
公務員講座など資格試験の専門家にして弁護士の豊泉裕隆が、公務員への就職・転職を目指す人のために、役立つ情報を提供する連載の第9回。今回は勉強する科目の選択の話。
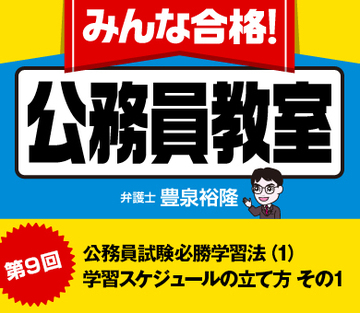
第5回
子どもの才能や体質がわかる遺伝子検査が進展 だが遺伝情報で人生の選択肢が広がるとは限らない
医療領域ではない、子どもの資質を見極めるための遺伝子検査も発展しつつあります。本当にそうした検査が必要なのか? 特に子ども向けの非医療領域の遺伝子検査リスクについて考えていきます。