記事検索
「数学」の検索結果:1741-1760/2851件
「女性は数字に弱い」「高齢者は記憶力がわるい」「日本人はアフリカ系の人に比べて身体能力で劣っている」。わたしたちはしばしば過度の一般化を行い、特定のステレオタイプをとおして周囲の人を眺めてしまう。そして、そうしたステレオタイプがときとして深刻な偏見や差別を生み出してしまうことは、多くの人が知っているとおりである。

第13回
日本の傑作コンテンツを世界に売りたい森岡毅が語る刀起業の真実(3)
USJ復活の立役者として知られる森岡毅氏が2017年に始動した「株式会社 刀」の動きが、このところ活発になっている。同社の取り組みは、丸亀製麺やネスタリゾート神戸(旧グリーンピア三木)の再建、農林中金バリューインベストメンツとの協業やUSJ時代に頓挫した沖縄テーマパークへの挑戦などが発表されていたが、さらに2020年に入り、西武園ゆうえんちのリニューアルやセガサミーと組んだ横浜IRへの取り組みも発表され、その勢いは止まるところを知らない。ダイヤモンド社より刊行された『苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』もベストセラーとなっている刀CEO・森岡毅氏に、刀の2年間を振り返ってもらい、未来への展望を聞いた。(取材/ダイヤモンド社・亀井史夫)

#13
プログラミングを学ぶにはコツがある。まずはごく基本の約束事や構造をきちんと押さえることだ。プログラミングスクール、コードキャンプの講師陣がレクチャーする。
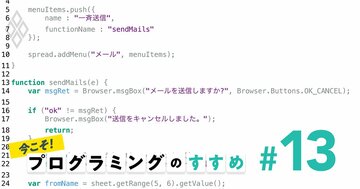
第12回
刀の本質はクライシスマネジメント森岡毅が語る刀起業の真実(2)
USJ復活の立役者として知られる森岡毅氏が2017年に始動した「株式会社 刀」の動きが、このところ活発になっている。同社の取り組みは、丸亀製麺やネスタリゾート神戸(旧グリーンピア三木)の再建、農林中金バリューインベストメンツとの協業やUSJ時代に頓挫した沖縄テーマパークへの挑戦などが発表されていたが、さらに2020年に入り、西武園ゆうえんちのリニューアルやセガサミーと組んだ横浜IRへの取り組みも発表され、その勢いは止まるところを知らない。ダイヤモンド社より刊行された『苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』もベストセラーとなっている刀CEO・森岡毅氏に、刀の2年間を振り返ってもらい、未来への展望を聞いた。(取材/ダイヤモンド社・亀井史夫)

第11回
「最初の半年間は給料も払えなかった」森岡毅が語る刀起業の真実(1)
USJ復活の立役者として知られる森岡毅氏が2017年に始動した「株式会社 刀」の動きが、このところ活発になっている。同社の取り組みは、丸亀製麺やネスタリゾート神戸(旧グリーンピア三木)の再建、農林中金バリューインベストメンツとの協業やUSJ時代に頓挫した沖縄テーマパークへの挑戦などが発表されていたが、さらに2020年に入り、西武園ゆうえんちのリニューアルやセガサミーと組んだ横浜IRへの取り組みも発表され、その勢いは止まるところを知らない。ダイヤモンド社より刊行された『苦しかったときの話をしようか ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」』もベストセラーとなっている刀CEO・森岡毅氏に、刀の2年間を振り返ってもらい、未来への展望を聞いた。(取材/ダイヤモンド社・亀井史夫)

第241回
筆者が本連載でコロナ禍に関連して「9月入学・始業」を主張した直後、この議論は急速に拡大。4月29日には安倍晋三首相が導入を検討する意向を表明するまでに至った。今回は「9月入学・始業」を絶対に導入すべき3つの理由について、教育現場の具体例を交えながら論じていきたい。

#8
英語の民間試験と記述式という“2本の柱”がなくなったら、センター試験と共通テストの違いはほとんどないのではないかと思う人もいるかもしれない。だが、実はセンター試験と共通テストでは、配点、出題形式などで大きく変わる部分がある。
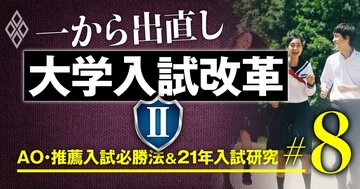
#7
AO・推薦入試の志望者が増加した大きな要因は、2021年度の入試から開始される共通テストへの不安だ。柱だった英語の民間試験採用と記述式の導入が見送られ、入試改革はどうなるのか。
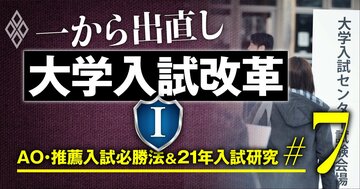
【中学受験への道】第63回
コロナ禍で「自宅リモート学習元年」となった学校と家庭で起きていること
感染が拡大する新型コロナウイルス。在宅生徒に向け遠隔で授業を行うため、各校はぎこちないながらも、いや応なしのICT(情報通信技術)の活用を始めている。現場はどのような状況になっているのか。緊急アンケートの結果も踏まえながら見ていこう。
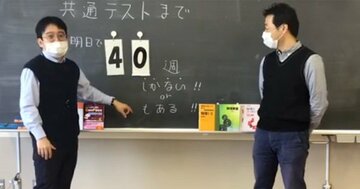
予告編
MARCH、関関同立、難関大「AO・推薦入試」入学術徹底研究!
大学入学者の半数がAO・推薦入試を利用する時代に突入した。本特集では、関東の人気私立大学群の「MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)」、関西の人気私立大学群の「関関同立(関西・関西学院・同志社・立命館)」をはじめ、難関大学のAO・推薦入試対策を徹底的に研究、「狙い目の大学」から「受かる志望理由書の書き方」までを大公開。さらに、迷走する大学入試改革の行く末についても実情を取材した。4月27日(月)から5月5日(火)までの全9回でお届けする。
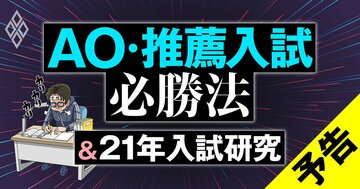
日常的にインターネットで検索するようになり、「ググる」という言葉が一般化したのは、いつからだろう。私たちは何かにつけて、すぐググってしまう。気になることがあるとき、レポートを書くとき、晩御飯の献立を考えるとき。頭で考えるよりも先にググることすら、既に誰もが経験済みだろう。

第68回
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、今や日本での産業活性化の合言葉になっている。もともとは「デジタル情報技術の普及により、人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる」という概念だった。それがビジネスの世界で使われるようになり、「デジタル情報技術により、企業の事業範囲やビジネスモデルを根底から変化させる」という意味合いとなった。

#3
ハードルが高い東大・京大の推薦入試。過去5年で合格者を輩出している高校をランキングした。東大の1位は広島の有名進学校、広島高校。京大の1位は文武両道で有名な大阪桐蔭高校。一般入試でも東大・京大に合格者を多数輩出する名門高校が並んだ。
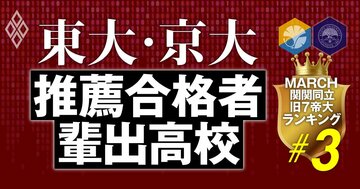
第12回
この生きにくい「資本主義社会」を救出する唯一の方法とは?
主流派経済学は、「現実世界」とはかけ離れた理論体系をつくり上げてきたために、「現実の経済で起きている現象」を正しく説明することができなくなっている。むしろ、主流派経済学から「異端」とみなされてきた、ケインズやハイマン・ミンスキーらの経済学こそが、この生きにくい「資本主義社会」を救出する方法を提供してくれると、中野剛志氏は語る。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第11回
なぜ、「経済政策」はいつも間違えてしまうのか?
アメリカの覇権パワーが凋落し、世界経済が縮小へと向かうなか、日本がたしかな国家戦略を立案するためには、「経済力と政治力・軍事力との間の密接不可分な関係を解明する社会科学」の確立が欠かせない……。その問題意識のもと中野剛志氏は、『富国と強兵 地政経済学序説』で地政経済学を提唱した。ただ、現在の主流派経済学では、政治学や地政学、歴史学などとの接続が不可能だという。何が問題なのか? 語っていただいた。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

第10回
世界はすでに、各国が「利己的」にならざるを得ない危険な状況に陥っている
「いま世界は極めて危険な状態にある」と中野剛志氏は指摘する。アメリカの覇権パワーが衰退するとともに、リーマンショック以降、世界経済は停滞に向かっていたうえに、コロナ禍で世界経済は大恐慌以来の景気悪化になると予測されているからだ。にもかかわらず、日本はいまだに冷戦構造下の国家政策に安住しようとしているのは危険すぎる。この問題意識から、中野氏が『富国と強兵 地政経済学序説』で提唱するのが地政経済学の確立だ。(構成:ダイヤモンド社 田中泰)

「世紀の大偉業だ」関係者がこう称えたのは、京都大学数理解析研究所の望月新一教授だ。これまで未解明だった数学の超難問「ABC予想」を証明したとする論文を2012年に発表し、その正しさが認められたことで、同研究所が編集する専門誌「PRIMS」(ピーリムズ、発行は欧州数学会)に掲載されることが決まった。京都大学によると、論文はA4サイズにして約600ページで構成された大作である。
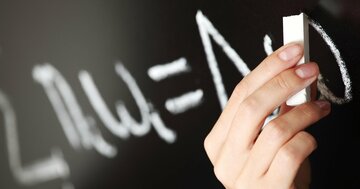
第4回
「TEDで話題の独学術」の超技法!“覚えたいこと”を「手続き化」するだけで極端に忘れにくくなる!
あらゆる種類のスキルの習得に使える「ウルトラ・ラーニング」という勉強法が話題だ。このメソッドを体系化したスコット・H・ヤングは、「入学しないまま、MIT4年分のカリキュラムを1年でマスター」「3ヵ月ごとに外国語を習得」「写実的なデッサンが30日で描けるようになる」などのプロジェクトで知られ、TEDにも複数回登場し、「世界の勉強法マニア」たちを騒然とさせた。本連載では、この手法を初めて書籍化し、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった話題の新刊『ULTRA LEARNING 超・自習法』の内容から、あらゆるスキルに通用する「究極の学習メソッド」を紹介していく。

昨年12月3日に公表された国際学習到達度調査(PISA)で、日本の読解力は15位と、前回調査時の8位から大幅に順位を落とした。その要因として、よく指摘されるのは読書習慣の低下だが、話はそう単純ではないという。元文部科学省主任視学官で、今回の調査結果の分析にも関わった川村学園女子大学の田中孝一教授に詳しい話を聞いた。

新型コロナウイルスの影響により学校が休校し、家庭で過ごす子どもが増えている。こうした中、子どもの勉強不足について不安に思う親たちは多いのではないか。だが、こういう時期だからこそ、子どもと向き合う時間は貴重なもの。『伸びる子どもは○○がすごい』(日本経済新聞出版社)の著者である榎本博明氏は、早くから勉強するよりも大切なことがあると説きます。
