その他産業(7) サブカテゴリ
第128回
世界最大の家電メーカーの座に君臨するサムスン電子。2012年に売上高約16.5兆円、営業利益約2.4兆円を記録した巨大企業の主力商品は、どのような仕組みで伸びているのか。
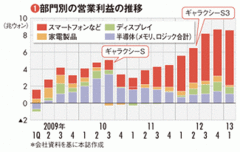
第5回
「ものづくり」こそが日本産業の要であり、これからも我々の生活を豊かにする――。よく耳にするこの言葉は、果たして本当なのだろうか? MITもインド辺境で出会って衝撃を受けた、「自分の暮らしを変える力」としてのものづくり、そして世界中が注目する「ファブラボ」の可能性に迫る。

第898回
「(造船業は)そんなに稼げない。早くそれに気づいて撤退するか、他の業態に変換するべきと思う。これは、ちょっと言い過ぎかな」。都内で“年に1回開かれる事業方針説明会”の席で、今治造船の檜垣幸人社長はおどけてみせた。あまりオモテ舞台に出ることをよしとしない今治造船だが、国内の造船メーカーと違って積極展開を見せる。
![円高修正で韓国・中国勢に“挑戦状” 今治造船グループが仕掛ける反転攻勢[ロングバージョン]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/4/2/240wm/img_42ea07492f2265909281a335c388f15e69289.jpg)
第120回
昨年12月に官民から1500億円の支援を受けることが決まったルネサスエレクトロニクス。しかし、出資金はまだ振り込まれず、経営計画は白紙の状態が続いている。

第4回
よい素材、高価なテクノロジーを使ったからといって、よい「もの」がつくれるとは限らない――。よく聞く言葉だが、その本質を理解しているだろうか? いま途上国で起こっている「ゴミ」を「資源」にした産業革命とも言える事象を読み解く3つの切り口から、真に必要な素材を見る「目」の養い方に迫る。

第897回
日本の二大トイレメーカーの戦略の違いが際立っている。飽くなき買収戦略に突き進んでいるのがLIXILグループだ。鍵を握るのがM&Aやアライアンスの積極活用だ。一方、世界トップのTOTOの海外展開は“自前主義”。稼ぎ頭の中国には30年以上前に進出し、メルセデスベンツと並ぶ庶民の憧れのブランドに育て上げた。

第896回
韓国・中国勢に対する“挑戦状” 今治造船グループの反転攻勢
「(造船業は)そんなに稼げない。早くそれに気づいて撤退するか、他の業態に変換するべきと思う」。「これは、ちょっと言い過ぎかな」。都内で“年に1回開かれる事業方針説明会”の席で、今治造船の檜垣幸人社長は、目をキョロキョロさせておどけてみせた。国家の全面支援を受けて東アジアの市場を席巻してきた「韓国・中国勢の動向に関して」と断った上での発言だが、理由がある。

第3回
使い手の顔、見えていますか?――「使い手の声=ニーズ」をつかむことは、ものづくりには欠かせない。一方で、日本企業が海外で苦戦していることもまた、この点だという。途上国向けのプロダクトデザイン&ビジネスコンテストで最優秀賞を獲得した著者が語る、「真のニーズ」の聞き取り方とは?

第237回
シャープとの出資交渉が頓挫していた台湾の電子機器受託製造(EMS)最大手、鴻海グループが5月下旬、独自に研究所「フォックスコン日本技研」を大阪に設立して波紋を呼んでいる。同研究所の代表を務める、元シャープの液晶開発幹部の矢野耕三氏が本誌のインタビューに応じ、今の心境を語った。

第890回
6月27日の午後7時半、東京・青山の瀟洒なレストランで、日本の造船業の将来を占う調印式がひっそりと開かれていた。集まったのは、日本とブラジルの船舶・海洋業界を結ぶ立役者ばかりだった。日本からは、IHIの釡和明会長と斎藤保社長、ジャパンマリンユナイテッドの蔵原成実会長と三島愼次郎社長、日揮の重久吉弘グループ代表と竹内敬介会長ほか。

第125回
度重なる事故で長期停止した千葉製油所が今月、再稼働を果たす。有利子負債が8429億円にまで膨らむなど財務は大幅に悪化している。会社が主張する通りに再建の道筋はついているのか。
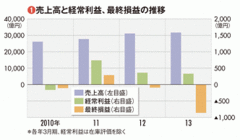
第2回
僕たちは、意味のある〈もの〉をつくれているのだろうか? ――実際にプロダクトデザイン&ビジネスコンテスト「シード・コンテスト」に参加した著者が、課題を抱える現場である東ティモールを訪れることで経験した、〈ものづくり〉が本来持っている「人と人とをつなぐ」という力とその効果とは?

第124回
歌舞伎座が2013年4月2日に開場したが、併設するタワービルを含めた総工事費は430億円。親会社の松竹には1000億円を超える有利子負債負担が重くのしかかる。

第233回
「ダンロップ」や「ファルケン」ブランドのタイヤを手がける住友ゴム工業。新興市場開拓をどうするのか、池田育嗣社長に迫った。

第1回
かつて豊かになることを約束してくれた〈ものづくり〉は、もう僕らを豊かにしてくれないのか?――挫折した一人の起業家が見つけた、ものづくりが本来持つ可能性を通して、大量廃棄が前提の時代で傷ついた使い手=消費者と作り手=生産者をもう一度つなぐ「ソーシャル・ファブリケーション」に迫る。

第232回
2月の社長就任会見では、西田厚聰会長と佐々木則夫社長(当時。現副会長)という首脳級2人の経営をめぐる価値観のズレが明らかになった東芝。その中で田中新社長がいかに独自色を出せるか。

第884回
6月13日、川崎重工業は、臨時取締役会で、半ば強引に三井造船との経営統合の交渉を進めていたという理由から、長谷川聡社長ら3人の役員を電撃解任した。“株主総会前の造反劇”という異例の事態は、産業界のみならず、一般社会からも注目されることとなった。

第231回
高成長を支えた液晶ガラス事業に依存した収益構造から、どのように脱却するのか。新興市場と次世代商品の拡大戦略について聞いた。

第882回
富士山の世界遺産登録で外国人客獲得狙う旅行会社
富士山の世界文化遺産登録が決まった。もともと富士山は多いときで月4000人以上の外国人が訪れる人気スポット。それだけに、旅行会社も外国人の富士山旅行に熱が入る。

第230回
石油元売り各社は燃料油事業の構造改革と新たな収益源の確保に迫られている。新たなトップの下、出光興産はどんな手を打つのか。
