
中野豊明
第1回
就職先として人気が高いコンサルティング業界。コンサルは華やかでスマートな職業とイメージする人も多いが、かつては長時間労働とハードワークが常識であり、非常に「泥くさい」職種でもある。ハードワークは、意識的にも技能的にも短期間で若手を育てあげるという大きな利点もあった。それが「働き方改革」などで不可能になった今、大手コンサル会社ではどのような方法で「プロ意識」を醸成すべきかが課題となっている。

9月に入り、日本における新型コロナウイルスの新規感染者の発生状況は少し落ち着いたようにも見える。このタイミングで、当初のコロナショックにおいて、企業内で進めてきた多くの検討課題を、まるで「なかったこと」のように、ストップしてしまっていることはないだろうか。
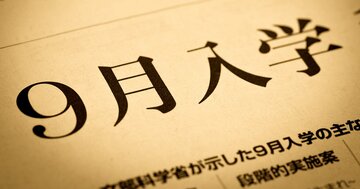
今回の東京都知事選でも圧勝した小池百合子氏。新型コロナウイルス対策や学歴詐称疑惑など、最近は何かと話題の小池氏だが、一連の発言やその後の物事の進め方を見ていると、どこの会社にでもおそらくいるであろう「火消し役」と呼ばれるリーダーの存在を想起してしまう。火消し役は、マネジメント層の評価は著しく高いが、現場の人々から見るとかなり厄介な側面を持つ。

4月以降、新型コロナウイルスによる影響が追い打ちをかけたとされる「コロナ倒産」の事例が報道されつつある。今後も「コロナ不況」はしばらく続くとみられ、企業の倒産・廃業は増えると予想される。特に増加が懸念されるのが、若い女性が少なく、人口流出・少子化が進み、存続が危ぶまれる「消滅可能性都市」が多い都道府県だ。

コロナ禍は社会に大きな影響を与えた。生活様式を一変させてしまい「ニューノーマル」と呼ばれるようになった。職場の人間関係や仕事の進め方も一変し、「世代間の認識ギャップ」や「価値観の違い」なども合わさって「大きな時代の波」となって押し寄せて来る。あなたは変化に対応できるだろうか。

これからウイズコロナの期間を迎えると、企業は出社と在宅勤務の社員が併存する。そこで、大きな問題となるのは人事評価だ。果たして、公平な人事評価は可能だろうか。

現在の景気回復期間がバブル期はもとより、「いざなぎ景気」も超えて戦後2番目の長さとなった。景気は循環するものであり、悪いときも必ず来る。社内でプロジェクトを立案し、実行する際はそれを忘れてはならない。

かつて隆盛を極めた企業が環境変化に追従できずに没落してしまう大きな原因の一つに「大企業病」があるのは明らかだが、管理部門を見れば、必ず兆候が見られる。

既存の市場や価値観を全く異なるものに変えてしまう起業家や企業は「創造的破壊者」と呼ばれる。最近の創造的破壊者にはどんな傾向や特徴が見られるのか。解説してみよう。

「人材の成長」には、成功や失敗を問わず、さまざまな経験の蓄積が欠かせない。しかし、それだけでは成長に限界がある。マンネリ化や過信に陥らないためにも、考え方の基本やテクニックをきちんと身につける必要がある。

さまざまな国のビジネスマンから構成されるグローバルプロジェクトに参加してみると、自分が先入観で持っていた各国の国民性というものをいい意味で裏切る人柄を持つ人物と触れ合う機会がある。その例をご紹介したい。

特定領域にやたら強い専門家や職人のような人材は、どの会社にもいるだろう。本人がそれを「縛られている」と考える場合は少々問題だ。まさに、あなたがそう感じるのなら、どういう解決方法があるのだろう。

優れたビジネスマンは、コミュニケーション能力が高い。会話も楽しいし、プレゼンテーションもわかりやすい。シンプルな心構えをしておくだけでも、あなたのコミュニケーション能力やプレゼン能力は高めることができる。

常識的な社会人のふるまいとして、ホウレンソウ(報告、連絡、相談)の励行が言われて長い年月が経つ。しかし、最近はあまりにホウレンソウに依存する人間がスピーディーな業務完了を妨げるケースも増えている。

海外のビジネスマンと会議をして最初に気がつくことがある。多くの日本人ビジネスマンは最初に「落としどころ」のイメージをもって会議に臨むが、そんなことをするのは日本人だけだ。

多くの日本企業では、中長期経営計画を作成している。現場は必死になって作成するが、外部から見れば、どこもあまり変わり映えしないもので、労力の割には有効性という点で疑問を抱くような計画が少なくない。

TOIECは900点以上、英語のプレゼンや会議はお手のもの、外国人からどんな質問が来てもスラスラと回答するというビジネス英語の達人でも「ホームパーティーや会食は苦手」という日本人ビジネスマンは少なくない。
