竹田孝洋
日本銀行は1月の政策決定会合で利上げに踏み切った。しかし、経済の現況は12月の前会合時に挙げた要件を満たしてはいない。利上げのチャンスを逃すまいと前のめりになった日銀の姿が浮かび上がる。

#1
基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの適用期間を一致させ、基礎年金の底上げを図る案が厚生労働省で検討されている。改正されれば若い世代は受取額が増加するが、高齢者世代は受取額が減少する。非正規雇用の多い氷河期世代のためにも基礎年金の底上げは重要だが、財政負担の増加をどう判断するか。
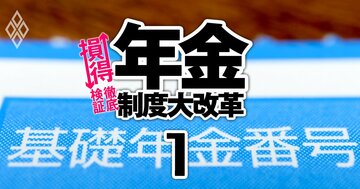
予告
年金制度大改革の<損↓得↑>を徹底検証!5年に1度の大改正であなたの受取額はどう変わる?
2024年の財政検証を受けた公的年金の改革案が厚生労働省から示された。この改革によって個人の受取額は増えるのか、減るのか。企業の負担や働き方はどう変わるのか。年金の仕組みや改革による損得を、ダイヤモンド編集部が徹底検証する。

#22
終戦後の焼け野原状態から80年。日本経済は高度経済成長期やバブル経済に代表される隆盛と“失われた30年”という停滞を経験した。東京大学名誉教授の伊藤元重氏に戦後の歩みを解説してもらうとともに復活の処方箋を示してもらった。
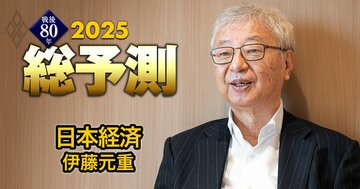
#10
高関税政策を公約する米国のトランプ次期政権、中国経済停滞など不透明な要因が多い中で、2025年の日本の景気はどうなるのか。10人のエコノミストに成長率、物価上昇率などについて聞いた。

米大統領選挙でドナルド・トランプ氏の復権が決まった。トランプ2期政権で、米国や日本の経済、株・為替市場はどう動くのか。BNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏とみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介氏に緊急対談で予測してもらった。対談の後編では、トランプ氏の政策が日本経済や日銀の金融政策に与える影響を検証する。

米大統領選挙でドナルド・トランプ氏の復権が決まった。トランプ2期政権で、米国や日本の経済、株・為替市場はどう動くのか。識者2人に緊急対談で予測してもらった。

衆議院議員選挙の結果は自由民主党、公明党両党合わせても過半数割れという与党惨敗となった。今回の選挙前後の株価の動きは、投票日前に下落、自民過半数割れでも上昇というこれまでの経験則に反するものだった。その理由を検証するとともに、為替動向も含めて相場の先行きを分析する。

#8
米大統領選挙の結果がマーケットに与える影響について、為替市場、株式市場の専門家12人にアンケートを実施した。「もしトラ」「もしハリ」で為替・株はどう動くのか。注目ポイントは何か。プロたちの見解の詳細をお届けする。

#4
大統領選挙の帰趨で米国の政策が変われば、米国に進出している日本企業の業績に影響する。また、直接進出していなくても、金融市場や米国におけるトレンドの変化が日本企業の先行きにインパクトをもたらすこともある。トランプ氏、ハリス氏の公約が実現された場合に日本株で浮かぶ銘柄、沈む銘柄はどれかを徹底検証した。

#3
米大統領選の結果は日本株へどう影響するのか。「もしトラ」で減税による景気浮揚、インフレ率と米金利の上昇となりドル高円安進行となれば、日本株にプラスに作用するだろう。「もしハリ」は為替同様、インパクトが小さいとの声もあるが、法人増税、キャピタルゲイン増税で米国株下落なら日本株にマイナスに働く。6人の識者に株価への影響に加えて、トランプ氏、ハリス氏それぞれが大統領に就任した場合に有利になるセクター、不利になるセクターを挙げてもらった。
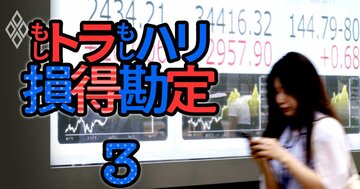
#2
「もしトラ」「もしハリ」で為替相場はどう動くのか。トランプ氏の政権復帰でインフレ率が上昇すればFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げペースは鈍化し、場合によっては利上げに転じる可能性がある。そうなればドル高が進むだろう。ハリス氏当選の場合は、為替相場には大きな影響を及ぼさないとみる市場関係者が多い。6人のストラテジストの見方を紹介する。

#1
トランプ氏の公約である関税引き上げは輸入価格を引き上げ、移民抑制は労働需給逼迫を通じてインフレ圧力を高めることは確実だ。一方、法人税増税をはじめとする増税の公約の多いハリス氏の施策は、成長率を押し下げることになりそうだ。

#9
2028年3月期からオペレーティングリースのバランスシートへの資産計上が義務付けられる。影響の大きい業種はどこなのか。日本基準の上場企業全体について、新リース会計基準の適用による財務悪化リスクの高い企業を独自に試算したランキングを掲載する。

#8
商品をメーカーから仕入れて小売業者やユーザーに販売するのが卸売業である。会社によって扱う商品は異なる。リースの対象となる物件も違ってくる。新リース会計基準の適用による財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位11社を掲載する。

#7
倉庫・運輸業は主力事業が陸運業と重なる部分が多い。そのためリースの主な対象も陸運業と同様に物流施設である。倉庫・運輸業界で新リース会計基準の適用による財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位7社を掲載する。

10月1日、自民党の石破茂総裁が首相に選任された。石破政権は株価急落、円高進行といった波乱の船出となった。しかし、これは高市早苗首相の誕生を織り込んで進んだ株高・円安の剥落に過ぎない。実は、石破政権の政策のかじ取り次第では、日経平均株価が4万円台を回復するシナリオも存在する。

#6
トラックなど車両や、倉庫など物流施設は、陸運業に不可欠な設備だ。自社所有しているだけでなくリースでも調達している。陸運業界で新リース会計基準の適用による財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位17社を掲載する。

#5
情報・通信業の会社は、一見リース取引とはあまり縁がなさそうに見える。製品・商品そのものが製造業のように大きな設備を必要としないからだ。しかし、情報・通信業にも新リース会計の適用で大きな影響を受ける会社が存在する。情報・通信業界で財務悪化リスクの高い企業を独自試算でランキングし、上位45社を掲載する。
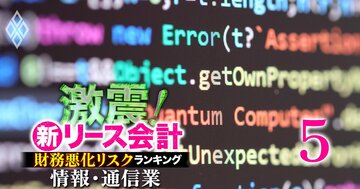
自民党総裁選に立候補した上川陽子外相が、ダイヤモンド編集部の単独インタビューに応じた。成長戦略とその分配の在り方、成長力を強化するための産業政策、増大する社会保障費の負担などについて語ってもらった。
