大崎真澄
個人がプロの建築家に注文住宅の間取りを手軽に依頼できる「madree(マドリー)」が事業を広げている。展示場などに行かずとも、スマホを使って自宅から簡単に相談できるのが特徴。希望する条件などをサイト上で記入していくと、プロが作った質の高い間取りが自分の元に届く。

個人の決済だけでなく、企業の決済領域においてもデジタル化の土壌が整い始めている。中でも複数のフィンテック企業が事業を展開し、市場が広がってきているのが「法人カード」を軸とした金融サービスだ。

ウェブサービスやモバイルアプリを手がける企業にとって、開発したものが自分たちの期待通りに動くかを検証する「ソフトウェアテスト」は不可欠な仕事だ。テスト市場は世界で1.3兆ドルにも及ぶ巨大市場であり、IT予算の3分の1をテストが占めるとも言われる。その反面、いまだに70%以上もの企業が時間と手間のかかる“手動テスト”に頼っている状況で、変革できる余地も大きい。その市場に“AIを活用したテスト自動化”というアプローチで挑むのがAutifyだ。

3DCGを活用することで未竣工物件の室内空間を自由に歩き回れる“VR内覧”を通じて、新築マンションの購入検討をサポートする「ROOV」の活用が広がっている。コロナ禍の緊急事態宣言によってマンションギャラリーへの集客が制限されたことにより、従来主流となっていた大量集客と複数回の対面商談を中心とした販売手法の見直しが急務となった。そこでオンライン接客を後押しするROOVのニーズが高まったかたちだ。

個人が未上場のベンチャー企業に“エンジェル投資家”として投資ができる、株式投資型クラウドファンディング(CF)。2020年7月にこの領域でサービスを始めたイークラウドが、約3億円の資金調達を実施してさらなる事業拡大を見据えている。

日本でも一見“レッドオーシャン”に見える業界はいくつか存在するが、不動産賃貸サービスはその代表例だ。SUUMOやLIFULL HOME'Sを筆頭に複数の大手プレーヤーが存在し、検索エンジンを使ってウェブから物件を探せば多数のポータルサイトに行き当たる。そのような市場において既存の事業者とは異なるアプローチからこの市場に入り込み、着実に成果を積み上げてきたのが物件探しアプリ「カナリー」を展開するBluAgeだ。
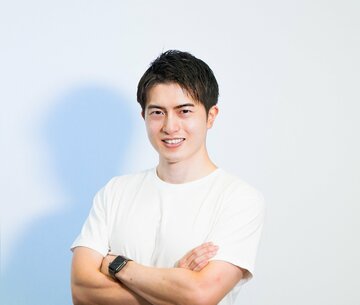
ECが普及すればするほど、事業者を後押しするようなサービスや消費者の購買体験をより良くするサービスのニーズが高まり、そこに新たなビジネスチャンスが生まれる。一見地味に思える「商品の返品業務・返品体験」のアップデートもその1つと言えるだろう。

「広告クリエイティブの民主化」を見据え、独自のマーケティング動画生成サービスを展開するリチカが事業を拡大している。プロのノウハウを活用した成果の出るマーケティング動画を簡単に作れるサービスを武器に、大手事業会社など累計400社以上にサービスを提供してきた。

印刷、物流、テレビCM──。設立から約10年の間に異なる3つの業界で立て続けに事業を立ち上げ、急成長を遂げてきたラクスル。直近では新たに4つ目の柱となる「ジョーシス」をローンチし、さらなる事業拡大も見据えている。そんな同社ではどのような考え方で事業領域を選定し、サービスを育ててきたのか。創業者で代表取締役社長CEOを務める松本恭攝氏に聞いた。

今後2〜3年で100億円規模の事業投資を行い、グローバルで数億ユーザーを目指す──。ゲームやメディアを軸に複数の事業を展開してきたグリーが、次の柱として大きな期待を寄せているのが「メタバース」事業だ。中核を担うのが100%子会社であるREALITY。同社が手掛ける「REALITY」は2018年8月にVTuberのライブ配信が視聴できるアプリとして産声を上げ、そこから現在の“アバターを用いたバーチャルライブ配信アプリ”へとアップデートを重ねてきた。そして8月、このREALITYを軸にメタバース領域で大規模な投資を行っていく方針を打ち出した。

カスタマーサクセスを実現するための取り組みの一環として、今にわかに注目を集めているのが顧客コミュニティを活用した“コミュニティタッチ”だ。カスタマーサクセスプラットフォーム「commmune(コミューン)」運営元のコミューンでは、企業のコミュニティ運営を後押しすることで事業を急成長させている。

会社に届く郵便物を、“メールと同じように”ウェブ上で確認できるようにする──。そんなアイデアを形にしたクラウド郵便サービスの「atena」が事業を拡大している。約1年前に法人向けのサービスとしてリニューアルして以降はIT企業を中心にさまざまな業界で利用が進み、直近半年で導入社数は約1.5倍に増えた。導入企業の1社であるZOZOではリモート環境でも紙の請求書の処理ができるようになり、作業時間が約100分の1以下に減少した例もあるという。

20代前半の学生たちが、次世代に向けて「屋根から自然エネルギー100%の未来を創る」ことを目標に立ち上げたスタートアップがある。複数台の電気自動車(EV)をエネルギーストレージとして有効活用するための“充放電システム”を手がけるYanekaraだ。

AIとデータを活用し、最適な生産量や販売量を高い精度で予測する──。いわゆる「AI需要予測」は製造業や小売業を始めさまざまな領域で社会実装が進んでいる。薬局における「医薬品の発注」もまさにその一例だ。「この薬がもっと必要になる気がするから、ひとまず3箱分買っておこう」といったように担当者の“勘や経験”に頼りがちで、結果として欠品や廃棄ロスが課題になっていた。業務負荷の軽減という観点からも、AIを活用して需要予測や在庫管理の質を改善する価値は大きい。薬局向けのクラウド型電子薬歴システム「Musubi(ムスビ)」で薬局のDXに取り組んできたカケハシでは、そんな在庫管理のためのサービスを9月8日より開始した。

ビジネスSNS「Wantedly」を運営するウォンテッドリーが、“エンゲージメント領域”で事業を広げている。2020年3月に福利厚生サービス「Perk」のベータ版をリリース。それ以降も同年4月にオンライン社内報サービス「Story」のアルファ版、同年6月にはチームマネジメントツール「Pulse」のアルファ版を連続して立ち上げ、従業員の定着や活躍を後押しするための事業に力を入れてきた。ウォンテッドリーでは1年以上にわたってブラッシュアップしてきたこれらの3サービスを、「Engagement Suite(エンゲージメント スイート)」として9月2日より本格的に展開を始める。

印刷・集客支援プラットフォーム「ラクスル」を皮切りに物流領域の「ハコベル」、広告領域の「ノバセル」と事業を拡張してきたラクスル。同社がこれらに続く第4の事業として、コーポレートIT領域の“不”を解決する新サービスを始める。9月1日に正式ローンチした「ジョーシス」はITデバイスとSaaSの統合管理プラットフォームだ。従業員の入退社に伴うデバイスの購入・返却やSaaSアカウントの発行・削除、在籍中の権限管理などを効率化することで、情報システム担当者をアナログな業務から解放したいという。

近年の気候変動に伴う自然災害や新型コロナウイルス感染症の影響により、企業における「サプライチェーンリスクマネジメント(SCRM)」の重要性が高まってきている。原材料の調達先や生産拠点が一部の地域に偏りすぎていると、現地が予期せぬトラブルに見舞われた際に深刻なダメージを負ってしまうリスクがある。実際に中国でコロナの感染拡大が進んだ結果、同国に依存していたサプライチェーンが途絶えてしまい、計画の大幅な変更や下方修正を余儀なくされた企業も少なくない。このような課題の解決策としてスタートアップのResilire(レジリア)では2021年5月よりサプライチェーンリスク管理プラットフォーム「Resilire」を運営してきた。同社では1億5000万円の資金調達を実施し、さらなる事業拡大を目指すという。

「データドリブンな病院経営」の実現を目指すメダップでは、第一弾のプロダクトとして“中規模・大規模病院向けのSalesforce”と言えるようなプロダクトを展開している。大規模な病院を経営するには地域のクリニックや医療機関の存在が欠かせない。入院患者のうちの約6割は地域の医療機関からの紹介経由であり、病院にとっては患者はもちろんのこと、そうした医療機関が重要な“顧客”になっている。この顧客との関係性構築をデータを用いて支援するのが「foro CRM」の役割だ。同サービスでは従来散らばっていたデータを一箇所に統合することで、それを基にさまざまな分析やアクションができる。

個人向けの家計簿サービス「マネーフォワード ME」やクラウド会計を軸としたバックオフィス効率化SaaS「マネーフォワード クラウド」など、フィンテック領域を中心に複数のサービスを手掛けるマネーフォワード。同社が新たに“社内で増え続けるSaaS”を効率的に管理するためのサービスを始める。新サービスの名称は「マネーフォワード IT管理クラウド」。グループ会社のマネーフォワードiを通じて運営する。まずは導入中のSaaSを一元管理できる機能などをベータ版として提供。2021年中を予定している正式版のローンチに向けて、対応するSaaSの拡充や機能追加を進めていく計画だ。

近年日本では“CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)ブーム”と言っても過言ではないほど、さまざまな企業がCVCの立ち上げに乗り出している。東京ディズニーリゾートの運営企業としてお馴染みのオリエンタルランドもその中の1社だ。2020年6月に全額出資の子会社としてオリエンタルランド・イノベーションズ(以下OLI)を設立した。今年に入ってすでに4社への投資を発表している同社は、なぜ今ベンチャー投資に力を入れるのか。その背景や展望について聞いた。
