
岡野雄志
新NISAを相続したら税金はどうなる?専門家が解説「大増税時代の相続対策」
今年3月、一時的ではあるが日経平均株価が4万1000円台に乗せたことで、市場が大いに賑わった。しかし、記録的な円安が続いており、相変わらず日本経済の先行きは不透明だ。さらに4月末、自民党が医療・介護保険料を算出する根拠として、新たに「金融所得」を反映するという議論が報道された。新NISAが始まって間もないが、投資への努力が生活の足かせとなる可能性が出てきている。魅力的な新NISAには、知っておきたい「相続時のリアルな注意点」もある。今回は新NISAについて、口座相続時のリアルな注意点を解説する。
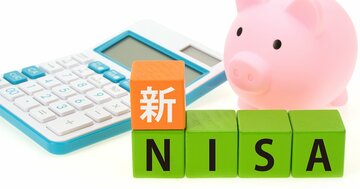
「紀州のドン・ファンの遺言」を親族が認めないワケ、“自筆遺言書”に潜むリスクとは?
紀州のドン・ファン事件を覚えているだろうか。2018年5月に亡くなられた和歌山県の会社経営者 野崎幸助氏(享年77)には、預貯金・有価証券など総額約13億5000万円の遺産があったとされている。この遺産には、遺言書があるとされており、その内容は「全額を田辺市に寄付する」というものだった。遺言書の形式は、A4のコピー用紙のようなものに手書きで書かれているものだったようだ。このような自筆遺言はトラブルの温床とも言われており、現在、法務省は遺言書の「デジタル作成」に向けて準備を進めている。そこで、今回はデジタル遺言書をテーマに、骨肉の争いを防ぐ遺言書の書き方を考察する。

子育て世帯の「生命保険料控除」がおトクに!いくらに拡充?保険を増やすべき?【税理士が解説】
毎年12月に発表されている「税制大綱」をご存じだろうか。今後の税制の行方を決める税制大綱は、翌年度の税制改正や、今後の税の課題をわかりやすくまとめている。2023年末に発表された税制大綱では、少子化対策について深く議論される結果となった。家族の人生を支え、相続対策にも有効な生命保険については、主に控除の視点から触れられている。そこで、今回の記事では2024(令和6)年税制改正大綱に盛り込まれた子育て支援策の3つのポイント、および生命保険の活用法と注意点について、相続対策の視点も交えながら解説する。

こんなハズじゃなかった…廃屋に100人の相続人「負動産」トラブルを防ぐ2つの対策とは?
「田舎に暮らす父親が亡くなった」――。誰もがいずれは経験する家族との別れだが、大学進学や就職などの機会に都心部に引っ越しをした人の中には、地方に暮らす家族の資産状況や暮らしぶりをあまり把握しないまま相続を迎える人もいる。いざ相続が始まったら、家族が残した不動産が、「負動産」だったというケースも少なくない。そこで、今回は「亡父が残した田舎の負動産」をテーマに、相続時によくある落とし穴を解説する。

大谷翔平「1000億円契約」のスゴイ節税効果!10年後に海外移住で所得税チャラも?【税理士が解説】
フリーエージェントとなっていた大谷翔平選手は、米大リーグのドジャースと総額7億ドルで10年契約を結びました。7億ドルを日本円に換算すると(1ドル=145円で計算)、約1015億円。一体どれほどの税負担があるのでしょうか。今回は、大谷選手が居住しているアメリカの税制や、モナコ公国、ドバイの「タックス・ヘイブン」を踏まえて、大谷選手の所得税への節税対策を検討します。

#13
相続税を「払い過ぎて」いるケースは少なくない。そして、税務署はそのことを教えてくれない。過払い相続税を取り戻した三つの事例から、土地の相続で損をしないテクニックを相続税専門の税理士が指南する。

ネットバンキングが普及し、また暗号資産などを所有する人も増えてきた。その所有者が亡くなると、デジタル資産は「デジタル遺産」になる。生前、本人もデジタル資産と意識せずに所有していたものが、相続発生後にトラブルとなるケースも増えている。

政府与党による「令和5年度税制改正大綱」で、贈与税の暦年課税制度による贈与者死亡前3年間の「相続税持ち戻し」が7年間に延長され、話題になっている。今回の大綱には、そのほかにも今後の相続税対策に関わる改正案の記述がいろいろとある。

2022年10月11日、マイナンバーカードに健康保険証を一体化させた「マイナ保険証」の利用に切り替えると政府が発表し、国民や町の医療機関をざわつかせた。事実上、マイナンバーカードの義務化となるかもしれない。気になるのは、やはりマイナンバーの税務への影響だ。

#9
相続税額はどんな税理士でも変わらない。そう感じる人も多いかもしれないが、相続専門の税理士が見直すと、相続税の「過払い」が判明するケースは少なくない。払い過ぎた相続税を取り戻すノウハウや過払いが発生しやすいポイントを、税理士に指南してもらった。
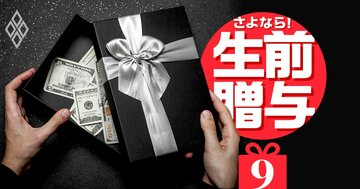
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて」との文言が話題となった令和3年度税制改正大綱だが、翌年の大綱でも具体策は示されなかった。しかし、岸田内閣の「資産所得倍増計画」により、にわかに「相続税と贈与税の一体化」が前進し始めたようだ。

高性能画像生成AIが無料配布され、ネット上で「革命」といわれ話題沸騰となっている。一方、2021年に老舗オークションでNFTアート作品が売り上げ100万ドル(1億4000万円超)を突破するなど、今、デジタルアートが熱い。海外では資産として注目度が高いが、日本ではどうなのだろう?相続税対策としてもNFTアートは有効なのだろうか。

少額から不動産投資でき、不動産管理の必要もなく、Webを介して始められるので、コロナ禍で人気急上昇の「不動産クラウドファンディング」。相続税対策としても注目度が高い。しかし、詐欺事件や横領事件などが相次ぎ、不安を覚える人も多いようだ。

国家公安委員会の特別機関・警察庁長官官房によると、サイバー犯罪は2013年に5741件だったのが、21年には1万2275件に増加しているという。犯罪に巻き込まれる危険性のあるネット利用はもちろん要注意だが、安易な発信が「税務調査」に至る恐れもある。

毎年7月1日、国税庁が公表する「相続税路線価」。2022年分は全国平均が2年ぶりに0.5%上昇した。新型コロナの感染状況が気になるところだが、この夏、久しぶりに家族が顔を合わせたら、ぜひ話し合っておきたいのが「実家の相続」についてだ。

コロナ禍で贈与税の実地調査件数は半減し、その反動で今年は贈与税の税務調査が強化されるのではと予想されている。贈与税の申告漏れのうち、無申告が8割強。「数百万円程度の現金の受け渡しを調べるほど税務署も暇じゃないだろう」と高をくくる向きもあるが、税務調査は税務署員の仕事であって、暇つぶしではない。したがって、プロなりのノウハウもある。

2022年4月19日、注目の「タワマン裁判」は納税者側による最高裁上告が棄却された。「総則6項」を振りかざした国税局側の勝訴となったわけだが、富裕層に多用されている「タワマン節税」は今後どうなるのか。それに代わる有効な相続税対策はあるのだろうか。

一般社団法人日本フードサービス協会(JF)によると、コロナ禍に見舞われた2020年、外食産業全体の売上金額前年比は84.9%に落ち込んだ。特にパブレストラン/居酒屋は50.5%、翌21年も57.8%と厳しい。そんな不況下にあえぐ、パブやクラブなどで働く女性、いわゆる“夜の蝶”に生活費を渡し続けたら、贈与税はどうなる?相続税専門の税理士として事例をもとに解説しよう。

コロナ禍で「巣ごもり投資」「ポイ活投資」などが人気を集め、円安・株高下、空前の投資ブームか!?と言われたのも束の間。ウクライナ情勢による不透明感が世界の株式市場を覆っている。こうした状況下で上場株式を相続したら、どうすればいいのか。

コロナ禍でオークション市場が盛況という。ネット入札でハードルが下がったからか、ステイ・ホームでアートを愛でる時間が増えたからか……。絵画の落札最高額は約510億円のレオナルド・ダビンチ作とされる『サルバトール・ムンディ』だそうだ。では、こういった高額な美術品や骨董品を相続したら、税金はどうなるのだろうか。
