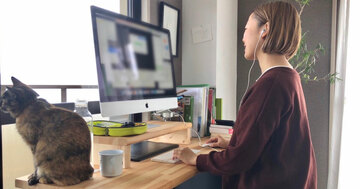ただ、液体ミルクをはじめとした人工栄養の普及にあたり、母乳推進の団体からメーカーや行政に対して疑問の声が寄せられていることも確かだ。
約2万人の乳児を診てきた川口市立医療センターの小児科医山南貞夫氏は、母乳育児の重要性を強調する。
「液体ミルクがあるから母乳はどうでもいいという発想は危険だ。人工栄養には含むことのできない側面が母乳にはある」と液体ミルクの普及によって、母乳育児へのモチベーションが下がることを山南氏は危惧している。
また、母子を取り巻く小児科医にも問題があると鋭く指摘する。適切な指導を行っても母乳が出ない人はごく稀なケースで、「人工栄養を安易に与える医師も多い。母乳か人工栄養かという二択は非常に危険で、あくまでも母乳育児が基本だ」と山南氏は主張する。
液体ミルクを販売したいメーカーは、こうした母乳推進派の声と真摯に向き合うことも必要だろう。また、粉ミルクも含めた人工栄養の市場を巡り、国内メーカーと医療現場の“グレー”な関係を危惧する声も上がる。
世界約50カ国で液体ミルクを販売しているネスレは「日本での販売は検討していない」と明言する。その理由について、「すべての国でWHO(世界保健機関)コードに基づいた企業活動をしている。WHOコードの観点から日本でのビジネス展開は、市場競争においてさまざまな課題があり、参入は難しい」(ネスレ日本担当者)というのだ。
WHOコードとは、「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」のことを指す。この基準は母乳推進のため、人工栄養のサンプルを配布してはならないことや、保健所や医療機関を通じて人工栄養を売り込んではならないことなどを倫理規定として定めている。
この倫理規定について、日本国内で違反した場合の罰則などの法整備がなされておらず、“日本市場はグレー”とネスレは捉えているのだ。
日本では一般的に行われている、病院の産婦人科で粉ミルクのサンプルを渡すという行為は、WHOコードに照らし合わせればグレーだ。
女性の社会進出が急速に進み、共働き世帯も増加の一途をたどる。「イクメン」の浸透をはじめ、男性の育児参加も求められている。液体ミルクの出現で、消費者にとって“選択肢が増えた”ことは間違いない。
海外と比べ、液体ミルクの普及が遅れた日本市場。法整備の遅れに加え、グレーな市場環境が液体ミルクの浸透を阻んできた側面がある。液体ミルクが市民権を得ていくためには、国内メーカーと医療現場のグレーな関係を解消していくことが必要だろう。