「職人的ルーティン」の内側にも
ポテンシャルが隠されている
末永 今回、こうやってアンリさんとお話する機会をいただいて、ぜひお伺いしたいと思っていたことがあるんです。アンリさんは、私が本のなかで書いていた「花職人」という生き方についてどう思われますか?
佐俣 「自分なりの答え」を求めて探究している人、ぼくの表現だと「熱」に基づいて動いている人が「アーティスト」であるのに対し、逆に、外部から与えられた課題に対して「みんなにとっての正解」をつくり続ける人を「花職人」と表現されていましたね。
末永 そうなんです。私は「花職人」としての生き方を否定するつもりはまったくなかったのですが、現実的には上司やクライアントから振られた仕事を「こなしている」人ってたくさんいますよね。そのせいか、この「アーティスト/花職人」という区分に反発を覚える人もいらっしゃったんです。
佐俣 良くも悪くも、「ルーティンをきちんと続けられる人」というのはたしかにいて、ぼくはそういう人たちは素直にすごいと思います。たとえば料理人でも、その店の長年のレシピを本気で守り続けている人はやはり気迫が違いますよね。そういう人を「アーティスト」と呼べるのかはちょっとわかりませんが……。
末永 私としては、職業上の区別として「アーティスト/花職人」を持ち出したわけではなく、あくまでも「ものごとに取り組む姿勢」の話だととらえています。ですから、職人や会社員など、他人のニーズに応えるような仕事に携わっている人も、アーティストとして生きることはできると思っていて。
たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチは、クライアントからの発注に基づいて絵を描く職人だったわけですが、そのプロセスのなかで自分なりの「タネ」を見つけたり、探究の「根」を伸ばしたりしていきましたよね。
佐俣 ルーティンの枠組みのなかで結果を出そうとする人がいる一方、請け負ったオーダー以上のいいものを提供しようとするすごい人は、どの業界にもいますよね。ルーティンをきちんとやり続けられる人はすごいけど、日々新しいことに向けて動ける人も大好きです。どっちも尊いと思いますね。
これに関連して、パッと思い浮かんだのは「お寿司」の世界です。ぼくはお寿司が大好きなんですが、お寿司って「握ったシャリの上にネタを乗せる」という「江戸前ずし」のフォーマットが200年にわたって固定化されているんです。日本中、いや、世界中どこでも、なぜかこの枠組みに従っていて、ほとんど全員がその型を守っている。
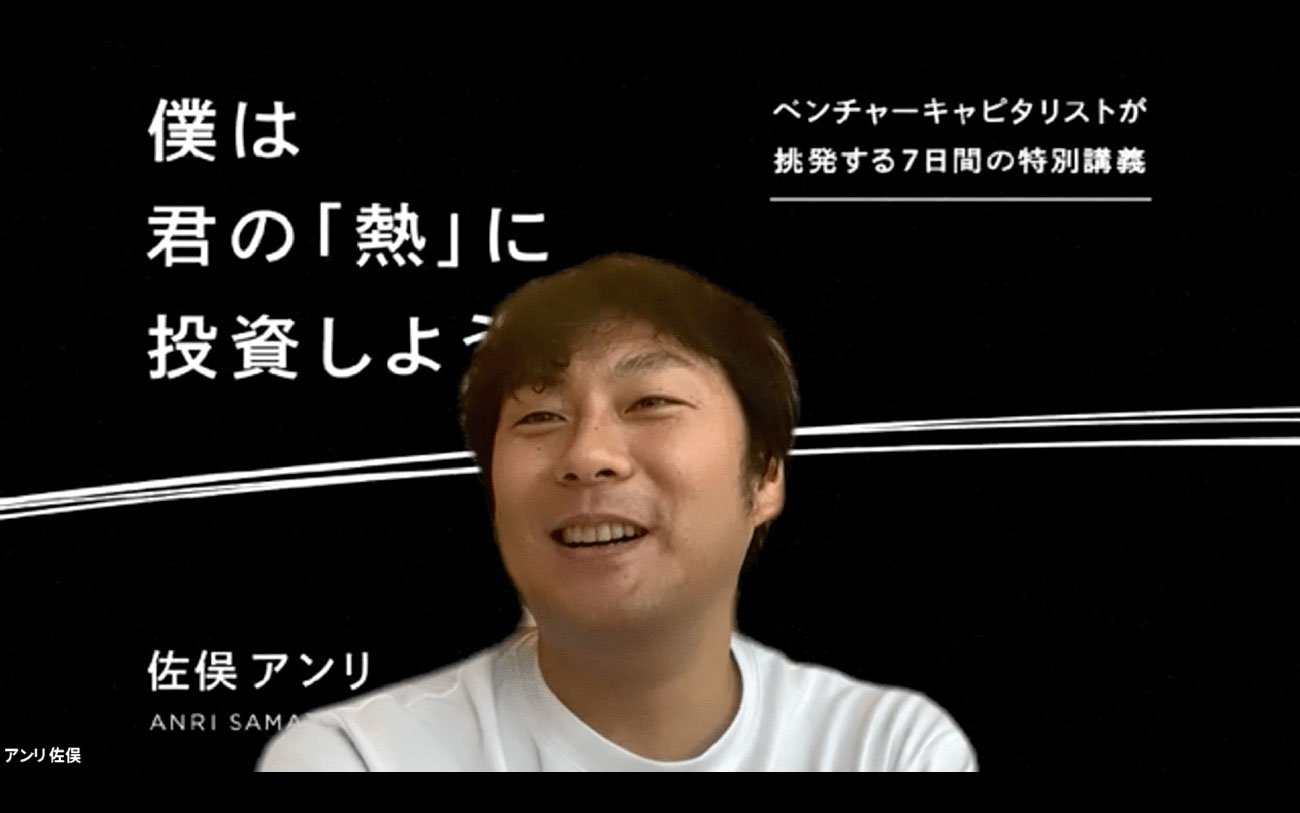
末永 「お寿司=フォーマット」というのは、言われてみればそのとおりですが、すごく斬新なとらえ方ですね。なぜこれがずっと守られているんでしょうか?
佐俣 きっと江戸前というフォーマットが、「うまくできすぎている」んでしょうね。でもじつは、江戸前ずしが生まれたそもそもの経緯をたどると、当時は保存技術がなかったというのと、関東近郊で漁れるのが主に小魚だったという事情があるんです。もはや世界中の魚が鮮度の高い状態で手に入るのに、なぜかいまだに当時のテンプレがずっと使われている。そういう意味では、お寿司って世にも不思議な食べ物なんですよ。
ただ、このフォーマットに縛られていない寿司屋もあります。わかりやすいのは、サーモンだろうがハンバーグだろうがなんでも出す「回転寿司」ですね。
他方で、回転寿司とも違うかたちで、ルーティンを破っていく人たちもいます。ストイックに江戸前ずしをつくり続けていくなかで、「本当に200年前のおいしさを表現しようと思ったら、当時と同じ技術とネタではできないはずだ」という答えにたどりついて、いつのまにか江戸前ずしのフォーマットから離れていくパターンです。
ぼくが毎月必ず一度は足を運ぶことにしている寿司屋の大将は、ずっとそういう探究を続けているので、行くたびに毎回、江戸前ずしとは違う「あたらしいお寿司」が出てきます。
末永 そういう意味では、スタート地点に「自分の好きなこと」がないといけないわけではないのかもしれませんね。たとえ他者から与えられたミッションであっても、それに取り組んでいるうちに、見えていなかった自分の「タネ」が見えてくることもありますから。
よくないのは、外部から与えられた課題に向き合ううちに、アンリさんの言う「違和感」に気づけなくなってしまうこと、「自分だけのタネ」を見失ってしまうことなんだと思います。
「ぼくは『ゼロの人』が好きで好きで仕方ない」
末永 『13歳からのアート思考』は、これ自体が私自身の「タネ」から生まれた「花」なんです。もともと書いた原稿は、まさに「0(ゼロ)」から生まれた「1」でしかありませんでしたが、編集者さんとのやり取りのなかでそれが「10」になり、出版され多くの人の手に渡ることで「100」へと大きく育っていっています。
そして、そのなかで、やはり私はいわゆる「10→100」のプロセスよりも「0→1」や「1→10」に喜びを見出す人間なんだなと再確認したんです。アンリさんはご自身をどういうタイプだと考えていますか?
佐俣 ぼくも「0」から起業したわけですが、ベンチャーキャピタリストとしてはもう10年選手ですから、「0→1」の段階は終えてしまっています。でも、ぼくはやっぱり「0の人」が「すごい人」になっていく過程が何よりも好きなんですよね。
起業家ってなんだかカッコいいイメージがあるかもしれませんが、はっきり言って「こいつ、人前に出して大丈夫か……?」って心配になる人だらけなんですよ(笑)。でも、ぼくはそんな「0の人」が本当に好きで仕方ない。そういう人があっと言う間に、ぼくよりもすごい大経営者になっていくサマを見守るのが最高に楽しいですね。
でも、それで自分の成長が終わったらつまらないでしょう? だから、ベンチャー投資家としての保護者的なスタンスと、1プレーヤーとして挑戦者のスタンス、その両面を持ち続けていたい。爆発的な勢いで成長していく彼らを見ていると、ぼく自身も「負けていられない!」という気持ちが湧き上がってきます。少なくとも、彼らと会話していて恥ずかしくないくらいには、自分も挑戦し続けないとダメだなと思いますね。
ぼくは基本的に怠惰な人間だし、継続的な努力が苦手なので、そこがすごく大きなモチベーション源になっています。「ファンド規模の拡大」を目標にするつもりはありませんが、自分のテンションを維持し続ける意味では、思い切ってファンドを大きくするような難しい挑戦もずっと続けていきたいですね。

(対談おわり)



